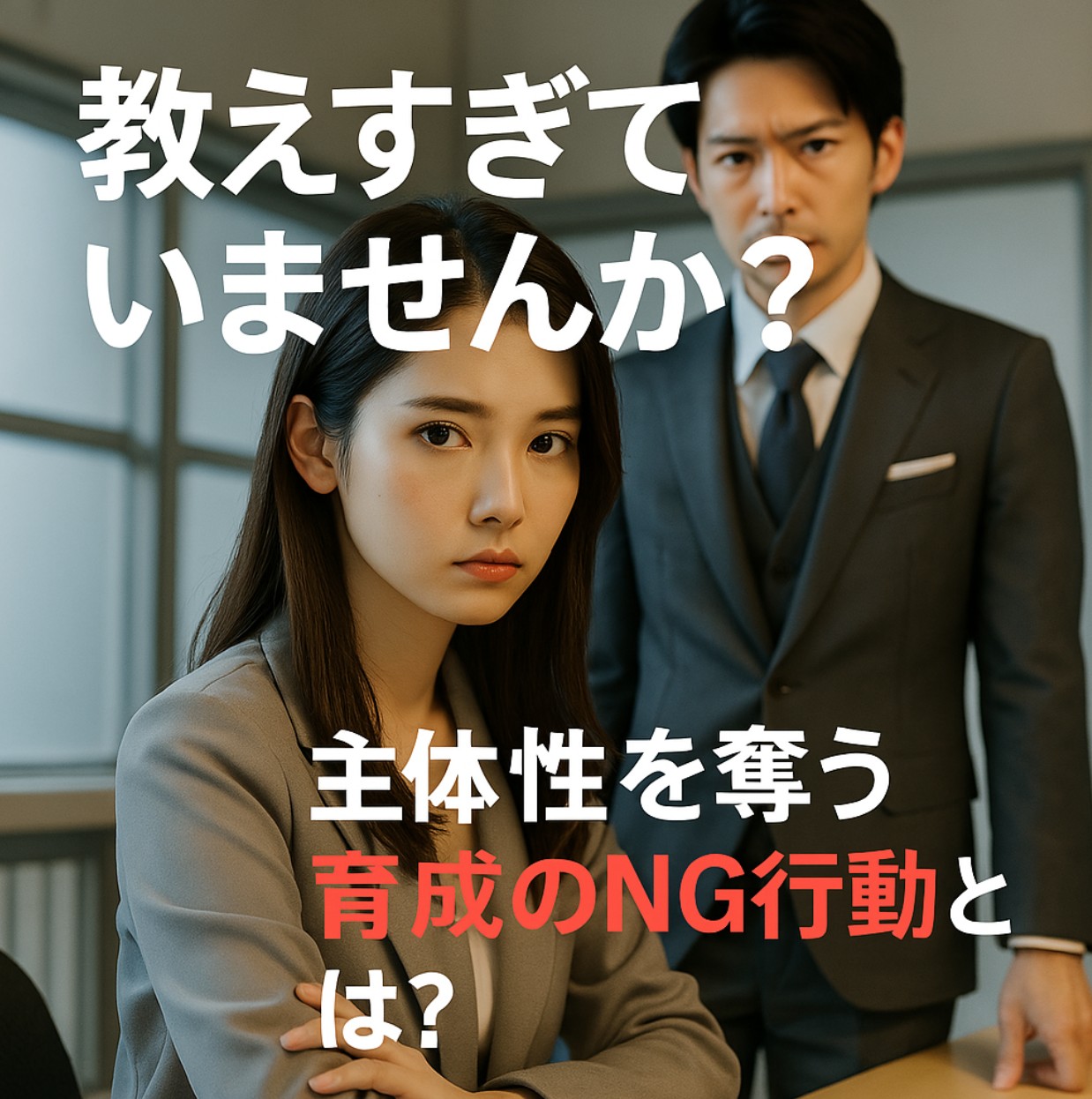この記事は、2025年4月1日の日経新聞を基に作成しました。
新人の成長に“ブレーキ”をかけているのは、あなたかもしれません
若手の成長を支援したい──そう願って丁寧に教えていませんか?
実はその「教えすぎ」が、主体性を奪い、成長の芽を摘んでいる可能性があります。
2025年4月1日の日経新聞では、ヤクルト・ファンケル・鹿島建設など、さまざまな企業が新入社員の定着と成長支援のために、“教え方”“任せ方”を見直し始めていると報じられました。
なぜ「丁寧な指導」が若手を止めるのか?
たとえば、上司が正解を教えすぎると──
- 若手が「自分で考える」前に答えが出てしまう
- 試行錯誤のプロセスがなくなり、“指示待ち”になる
- 挑戦しない状態が続くことで、「自信のなさ」が定着してしまう
このように、**「教えすぎ → 指示待ち化 → 成長停滞」**という悪循環が生まれます。
教えすぎかどうか、チェックしてみましょう
以下のような傾向があれば要注意です:
ミスを防ぐために、手順をすべて先に説明している
フィードバックのたびに「もっとこうした方がいい」と言ってしまう
成果よりも“やり方”の指導に時間を割いている
一方で、“任せる力”とは単なる放任ではありません。
若手に「考える余白」と「挑戦の余地」を与える工夫が求められるのです。
「任せる=育てる」とはどう違う?
教えることは“過去の答え”を伝えること。
任せることは“未来の可能性”を信じること。
ヤクルトは、上司に向けて「仕事の任せ方」「育成計画の立て方」などを研修に組み込んでいます。
鹿島建設は13年にわたる長期育成プログラムを設け、「経験にばらつきが出ない仕組み」を重視。
これらの事例が示すのは、「育成は属人的であってはいけない」ということです。
Bay3の支援事例|“教えすぎない”育成の設計とは
Bay3では、次のような支援を通じて“指導のしすぎ”による主体性喪失を防ぐ仕組みを整えています。
若手が“自分で考える”思考を育てるキャリア思考研修
管理職向け「任せる技術」ワークショップ
育成のバラつきを防ぐ“仕組み化”の支援
たとえばある企業では、フィードバックの内容を「問いかけ」に置き換えるだけで、
若手から自発的な提案が倍増し、面談が“教える場”から“成長の対話”へと変化しました。
関連リンク(内部リンク)
まとめ|「教えない」ことが最大の成長支援になる
- 若手の主体性を奪うのは、本人ではなく“教え方”の可能性もある
- 成長には「問いかけ」「任せる」「見守る」の3つが重要
- 教えるだけでなく、「引き出す」ことを育成に取り入れよう
無料相談|育成に“余白”を設けたい企業さまへ
Bay3では、「任せる技術」をベースとした若手育成の仕組みを支援しています。
若手が自走し、上司が信じて任せられる組織を一緒につくりませんか?
▶ 無料相談はこちら