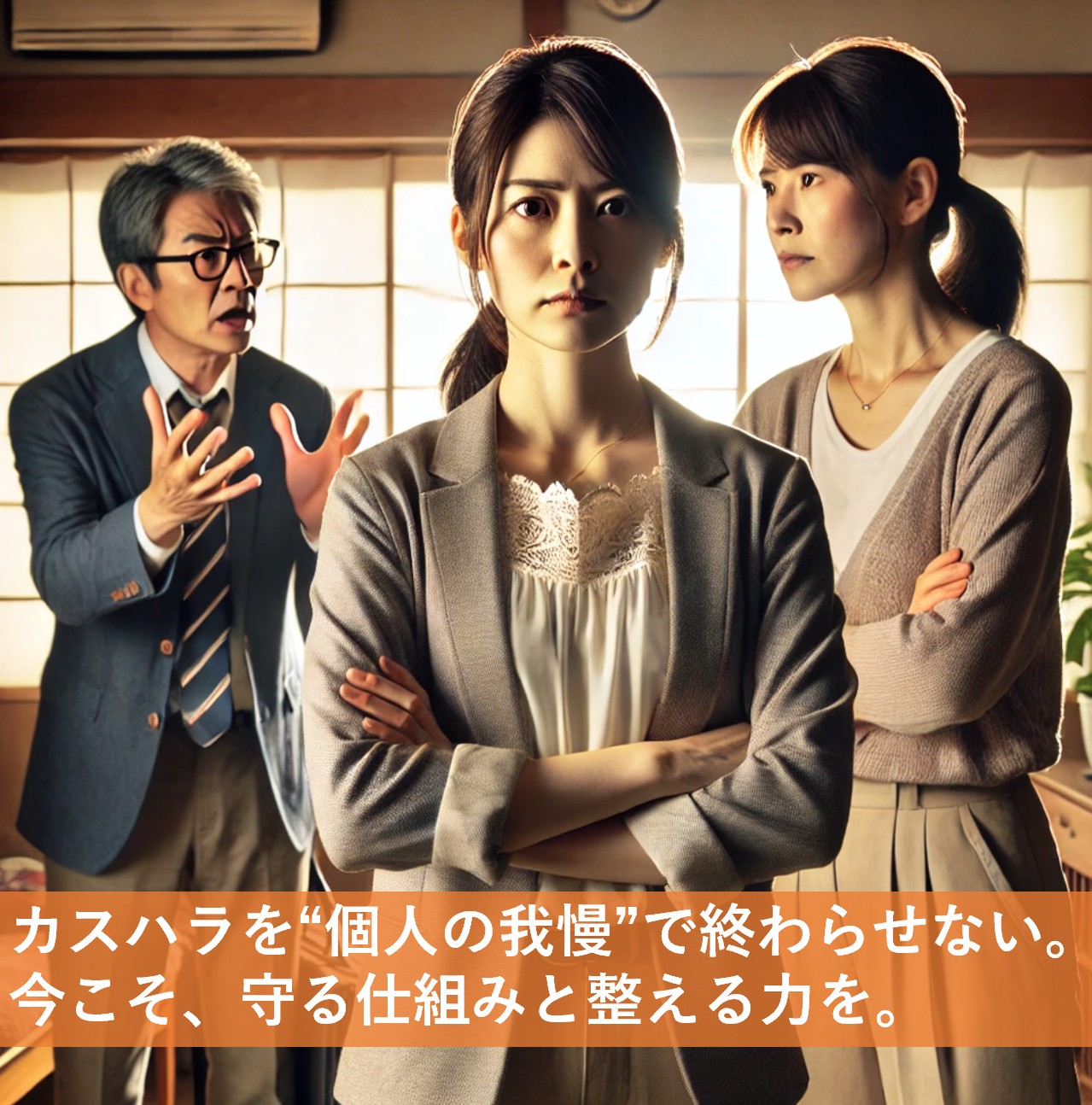この記事は、2025年4月21日の日経新聞の記事を基に作成しました。
2025年4月、日本介護支援専門員協会が実施した調査により、
ケアマネジャーの37.7%が過去1年間にカスタマーハラスメント(カスハラ)を受けたことが明らかになりました。
これは、厚労省が2023年度に公表した全業種平均(10.8%)と比較すると、約3.5倍の高水準です。
つまり、介護の現場はハラスメントリスクが非常に高い職種のひとつであるといえるでしょう。
被害内容と加害者の傾向
調査は2024年11月~12月にかけて行われ、1,293名から有効回答が集まりました。
そのうち約4割が、何らかのカスハラを経験したと回答しています。
具体的な被害内容としては、以下のとおりです:
- 言葉の暴力・精神的な攻撃:32.0%
- 過度または不当な要求:25.2%
- 根拠のないクレームや暴言:多数報告あり
また、加害者の傾向としては、利用者の主介護者や家族(46.0%)が最も多く、
次いで利用者本人(28.3%)が挙げられました。
この結果からも、家族との関係性がカスハラの中心であることが読み取れます。
業界への影響とその背景
カスハラを受けたケアマネジャーの中には、「辞めたい」と感じる人も少なくありません。
実際に、精神的に限界を感じたという声も報告されています。
その背景として、ケアマネジャーの業務が主に「利用者の自宅」という私的な空間で行われる点が挙げられます。
このような環境では、利用者や家族が「自分の方が立場が上」と錯覚しやすい構造が生まれがちです。
その結果、現場職員が一人で対応を抱え込むリスクが高まります。
協会の見解と要望
このような状況に対し、日本介護支援専門員協会の常任理事は次のようにコメントしています:
「カスハラは表に出にくく、現場で我慢されがちです。
したがって、行政には相談窓口の整備や支援制度の導入を求めたい。」
つまり、職員個人の努力や忍耐に任せるのではなく、制度的なサポートが必要不可欠なのです。
▶ Bay3が提案する「仕組みで守る」現場改善支援
このような現場の課題に対し、Bay3では以下のような実行的支援を提供しています。
1|評価制度の設計・見直し支援
- カスハラ対応や報告行動を「行動評価」に組み込み、行動基準として明文化
- 評価制度を通じて、対応が“評価される行動”であることを組織全体に浸透させます
2|1on1制度・管理職研修の設計支援
- 部下が悩みを話しやすい面談の仕組みを整備
- また、管理職がカスハラの兆候に気づき、的確に対処できるスキル研修も提供
▶ ご相談は無料です
「制度を導入したいが、どこから手をつけていいか分からない」
といったご相談も歓迎しています。
まずはお気軽に、Bay3までご連絡ください。
まとめと学びポイント(他法人への示唆)
“個人の我慢”に頼らない現場づくりが、これからの介護組織に必要です。
カスハラは特別な職場だけの問題ではなく、
「声をあげにくい」「相談しても動かない」という空気の中で、じわじわと現場を蝕みます。
だからこそ今、仕組みと対話で支える工夫が求められています。
- 制度設計は、組織を“守る器”になる
→ 評価制度や面談の仕組みに「相談・対応・行動」を組み込むだけでも、大きな安心になります - 1on1や感謝の可視化は、どの業界でも再現可能な“関係性の基盤”
→ 言葉にならない不安や感情を、日常の中で拾い上げる土壌をつくることができます
本記事では、介護現場におけるカスハラ問題と、それに向き合う組織的アプローチをご紹介しました。
もし貴社でも、「人が辞めない仕組み」や「仕組みで守る現場」について感じることがあれば、ぜひご意見をお聞かせください。
匿名でのご相談・ご質問も歓迎しております。