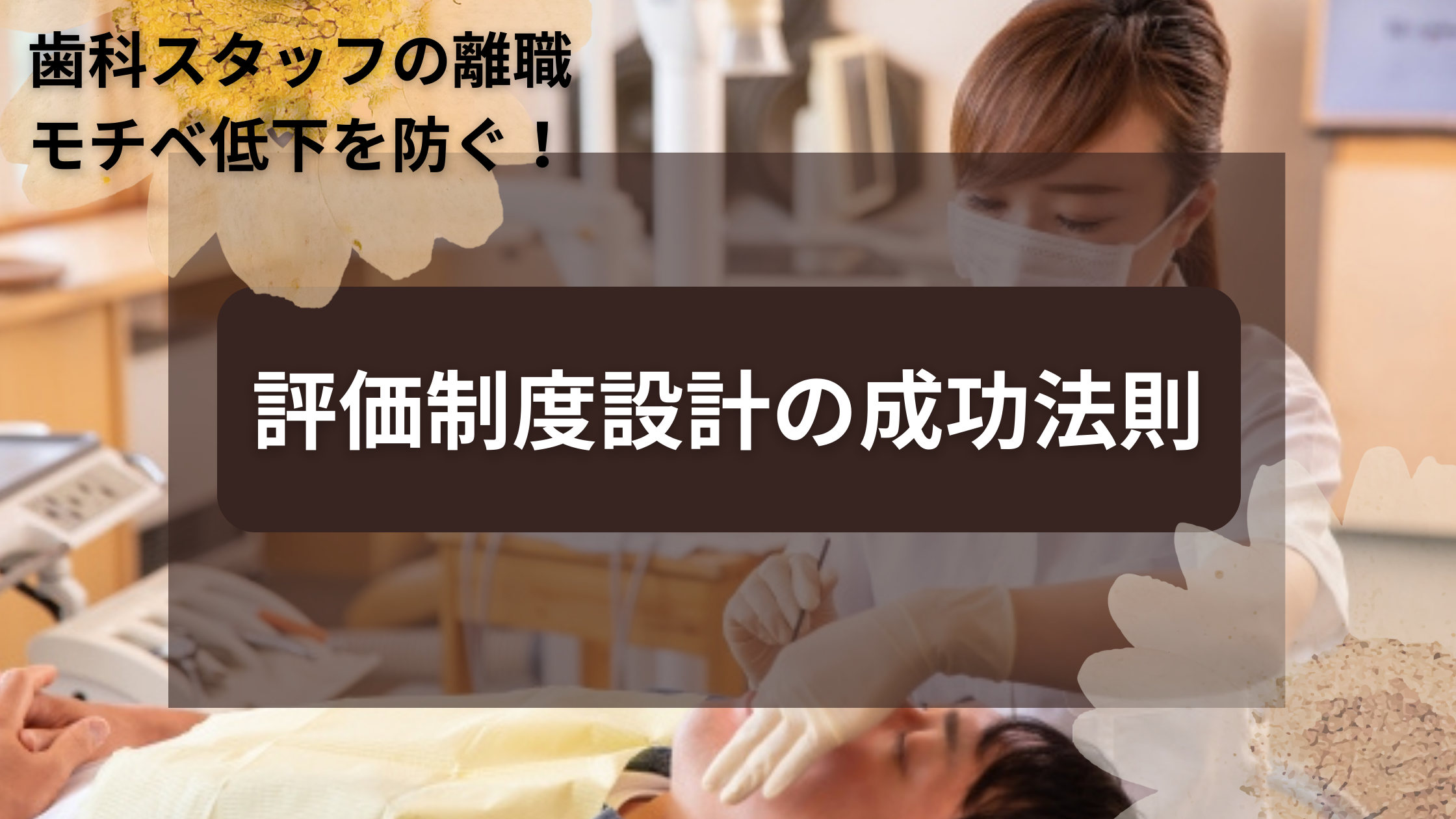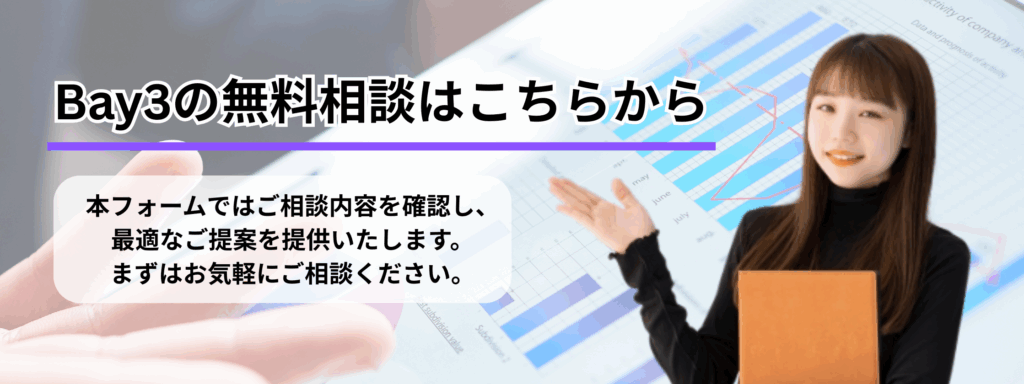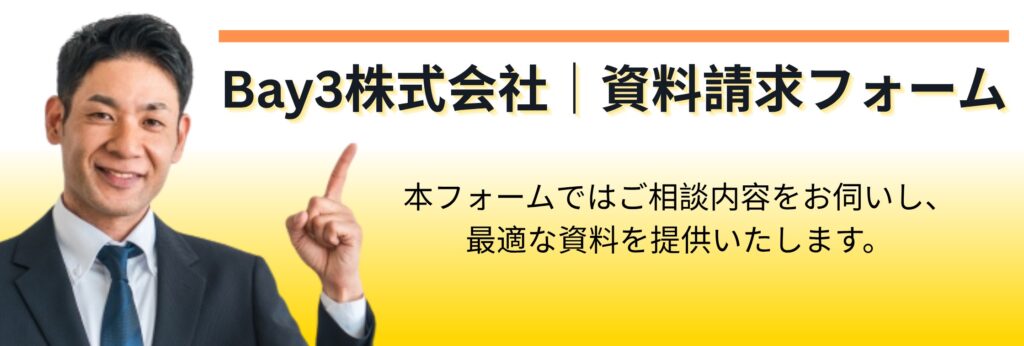「うちのスタッフ、最近元気がない…」
「せっかく育った人材がすぐ辞めてしまう…」
歯科医院の院長からよく聞くこの悩み、原因は単なる給与額や休暇日数だけではありません。
実は、スタッフの“評価のされ方”と、その見える化の仕組みが離職やモチベ低下に大きく影響しています。
本記事では、
- なぜ歯科スタッフのやる気が下がるのか
- スタッフが納得する評価制度の作り方
- 導入後の運用ポイントと成功事例
を、現場のリアルな視点と具体的なステップで解説します。
評価制度は「作って終わり」ではなく「文化として根付かせる」ことが大切。
今日からでも一歩踏み出せるヒントを、たっぷりご紹介します。
なぜ歯科スタッフの離職やモチベ低下が起きるのか
歯科医院の離職は「もっと給料が高いところに行きたい」という単純な理由だけじゃありません。
日々の働き方や評価のされ方がじわじわ効いて、気づけばモチベーションがゼロに…なんてことも。
ここでは、院長が意外と見落としがちな3つの落とし穴を解説します。

感覚的な評価が不満や不信感を招く理由
- 「○○さんは最近頑張ってる気がするから昇給」なんて、明確な基準がない評価はスタッフの不信感を招く
- 自分なりに努力していても、評価される人とされない人の差が不透明だと「どうせ頑張ってもムダ」と感じやすい
- 院長目線では“感覚”でも、スタッフにとっては「えこひいき」や「好き嫌い評価」に見えてしまう
スタッフは評価の一貫性や透明性に敏感。
「基準はあるけど口頭で説明してない」「なんとなく点数をつけている」状態は、離職予備軍を生みやすいんです。
給与・昇給の基準が不明確なことによる影響
- 「来年も昇給するの?」「ボーナスは何を基準に決まるの?」が曖昧だと、将来設計が立てられない
- 評価基準と給与反映のルールがリンクしていないと、頑張っても収入が増えず不満が蓄積
- 若手ほど「キャリアの見通し」が欲しいため、不透明な給与制度は転職動機になりやすい
給与のルールは“院長の頭の中だけ”ではなく、紙やデータで共有することが大事。
「この基準を満たせば、ここまで昇給」という見える化が安心感を生みます。
院内コミュニケーション不足と評価制度の関係
- 評価面談やフィードバックが年1回だけだと、スタッフは「自分の評価を知らないまま」働くことに
- 日常の業務での小さな改善や成果がスルーされると、やる気は自然に下がる
- コミュニケーション不足は評価基準の理解不足にもつながり、「なぜこの点数?」と疑問が増える
院内の会話が少ない職場は、評価制度があっても機能しません。
日々の声かけや月次ミーティングで評価ポイントを共有するだけで、制度の納得感はぐっと高まります。
スタッフが納得する評価制度の運用ポイント
せっかく作った評価制度も、運用でつまずくとすぐ形骸化してしまいます。
ポイントは 「透明性」「継続性」「双方向性」 の3つ。
ここでは現場でうまく回すためのコツをご紹介します。
評価制度の具体的な設計から導入、運用までの7つのステップは、こちらの記事でも詳しく解説しています。
院長とスタッフ双方が理解できる評価基準の共有
- 制度を導入したら、最初に全スタッフ向け説明会を行う
- 専門用語やあいまいな表現は避け、具体例を交えて説明
- 「なぜこの基準なのか」を話すことで納得度が上がる
評価基準は院長の頭の中だけで完結させないこと。
「この評価はこういう行動を目指している」という背景まで共有すると、スタッフの行動も変わります。
定期面談と評価フィードバックの習慣化
- 面談は最低でも年2回、理想は四半期ごとに実施
- 面談では一方的に評価を伝えるだけでなく、本人の意見も聞く
- 日常業務での小さな成果や努力も必ずフィードバック
評価は「通知」ではなく「対話」。
本人が成長を実感できるフィードバックが、やる気を長持ちさせます。
院内ミーティングでの評価制度浸透法
- 月1回程度の院内ミーティングで評価項目や良い事例を共有
- 「この行動は高評価につながる」という具体例をスタッフ間で出し合う
- 評価制度を“日常会話に登場する存在”にする
制度は使ってナンボ。
ミーティングで定期的に話題にすれば、「評価制度ってあったよね?」という存在感薄れを防げます。
評価制度を改善し続けるためのアンケート活用
- 年1回、全スタッフに匿名アンケートを実施
- 「評価基準のわかりやすさ」「面談の満足度」など具体的に聞く
- 結果を院長だけで抱え込まず、改善案と一緒に共有
評価制度は一度作って終わりではありません。
スタッフの声を取り入れて少しずつアップデートしていくことで、制度は生きたツールになります。
成功事例|評価制度で変わった歯科医院の実例
机上の理論よりも、リアルな現場の変化のほうが説得力があります。
ここでは、評価制度によって劇的に変わった歯科医院のエピソードをご紹介します。
スタッフ定着率80%を達成した院長の実践法については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
スタッフ定着率90%超を達成したA歯科医院の取り組み
- 評価基準を職種別に細分化し、努力が正しく反映される仕組みを構築
- 四半期ごとの面談で「良い点3つ+改善点1つ」のフィードバックを徹底
- 制度導入から2年で定着率が65%→92%にアップ
A医院では「評価制度=不満解消ツール」ではなく「成長支援ツール」と位置づけたことで、離職率が激減しました。
患者満足度が向上したB医院の評価基準改善例
- 評価項目に「患者説明のわかりやすさ」と「笑顔率」を追加
- 患者アンケートの結果を評価の一部に組み込み、接遇意識を強化
- 半年後、口コミ評価が平均3.8→4.4に上昇
B医院は「技術力だけの評価」から脱却。
患者視点を基準に加えることで、医院全体の雰囲気が明るくなりました。
短期間で運用が定着した評価制度導入のポイント
- 初期段階からスタッフ代表を制度設計メンバーに入れる
- 評価表はシンプルにし、初回面談時に全員で記入練習
- 導入3か月後に全員で改善会議を行い、ルールを微調整
短期間で浸透した理由は「一方的に与えられた制度」ではなく、「みんなで作った制度」にしたこと。
参加感があると、運用もスムーズです。
まとめ|評価制度は「作る」より「育てる」もの

評価制度は一度作ったらゴール…ではなく、スタート地点です。
実際に運用して、スタッフの声や現場の変化を反映しながら少しずつ成長させていくことで、初めて本物の制度になります。
ここでは導入前に知っておきたい成功法則と、制度を医院文化にするコツをご紹介します。
導入前に押さえておきたい成功法則
- 目的を明確にする(離職防止、モチベアップ、患者満足度向上など)
- 職種別の評価基準を用意し、誰でも理解できる形にする
- 評価と給与・昇給ルールをセットで設計する
- 初期段階からスタッフを巻き込むことで浸透スピードを上げる
制度は「やらされ感」で始めると失敗します。
みんなでゴールを共有してから走り出すのが成功のカギです。
評価制度の「仕組み化」を進める上で、あらかじめ知っておきたいデメリットについては、こちらの記事もご一読ください。
評価制度を医院文化として根付かせるために
- 定期的な面談やミーティングで評価基準を自然に会話に登場させる
- 年1回はアンケートや改善会議で制度を見直す
- 新人スタッフにも入社時に制度を説明し、当たり前のルールとして認識させる
評価制度が文化になると、「制度があるからやる」ではなく「医院の価値観としてやる」に変わります。
そうなると、制度は形骸化せず、医院の成長エンジンになってくれます。
無料相談・資料請求のご案内
「うちの医院にも評価制度を導入したいけど、どこから手をつければいいの?」
「制度はあるけど、スタッフが全然納得してくれない…」
そんなお悩みをお持ちの院長先生は、ぜひ一度ご相談ください。
Bay3株式会社では、
- 現場目線での評価制度設計
- 導入後の運用サポート
- 職種別の評価項目テンプレート提供
まで、ハンズオンでお手伝いします。
今なら無料で導入ステップ解説資料もプレゼント中!
まずはお気軽にお問い合わせください。