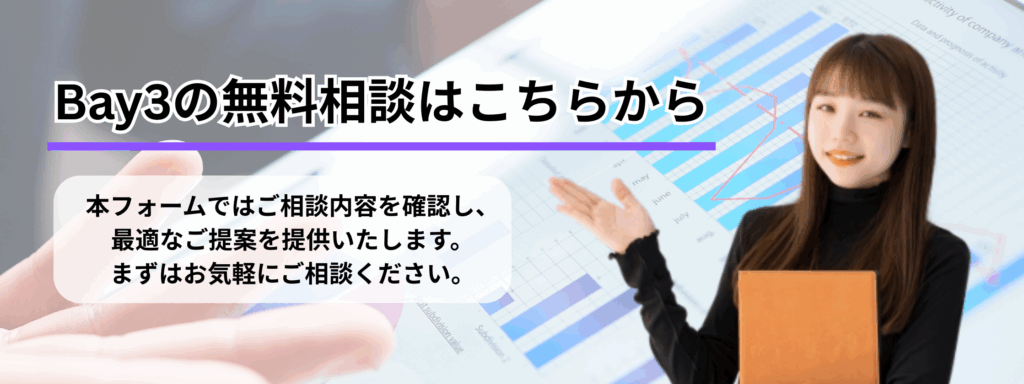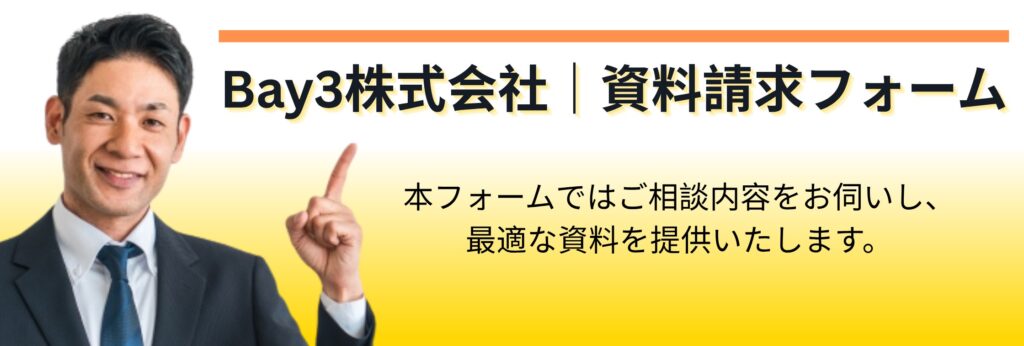開業から3年ほど経ち、「そろそろ軌道に乗ったかな」と思った矢先に――
「売上は安定しているのに、利益が伸びない」「スタッフが辞める」「院長が何でも抱え込みがち」
そんな“開業3年目の壁”にぶつかる歯科医院は少なくありません。
診療スキルは高くても、経営やマネジメントの壁はまったく別の課題。
そこで注目されているのが、「歯科コンサル」=経営の伴走パートナーという存在です。
本記事では、「歯科コンサルとは何をしてくれるのか?」「頼むと実際に何が変わるのか?」を、
Bay3株式会社が現場支援で培ってきたリアルな視点から徹底解説します。
歯科コンサルとは?医院経営の“伴走パートナー”

そもそも「歯科コンサルティング」の意味とは
結論から言えば、歯科コンサルとは「医院経営を改善・成長させる専門家」のこと。
単なるアドバイス屋ではなく、経営・組織・数字・人材のあらゆる課題を“横断的に”支援する存在です。
多くの院長が「経営も現場もすべて自分がやらなきゃ」と感じていますが、
医院運営はもはや“一人プレー”で成立しない時代。
集患、人材教育、評価制度、業務効率化――課題が複雑に絡み合う中で、
コンサルは「整理し、優先順位をつけ、実行まで導く」役割を担います。
つまり、診療のプロである院長を、経営のプロが支える構図。
それが歯科コンサルティングの本質です。
コンサルが関わる主な領域(集患・人材・財務・組織)
「コンサルって何をしてくれるの?」とよく聞かれますが、
実際の支援領域は想像以上に広く、医院の“総合経営支援”に近い形です。
代表的なサポート領域は以下の通りです👇
- 集患・マーケティング支援:広告戦略、口コミ改善、ホームページ導線の最適化
- 人材採用・教育:採用フロー設計、面接官トレーニング、スタッフ研修
- 財務・収益改善:原価率分析、損益構造の最適化、KPI設計
- 組織・マネジメント強化:評価制度構築、会議設計、チームマネジメント
とくに近年は、「人材定着」「評価制度」「マネジメント改善」といった
“内部体制の仕組み化”を求める医院が急増。
単に「集患を増やす」ではなく、医院全体を“仕組み”で強くする方向にシフトしています。
アドバイス型と実行支援型の違い
歯科コンサルには大きく2つのタイプがあります。
1️⃣ アドバイス型(提案・助言中心)
→ 現状分析や提案資料を提供するスタイル。比較的安価だが、実行は院長任せになりがち。
2️⃣ 実行支援型(伴走・実装重視)
→ コンサルタントが現場に入り、ミーティング設計・評価運用・スタッフ教育まで伴走するスタイル。
課題を“仕組み”で解決するのが特徴です。
短期的なノウハウ提供よりも、“現場を動かす力”と“実行までの支援”が求められている今、
多くの医院が実行支援型を選ぶ傾向にあります。
現場で結果を出すのは「伴走型コンサル」
アドバイスだけでは現場は変わりません。
大切なのは、「やり方を教えて終わり」ではなく、“一緒に仕組みを作り、定着させる”こと。
Bay3が提唱するのは、この「伴走型コンサル」。
定量+定性の両面で“見える化”しながら、現場の定着・育成・評価まで支援します。
たとえば「評価制度を作って終わり」ではなく、
「実際に面談で使えるようになるまで」伴走する。
その姿勢が、成果を出す医院とそうでない医院を分けるのです。
開業3年目で立ちはだかる“医院経営の壁”とは
売上は安定したのに「なぜか利益が増えない」
開業から数年、患者数も安定。けれども「思ったほど手元にお金が残らない」――
これが多くの院長が最初に感じる“見えない壁”です。
理由はシンプル。
- 人件費や材料費がじわじわ上昇している
- リピート率や単価アップの施策が止まっている
- 診療スピードばかりに目が行き、経営数字を追えていない
つまり、“売上が増えても利益構造が改善されていない”状態。
歯科コンサルは、この「見えない赤字構造」を可視化し、利益率を改善する支援を行います。
スタッフとの関係がぎくしゃくし始める理由
開業当初はチーム一体だったのに、3年を過ぎると「なんとなく雰囲気が悪い」「離職が増えた」――。
実はこれ、組織づくりを仕組み化していない医院でよく起こる現象です。
評価制度やミーティングの型がないと、
「誰がどのように頑張っているのか」が伝わらず、モチベーションが低下します。
また、院長の忙しさからスタッフとの対話が減ると、誤解や不満が生まれやすくなるのです。
コンサルが介入すると、“評価とコミュニケーションを見える化”する仕組みを導入し、
チーム全体の空気が整います。
院長一人では限界を感じる「経営と現場の両立」問題
「患者対応、経営管理、採用、教育…全部自分でやっている」
そんな院長ほど、疲弊と停滞が同時にやってきます。
開業3年目は、“個人の限界”から“組織で動かす体制”への転換期。
この時期にコンサルが入ることで、
- 業務の分担
- マネジメント会議の導入
- KPI管理シートの整備
といった「経営の見える化と分業化」が進みます。
つまり、院長が“診療に専念できる環境”を取り戻すための支援こそ、
歯科コンサルの大きな価値なのです。
歯科コンサルが支援できる7つの経営課題

歯科医院の経営課題は、ひとつを直せば解決する単純な問題ではありません。
多くの医院では、「集患が伸びない」「スタッフが定着しない」「数字の管理ができていない」といった
複数の要素が絡み合っています。
歯科コンサルは、それらの課題を分解・整理し、優先順位をつけて実行支援する存在です。
ここでは、歯科コンサルが現場で支援できる代表的な7つのテーマを紹介します。
① 集患・マーケティング戦略の立て直し
「患者数が減ってきた」「新患が伸び悩んでいる」と感じる医院では、
多くの場合、広告やHPではなく戦略全体の設計に課題があります。
コンサルが行う主な支援内容は以下の通りです。
- ターゲット層や地域特性の分析
- 新患・再来率・単価などのKPI設計
- Googleマップ・口コミサイトの導線改善
- SNSやWeb広告の見直し
特に最近は、「患者に選ばれる理由」を明確化した上で、
“通いたくなる医院づくり”を支援するケースが増えています。
② 人材採用・教育体制の強化
採用に失敗する医院の多くは、求人内容よりも医院の魅力が伝わっていないことが原因です。
歯科コンサルは以下のような形で採用・教育を強化します。
- 採用コンセプトの言語化(理念・強み・働き方)
- 求人票・面接スクリプトの見直し
- 入社後の教育プログラム・研修カリキュラム設計
- スタッフ面談の設計と運用サポート
採用から育成までの流れを“仕組み化”することで、
「採ってもすぐ辞める」状態から脱却できます。
③ スタッフ定着と離職防止の仕組みづくり
「雰囲気が悪くなってきた」「人がすぐ辞める」――
こうした課題は、評価の不透明さやコミュニケーション不足が原因です。
歯科コンサルが行うサポートは次の通りです。
- 離職要因のヒアリング・分析
- 評価制度・面談制度の導入
- キャリアパス(成長の道筋)の明確化
- チーム別目標設定と達成支援
スタッフが「この医院で成長できる」と実感できる環境を整えることで、
離職率の低下とモチベーション向上を両立させます。
④ 経営数値・KPIの“見える化”
「今月の数字、なんとなく把握しているけど自信がない…」
そんな医院ほど、感覚経営になっている危険信号です。
コンサルは、経営指標を明確にし、数字で意思決定できる体制を作ります。
- 売上・原価・稼働率・キャンセル率などの可視化
- 月次KPIレポート・グラフ化・会議共有
- 数値に基づく改善アクションの設計
これにより、曖昧だった「なんとなく黒字」から脱し、
利益構造を管理できる医院経営へと進化します。
⑤ 評価制度・給与テーブルの整備
「頑張っているスタッフをどう評価すればいいのか分からない」
そんな悩みを持つ医院は非常に多いです。
歯科コンサルは、公平性と納得感を両立する仕組みを設計します。
- 職種ごとの行動・成果基準の明確化
- 定量(成果)×定性(行動)のバランス評価
- 評価結果を給与・昇給に連動させる仕組み
- 院長・リーダー向けの評価面談トレーニング
評価が見える化されると、スタッフの目標意識と一体感が劇的に高まります。
評価制度の設計と運用の実務は、こちらの記事が参考になります。
⑥ 会議設計・マネジメント改善
「毎週会議をしているのに、結局何も変わらない」
そんな医院に共通しているのは、会議の目的が曖昧なことです。
歯科コンサルは次のような流れで会議の生産性を高めます。
- 会議体の設計(目的・頻度・参加メンバー)
- アジェンダテンプレートの導入
- 決定事項・アクション・振り返りの定着支援
- 管理職・マネージャー向けマネジメント研修
報告会から“動く会議”へ変わることで、医院全体の推進力が上がります。
⑦ 院長の負担を減らす業務効率化
最後に多くの院長が求めているのが、「自分の時間を取り戻す仕組み化」です。
歯科コンサルは次のような形で業務効率化を支援します。
- 業務フローの棚卸しと優先順位づけ
- 事務・勤怠・報告業務の自動化(スプレッドシート・AIツール活用)
- 院長とスタッフ間の情報共有ルール設計
- 「やめる」「減らす」「自動化する」仕組みの構築
これにより、院長が診療と経営の両立に悩む状態から解放され、
「自分がいなくても医院が回る」仕組みが整います。
経営、採用、教育、評価、効率化――
これらはバラバラに存在するのではなく、すべてが“つながる課題”です。
歯科コンサルはその全体像を俯瞰し、医院の“経営の仕組み”を再設計することで、
院長が本来の仕事に集中できる環境を実現します。
評価・予約・研修・会議までの仕組み化については、こちらの記事で全体像を押さえられます。
実際に“何が変わる”?歯科コンサル導入のビフォーアフター
「歯科コンサルを入れると、本当に何か変わるの?」
そう感じる院長は多いはずです。
ここでは、コンサル導入前後でどんな変化が起こるのかを、実際の医院のリアルな状況に沿って紹介します。
Before:属人的な経営で現場が混乱していた医院
導入前の多くの医院は、次のような状態にあります。
- すべての判断が院長依存で、スタッフが指示待ち
- 評価や給与の基準が曖昧で、不満が溜まりやすい
- 会議や報告が“形だけ”になり、改善が進まない
- 売上は安定しているが、利益やチームの活気が停滞
こうした状況では、経営が“人に依存する”属人的な体制になっており、
院長の負担が増えるほど組織全体が回らなくなります。
After:評価と給与が連動し、チームが自走する組織へ
コンサル導入後は、次のような変化が見られます。
- 各スタッフに明確な目標と役割が生まれ、仕事への主体性が向上
- 評価制度と給与テーブルが整い、成果が公平に反映される
- 定例ミーティングが“報告の場”から“改善の場”へ変化
- 院長の意思決定がスムーズになり、経営と現場のバランスが取れる
特に大きな変化は、「自分で考えて動くスタッフが増える」こと。
チーム全体が“院長に頼らず自走する組織”へと進化します。
成功事例|3年目医院で離職率を半減させた改善プロセス
ある開業3年目の医院では、年間離職率が25%を超え、常に採用に追われていました。
そこで歯科コンサルが入ったことで、次のようなステップで改善を進めました。
① 現状分析と課題整理
・スタッフ面談とアンケートで不満要因を可視化
・「評価の不透明さ」「感謝の伝達不足」が課題と判明
② 評価制度・給与基準の整備
・行動基準と成果基準を設定
・頑張りが数値と報酬に連動する仕組みを導入
③ チームミーティング・1on1面談の導入
・院長とスタッフの対話を増やし、信頼関係を再構築
結果、わずか半年で離職率が半減し、スタッフ満足度が大幅に向上。
「辞める人がいなくなった」だけでなく、紹介で入社するスタッフが増えるまでに変化しました。
ポイントは「課題を一緒に見つけ、仕組みで解決する」
歯科コンサルの真価は、単なるノウハウ提供ではなく、
“院長と共に課題を見つけ、現場で動く仕組みをつくる”こと。
多くの失敗は「提案で終わる」ケースにあります。
成功する医院は、コンサルと院長が二人三脚で改善を進め、
実行の仕組みを定着させています。
初めてでも安心!歯科コンサル導入までの流れ

「相談したいけど、どう進むのか分からない」
そんな方のために、初回相談から支援開始までの流れを3ステップで紹介します。
実際の医院で行っている進め方をイメージしてみてください。
ステップ①:無料相談・課題整理シートの実施
まずは現状を整理するところからスタートします。
コンサルタントが医院の状況をヒアリングし、課題整理シートを使って、
「何が課題で、どこから手をつけるべきか」を明確化します。
この段階では、契約や費用の話はありません。
“経営の健康診断”のような位置づけで、客観的な現状分析を行うステップです。
ステップ②:課題ヒアリングと支援プラン設計
次に、整理した課題をもとに、具体的な支援内容を設計します。
- 経営・人材・集患・組織運営などの優先順位を決定
- 必要に応じて、現場スタッフへのヒアリングも実施
- 改善テーマごとに、3〜6か月の伴走プランを設計
この時点で「どんな進め方をするのか」「どんな成果を目指すのか」を明確にするため、
導入後のミスマッチが起こりにくくなります。
ステップ③:伴走支援の開始(週次・月次ミーティング)
契約後は、いよいよ本格的な伴走支援フェーズです。
支援は医院ごとにカスタマイズされますが、一般的には以下の形で進行します。
- 週次 or 月次ミーティングで進捗確認
- KPIレポートによる成果の“見える化”
- スタッフ研修・会議設計・評価制度運用のサポート
- 経営数値・課題・成功事例を共有しながらPDCAを実行
この段階では、「変化が見える」実感を持てる医院が多く、
スタッフの意識やチームの雰囲気が変わり始めます。
現場の“変化が見える”運用フォローが重要
多くの医院が途中でつまずくのは、「作った仕組みが定着しない」こと。
Bay3では、定例ミーティングやSlack等を活用し、現場の変化を追跡しながら改善を継続します。
“導入して終わり”ではなく、定着するまで伴走する。
それが、現場主義の歯科コンサルが選ばれる最大の理由です。
「うちの医院も、そろそろ仕組みを整えたい」そう感じたら。
経営の課題は、“気づいた瞬間”がチャンスです。
Bay3では、歯科医院向けに「無料課題整理相談」を実施しています。
- 売上・離職率・評価制度などの課題を“見える化”
- 院長が抱えている悩みを、経営・人材・仕組みの3軸で整理
- 実行まで伴走できるコンサルタントが丁寧にサポート
「どこから手をつければいいか分からない」状態でも大丈夫です。
あなたの医院に合った改善ステップを、一緒に整理することから始めましょう。
歯科コンサルに依頼するメリットとデメリット

歯科コンサルを導入するかどうかを検討する際に、
気になるのが「本当に効果があるのか?」「どんなデメリットがあるのか?」という点です。
ここでは、実際の現場で得られる5つのメリットと、注意しておきたい3つの落とし穴を整理して紹介します。
メリット|医院経営に歯科コンサルを導入する5つの効果
歯科コンサルの最大の価値は、経営の見えない課題を“仕組み”で整えることです。
経験とデータに基づいたアプローチによって、医院の安定経営とチーム力向上を同時に実現できます。
① 経営課題を客観的に分析してもらえる
自分の医院の課題は、近すぎて見えないことが多いものです。
コンサルは第三者の視点から、数値・人・仕組みを総合的に分析し、
「どこにボトルネックがあるか」「何を優先すべきか」を整理してくれます。
この客観的な診断により、勘や感覚ではなくデータに基づいた経営判断が可能になります。
② 集患・人材育成・評価制度などを体系的に整えられる
院長一人では手が回らない領域を、体系的に仕組み化できるのがコンサルの強みです。
- 集患マーケティングの設計(HP・口コミ・SNS)
- 採用と教育の連動(入社後フォロー・研修計画)
- 評価制度と給与テーブルの整備
単発的な改善ではなく、医院運営全体を一貫した仕組みとして整えることで、
持続的な成長サイクルを作ることができます。
③ 院長が診療に専念しやすくなる
コンサルが経営やマネジメントの仕組みを支えることで、
院長が日々の“経営判断”から解放され、診療に集中できるようになります。
「人の問題」「数字の問題」「組織の問題」をすべて抱え込む状態から脱却し、
“経営の見える化”によって意思決定のストレスを軽減できます。
④ スタッフのモチベーションと定着率が向上する
評価制度やキャリアパスを整えることで、
スタッフが「自分の頑張りが正しく評価される」と感じられるようになります。
さらに、会議や1on1面談の仕組みを導入すれば、
コミュニケーションの質が上がり、チームの一体感も高まります。
結果として、離職率の低下・採用コスト削減・チーム力の向上という好循環が生まれます。
⑤ 成果を「数値」で見える化できる
コンサル導入後は、売上・利益・稼働率・離職率といった指標を定期的にモニタリングします。
これにより、医院の変化が「なんとなく」ではなく“数値で明確に”見えるようになります。
数値を追う文化が根づくことで、チーム全体が成果に意識を向け、
自然と改善が続く“自走する組織”へと変化します。
デメリット|注意すべき3つの落とし穴
もちろん、歯科コンサルにも注意点はあります。
導入する際は、次の3つのポイントを理解しておくことが大切です。
① コンサル内容が現場に落とし込めないケースもある
アドバイス型のコンサルに多いのが「提案して終わり」というケースです。
現場への落とし込みが弱いと、結局“机上の空論”になってしまいます。
コンサルを選ぶ際は、現場での実行支援やフォローがあるかどうかを必ず確認しましょう。
② 成果が出るまで時間がかかる場合がある
経営改善は“即効性”のあるものではありません。
特に、人や組織の課題は定着までに3〜6か月以上かかることもあります。
焦らずに、中長期的な視点で仕組みを定着させる姿勢が大切です。
③ 費用対効果を明確にしないと続けづらい
「結局いくらかかるの?」「どれだけ効果が出るの?」
この部分を曖昧にしたまま始めると、途中で不安が募ります。
契約前に、費用対効果の目安とKPI(成果指標)を共有しておくことで、
納得感のある投資として継続できるようになります。
歯科コンサルの費用相場と料金体系を解説

コンサル導入を検討するうえで、最も気になるのが「費用感」。
実は、契約形態や支援範囲によって料金は大きく変わります。
ここでは、一般的な料金体系と相場の目安を整理して解説します。
スポット支援と顧問契約の違い
歯科コンサルには、大きく分けて2つの契約形態があります。
| 契約タイプ | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| スポット支援 | 単発で特定の課題を解決(例:評価制度構築、採用戦略設計など) | 短期的・明確な課題に向いている |
| 顧問契約(伴走型) | 月単位で継続的に支援(例:経営会議・人材育成・数値改善) | 長期的に経営基盤を整えたい医院向け |
スポット型は一時的な改善、顧問型は“仕組みの定着”を目的としています。
一般的な費用相場(月額・単発・成果報酬型)
料金は内容や規模により幅がありますが、以下が一般的な目安です。
- スポット支援(単発):30万〜80万円程度
- 顧問契約(月額):10万〜40万円程度
- 成果報酬型(売上・利益改善率連動):成果の5〜10%前後
※あくまで相場であり、医院の課題規模や地域によって異なります。
医院規模別の目安費用(個人医院/中規模/法人)
| 医院規模 | 想定支援内容 | 相場感(月額換算) |
|---|---|---|
| 個人医院(スタッフ5名以下) | 集患・評価制度・数値改善 | 10〜20万円前後 |
| 中規模医院(10〜20名) | 組織マネジメント・教育体制整備 | 20〜30万円前後 |
| 法人/複数医院展開 | 人事制度・会議設計・拠点統括支援 | 30〜50万円以上 |
医院のフェーズに合わせて、無理のない範囲で段階的に導入するのがポイントです。
費用対効果を高めるポイント
コンサル費用を“コスト”ではなく“投資”に変えるためのポイントは以下の通りです。
- 明確なKPI(成果指標)を設定する
- 経営会議やミーティングで進捗を可視化する
- コンサルを“指示役”ではなく“共創パートナー”として活用する
補助金・助成金の活用でコストを抑える方法
「小規模事業者持続化補助金」や「人材開発支援助成金」などを活用すれば、
コンサル費用の一部を補填できる場合があります。
とくに、人材育成・組織改善・評価制度構築に関する支援は対象になることが多いため、
事前に確認しておくと良いでしょう。
「構築だけ」ではなく「運用サポート」まで含めるメリット
初期構築だけの契約は安く見えますが、実際は「仕組みが回らない」まま終わるケースも多いです。
運用フェーズまで含めたプランを選ぶことで、定着率・成果率が大きく向上します。
“作るだけで終わらない”――これが成功する医院の共通点です。
失敗しない歯科コンサルの選び方
「どのコンサルがいいのかわからない…」
そんな声をよく聞きます。
歯科コンサルには得意・不得意の領域があり、医院の状況に合っていない相手を選ぶと、せっかくの投資が無駄になってしまうこともあります。
ここでは、失敗しないコンサル選びの3つのポイントを紹介します。
① 現場支援まで対応できるか
最も重要なのは、「提案で終わらず、現場で一緒に動けるか」です。
- 机上の分析だけでなく、スタッフ面談・会議参加など“現場介入”があるか
- 改善施策を「実行→検証→改善」まで伴走してくれるか
- 成果指標(KPI)を一緒に追ってくれるか
「現場に強いコンサル」は、制度や戦略を“実際に機能させる”支援をします。
逆に、現場を知らないコンサルは理想論で終わり、定着しないことが多いです。
② 実績・支援企業の規模を確認する
コンサルを選ぶときは、どんな医院を支援してきたかを見ることが大切です。
- 自院と同じ規模(10〜50名程度)の支援実績があるか
- 導入後の成果(売上改善・離職率改善など)が公開されているか
- 担当者の経歴・得意分野が明確か
たとえば「大手法人ばかり支援しているコンサル」は、
中小医院には合わない場合があります。
自院のステージに近い医院で成果を出しているかを基準に選びましょう。
③ 医院のフェーズ(開業〜拡大)に合っているか
医院経営にも“フェーズ”があります。
開業期・安定期・拡大期では、求める支援がまったく異なります。
| フェーズ | 主な課題 | 向いているコンサル |
|---|---|---|
| 開業〜1年目 | 集患・採用・仕組みづくり | 立ち上げ型コンサル |
| 2〜5年目 | 定着・組織化・評価制度 | 実行支援型コンサル |
| 6年目以降 | 拡大・多院展開・幹部育成 | 戦略型コンサル |
「実行支援型コンサル」が3年目医院に最も合う理由
開業3年目の医院は、“人”と“仕組み”の両面が課題になる時期です。
評価制度・会議設計・マネジメントなど、目に見えない部分の整備が必要になります。
この段階で必要なのは、アドバイスだけではなく、
一緒に動きながら仕組みを定着させる「実行支援型コンサル」です。
Bay3のような実行支援型では、週次・月次で現場を伴走し、
「提案して終わり」ではなく“成果が出るまで支える”点が特徴です。
選定基準のチェックは、こちらの記事の要点も役立ちます。
まとめ|経営を立て直す第一歩は“課題の見える化”から
経営の悩みは、誰もが抱えています。
大切なのは、「どこに課題があるのか」を明確にすること。
すべては“見える化”から始まります。
院長一人で悩まない、経営の壁を乗り越える方法
開業3年目の壁を乗り越えた医院の多くは、一人で抱え込むのをやめた瞬間から変わり始めます。
- 経営の優先順位を整理する
- 数値・人・仕組みの課題を可視化する
- チームで課題を共有し、改善に動く
院長がすべてを背負うのではなく、
「伴走者」と一緒に仕組みを整えることで、医院経営は安定していきます。
Bay3の無料相談では、課題整理から伴走支援までサポート
Bay3株式会社では、歯科医院向けに「無料課題整理相談」を実施しています。
- 経営・人材・評価制度の現状を可視化する「課題整理シート」
- 医院のフェーズに合わせた「支援プランの提案」
- 実行フェーズでの週次/月次伴走支援によるフォロー
制度を作るだけでなく、“定着させるところまで支援”するのがBay3のスタンスです。
「うちの医院にも合うかな?」という段階でも大丈夫です。
まずは課題を整理するところから、一緒に始めてみませんか。