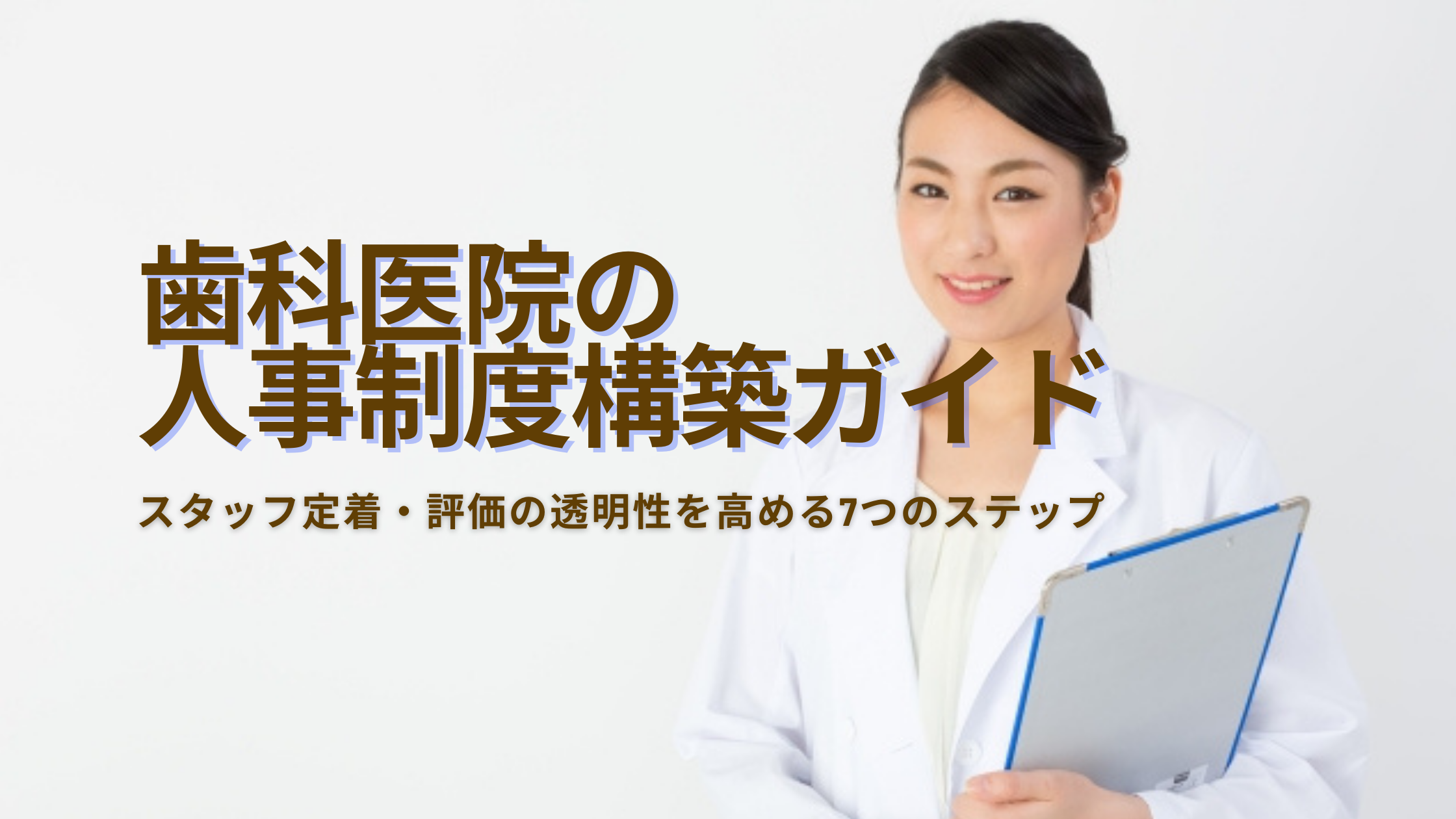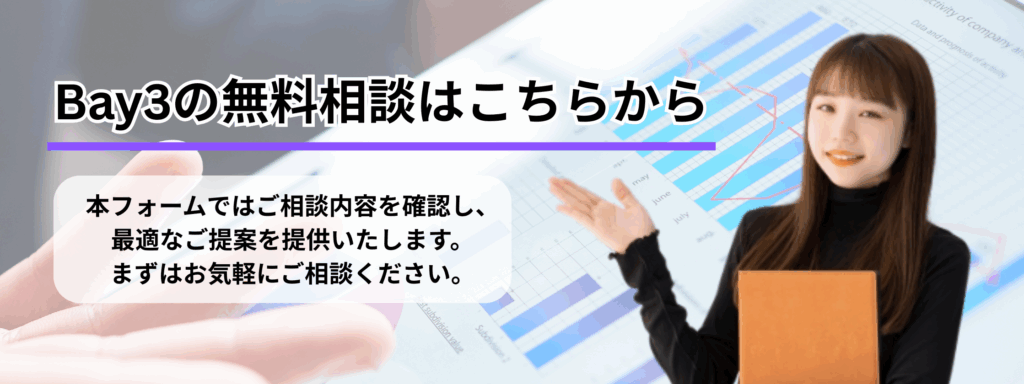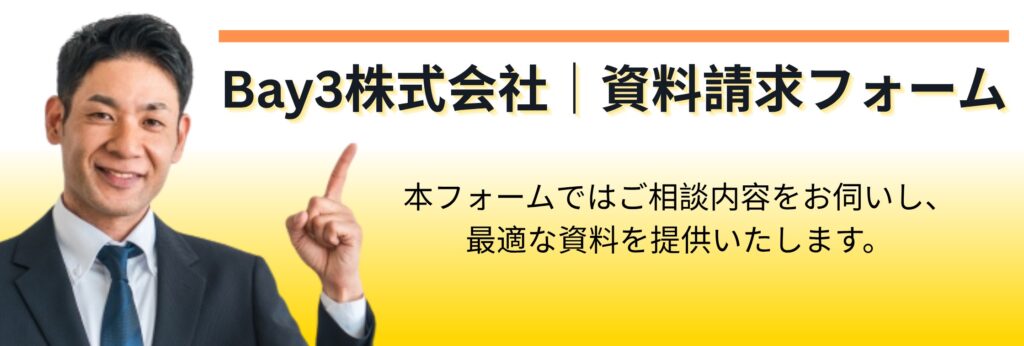「スタッフがすぐ辞めてしまう」「評価や給与に納得感がないと言われる」──そんな悩みを抱える歯科医院は少なくありません。
実は、これらの課題の多くは人事制度の不在や曖昧さに起因しています。
本ガイドでは、歯科医院がスタッフを大切に育て、安定経営を実現するために欠かせない人事制度の構築と運用のステップを分かりやすく紹介します。
評価の透明性を高め、モチベーションを引き出す仕組みを整えることで、医院は定着率の改善・採用力の強化・患者満足度の向上を同時に実現できます。
「制度を整えるのは大規模医院だけでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが、スタッフ数5名からでも取り入れられる実践的な方法があります。
ここでは7つのステップに分けて、人事制度のつくり方を解説していきます。
歯科医院における人事制度構築の重要性
まず押さえておきたいのは、なぜ人事制度が歯科医院にとって重要なのかというポイントです。
制度は単なるルールづくりではなく、医院の経営戦略そのものに直結します。評価・給与・目標管理・教育をきちんとリンクさせることで、スタッフは安心して働き、医院は持続的に成長できる土台をつくれるのです。
まずはサクッと現状診断しませんか?
評価の偏り/給与連動の曖昧さ/面談の滞りを30分で見える化。小さく始めて大きく外さないための第一歩です。
- チェック結果はその場でフィードバック
- 医院規模に合わせた優先順位表つき
なぜ歯科医院に人事制度が必要なのか
歯科医院は医療機関でありながら、患者さんから見れば接客業・サービス業の側面も強い職場です。
そこで働く歯科衛生士・歯科助手・受付スタッフにとって、評価や給与がどう決まるのかが見えない環境は大きな不安要素となります。
人事制度を導入することで得られる代表的なメリットは次の通りです:
- 評価基準の明確化:何を頑張れば昇給・昇格につながるかが分かる
- キャリアパスの提示:長く働くイメージが持てる
- 組織と個人の目標の統一:医院の成長とスタッフの成長がリンクする
つまり人事制度は、医院とスタッフ双方の「安心材料」であり、日々のやる気や医院経営の安定を支える土台になるのです。
評価の不透明さが招く離職と不満
制度がない状態では、どうしても院長の主観や感覚で評価や給与が決まりがちです。
するとスタッフからは、
- 「どうしてあの人だけ昇給したの?」
- 「頑張っても報われない」
- 「将来どうなれるのか全然見えない」
といった不満が噴き出します。
歯科衛生士や受付は転職市場でニーズが高いため、評価の不透明さは即・離職につながるリスク大。
逆に評価制度があれば、行動と成果がきちんと給与や昇格に反映されるので、納得感が高まり定着率の改善につながります。
制度構築がもたらす医院の成長と安定経営
人事制度の導入・構築は、単なる人材マネジメントの話にとどまりません。
医院の経営そのものを安定させ、成長スピードを上げる戦略的投資です。
具体的には次のような効果が期待できます:
- 離職率の低下 → 新規採用や教育コストを大幅削減
- サービス品質の向上 → 経験豊富なスタッフが長く定着し、患者満足度が上がる
- 組織文化の醸成 → 医院の理念やビジョンを共有する仲間が増え、チーム力が強化
競合医院が増える中で、制度構築は「選ばれる医院」になるための必須条件。
スタッフが安心して働ける環境を整えることが、最終的には患者からの信頼につながります。
人事制度の導入だけでなく、より包括的な視点から医院を変えたい方は、こちらの記事もご一読ください。
人事制度構築の全体像と基本ステップ
「人事制度をつくろう!」と思っても、いきなり評価シートや給与テーブルを作成するのは危険です。
まず全体像を理解し、順番を守って構築することが成功のカギになります。
ここでは制度設計の前に押さえるべき考え方と、7つのステップで実際に進める方法を解説します。
制度設計の前に押さえるべきポイント
制度構築を始める前に、次のポイントを整理しておくとスムーズです。
- 経営の方向性とリンクさせる:単なる評価や給与の仕組みではなく、医院の成長戦略と一体化させることが重要。
- シンプルで分かりやすくする:複雑な制度は現場で形骸化しがち。誰でも理解できる設計を意識。
- スタッフを巻き込む:院長だけで決めず、マネージャーやベテラン衛生士を巻き込むことで納得感が高まる。
- 運用を前提に考える:作って終わりではなく、評価・給与・面談に落とし込んでこそ意味がある。
この下準備ができていないと、「制度は作ったけど使われていない」という残念な結果になりがちです。
まずは経営・現場・未来の3つをつなぐ視点を持ちましょう。
7つのステップで進める人事制度構築の流れ
では実際にどう進めればいいのか?
歯科医院で取り組みやすいように7ステップに分解しました。
ステップ1:医院の理念とビジョンを明確化する
人事制度は「医院がどこに向かうのか」を示す羅針盤とセットで機能します。
理念やビジョンが曖昧なままでは、評価基準もブレやすく、スタッフも納得できません。
たとえば、
- 「地域に根ざした予防型歯科を広めたい」
- 「ホスピタリティを重視し、患者満足度No.1を目指す」
といったビジョンを打ち出すと、それに沿った行動指針や評価基準を設定しやすくなります。
ステップ2:求める人物像と行動指針を整理する
理念を具体的な人材像に落とし込みます。
「どんなスタッフに成長してほしいか」「医院にとって必要な価値観は何か」を言語化するのです。
たとえば、
- 患者さんへの丁寧な説明ができる
- チームワークを大切にする
- 自主的に学び、技術を磨く
といった行動指針を示せば、評価基準の骨格になります。
ステップ3:職種ごとの役割・業務内容を定義する
歯科医院は小規模でも多職種チームです。
歯科医師・衛生士・助手・受付など、それぞれの役割を明確にしないと評価が曖昧になります。
たとえば受付なら「予約管理・会計・電話応対」、衛生士なら「予防処置・指導・診療補助」といった業務をリスト化。
さらに「医院全体にどんな価値を生んでいるか」まで整理すると、評価項目に落とし込みやすくなります。
ステップ4:評価基準と評価項目を設計する
人事制度の中核は評価制度です。
「どんな行動や成果を評価するか」を基準と項目に落とし込みます。
代表的な観点は次の通り:
- 業務遂行力:診療や受付業務の正確性・スピード
- 接遇力:患者対応・言葉遣い・ホスピタリティ
- 協調性:チームワーク・周囲への協力姿勢
- 成長意欲:勉強会参加・資格取得・スキルアップ
数値化できる部分(売上や来院数)と、定性的な部分(接遇や協調性)をバランスよく組み合わせるのがポイントです。
ステップ5:給与・昇給・賞与との連動ルールを決める
評価が給与にどう反映されるかが見えないと、スタッフは納得しません。
「評価=給与への反映」が明確になって初めて、制度は定着します。
たとえば、
- 評価点数80点以上 → 昇給+5,000円
- 70点以上 → 昇給+3,000円
- 60点未満 → 昇給なし
といった形でルールをシンプルに提示すると分かりやすいです。
賞与も「評価+医院業績」の両軸で決めると公平感が高まります。
ステップ6:評価シートと面談フローを整備する
制度を現場で運用するためのツールとプロセスを整える段階です。
評価シートは「職種別×行動基準」で作成し、年2回の評価面談でフィードバックする流れをつくるのが一般的です。
面談では、
- 良かった点を具体的に伝える
- 改善点を一緒に考える
- 次の目標を合意形成する
といったステップを踏むと、単なる点数付けではなく成長を後押しする対話になります。
ステップ7:制度を運用・改善し続ける仕組みをつくる
制度は作って終わりではありません。
実際に回してみると「項目が多すぎて運用できない」「評価が甘くなりがち」といった課題が必ず出ます。
そこで大切なのは改善のサイクルを仕組み化すること。
年に1回は見直しミーティングを行い、スタッフの声を反映させると制度が生きたものになります。
こうして「理念→設計→運用→改善」の循環を回すことで、制度は医院の成長に合わせて進化し続けるのです。
そのまま使える「職種別評価シート」テンプレをプレゼント
衛生士・助手・受付の4指標×4段階ルーブリックと、昇給テーブル例をセットでお渡しします。
- 月次1on1メモのテンプレつき
- 配布してすぐ試運用OK
こちらの記事で、歯科スタッフの離職・モチベ低下を防ぐ成功法則について深く知ることも可能です。
評価制度を成功させるための工夫と現場浸透のポイント
人事制度を設計しただけでは意味がありません。
大切なのは現場に浸透させて、スタッフが納得して動けるようにすることです。
ここからは、評価制度を「使える仕組み」にするための工夫を紹介します。
院長・副院長・マネージャーの役割分担
歯科医院では、制度の運用が院長ひとりに偏ってしまうと、必ず負担が大きくなります。
そこでおすすめなのが役割分担です。
- 院長:理念・方針の発信者。評価制度の方向性を示す。
- 副院長や主任衛生士:日々の行動評価やフィードバックの担当。
- 事務長・マネージャー:シート管理や面談日程の調整、制度の運用サポート。
このように分担することで、評価が「院長の一存」ではなく組織としての仕組みになります。
スタッフが納得する評価の伝え方
評価は伝え方次第で意味が変わるもの。
点数だけを渡すと不満につながりますが、納得感のある伝え方をすればモチベーションアップにつながります。
フィードバック面談の進め方
フィードバック面談は単なる「成績発表」ではなく、スタッフの成長を支援する時間です。
次の流れで進めると効果的です。
- 良い点を具体的に伝える:「患者対応が丁寧で信頼につながっていたね」
- 改善点を一緒に考える:「説明のスピードを工夫すると、診療がもっとスムーズになるよ」
- 次の目標を合意形成する:「次回は新人の指導も任せてみようか」
この3ステップで行うと、スタッフは「評価されるだけ」でなく成長への期待を感じられます。
面談の質、台本で一気に上げましょう
褒め→課題→約束の3ステップ台本/NGワード集/目標サンプルの面談キットをご用意。
- 初回面談の同席サポートも可能
- スタッフの納得感が違います
モチベーションを高める対話のコツ
面談や日々の対話で、次のような工夫を取り入れるとモチベーションが高まりやすいです。
- 事実ベースで伝える:「あなたは患者アンケートで◯◯という評価を受けていた」
- 未来志向の言葉を使う:「次はどんな挑戦をしてみたい?」
- 本人の意見を引き出す:「どの業務にやりがいを感じる?」
一方的に伝えるのではなく、双方向の対話にすることで「この医院で頑張りたい」という気持ちが育ちます。
評価制度と教育・研修の連動
評価制度は教育・研修とセットで運用することで、初めて「成長の仕組み」になります。
評価だけで終わらせず、次にどう成長してもらうかを研修につなげましょう。
例としては、
- 接遇評価が低かったスタッフ → 接遇研修やロールプレイへ
- 技術面に課題のある衛生士 → 院内勉強会・外部セミナーへ
- リーダー候補 → マネジメント研修へ
このように「評価→教育→再評価」の流れを作れば、制度は単なる点数付けではなく人材育成のサイクルとして機能します。
定着率を高めるための運用チェックリスト
制度を現場に定着させるには、日々の運用がポイントです。
次のチェックリストを定期的に振り返ると良いでしょう。
- 年2回の評価面談を必ず実施しているか?
- 評価基準がスタッフ全員に周知されているか?
- 評価と給与の連動ルールを明確に示しているか?
- 面談で次の目標を合意形成できているか?
- スタッフの声を制度改善に反映できているか?
このように運用と改善を続けることが、評価制度を医院文化として根づかせ、結果的に定着率アップにつながります。
よくある失敗と回避のポイント
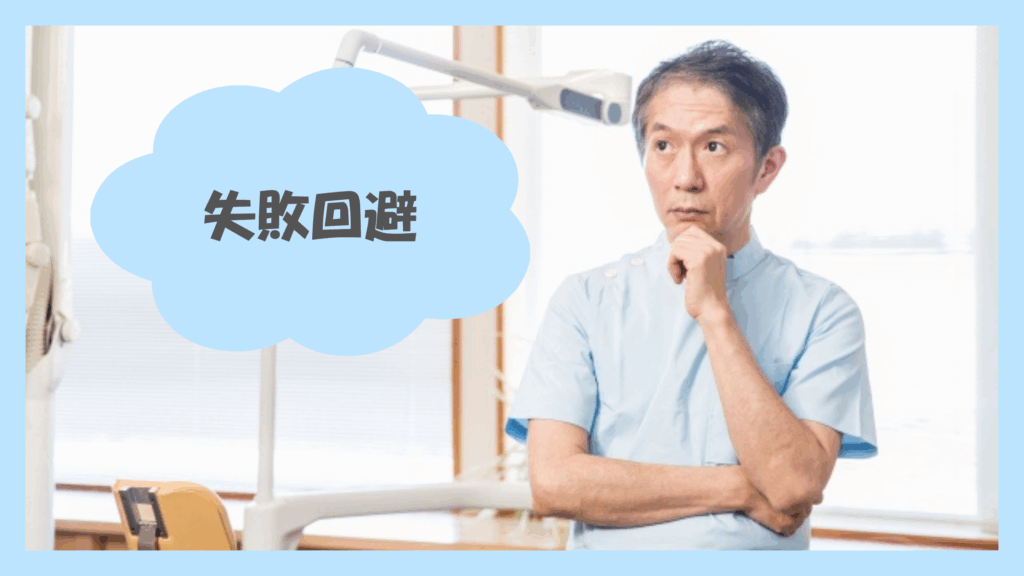
制度を構築した後に起きがちな「あるある」を先回りでつぶしておくと、運用が軽くなり、評価の透明性とスタッフ定着が一気に安定します。
ここでは歯科医院で頻出する失敗パターンと、今日からできる回避アクションをサクッと整理します。
評価基準が抽象的すぎる
「コミュニケーション力」「主体性」…きれいだけど、評価するときに人によって解釈が割れるワードは危険信号。抽象語だけだと公平性が崩れ、納得感が消えます。
- NG例:接遇が良い/チームワークがある
- OK例(観察可能に):初診患者へ治療計画を3分以内に要約し、理解確認の質問を1回以上行う/朝礼で1回以上、他職種の業務をフォローした事実を共有
回避アクション:
- 行動指標×頻度×品質で書く(例:「説明」「週◯回」「NPS/アンケート◯点以上」)
- 職種別に評価項目を分ける(衛生士/助手/受付/管理)
- 各項目にレベル定義(Lv1〜Lv4)を付け、サンプル記述を置く
給与との連動が曖昧で不満が出る
点数は出たのに給与や昇給がどう決まるかが見えないと、「結局、裁量で決まってる?」という疑念に直結します。
- よくある症状:評価Sでも昇給額が人によって違う/賞与が毎回「様子見」
回避アクション:
- 評価ランク→昇給テーブルを明示(例:S:+5,000円/A:+3,000円/B:+0円/C:改善プラン)
- 賞与=評価(個人)×業績(医院)の二軸に固定(例:個人係数S=1.2、A=1.0、B=0.8)
- 面談時にルールの印刷物を配布し、サインで合意を残す
運用が一度きりで形骸化する
シートを配って1回回しただけで満足…では制度は定着しません。改善サイクルが回らないと、現場とのズレが雪だるま式に。
回避アクション:
- 年2回の評価面談をカレンダー固定(上期:6月/下期:12月)
- 面談後1週間以内に個人目標(KPT)を確定し、月次1on1で進捗チェック
- 半期ごとに制度レビュー会(30分×全職種)を実施し、改善案を次期に反映
- ミニTips:項目が多いと回らない。まずは重要5項目×重み付けから始めると続きやすい。
院長だけに負担が集中するケース
全部を院長がやると、評価は遅れ、フィードバックは浅くなりがち。結果として「やっぱり制度は面倒だ」で終わります。
回避アクション(役割分担):
- 院長:理念・方針の発信、最終決裁、評価のバイアス是正
- 副院長/主任衛生士:日常の行動観察、一次評価、育成プラン作成
- 事務長/マネージャー:シート配布・回収、日程調整、記録管理、問い合わせ窓口
仕組み化のコツ:
評価委員会(15分×月1)を設置し、指標の解釈ズレをすり合わせ。属人化を防ぎ、公平性を担保します。
外部コンサルを入れるべきタイミング
自走は理想。ただ、以下に当てはまるなら外部支援で一気に整える方がコスパが良いです。
- 評価基準が3ヶ月以上まとまらない/現場からの反発が強い
- 職種別の評価項目や給与テーブルの設計で行き詰まり
- 面談運用が続かず、定着率が改善しない
外部に依頼するメリット:
- 短期で骨格を構築(テンプレ活用+医院向けカスタマイズ)
- 第三者視点でバイアス除去&現場の納得形成
- 運用設計(面談フロー/目標管理/教育連動)まで一気通貫で整備
まずは90日間の試運用を切って、課題抽出→改訂まで伴走してもらうと、制度が運用に乗りやすくなります。
次章では、いま挙げた落とし穴を避けつつ現場で回る仕組みにするために、評価×教育×面談の連動を事例ベースで深掘りします。
歯科医院の事例に学ぶ人事制度構築の実践

「制度は作った。さて、ここからどう“回す”?」をスッと解決するために、規模別の実践例をまとめました。
キーワードは評価の透明性/運用の軽さ/定着と成長の両立。すべて現場でそのまま使えるレベルに落とし込んでいます。
スタッフ5〜10名規模の小規模医院の取り組み
少人数はスピードとシンプルさが命。最短で「回る制度」にするコツは、紙一枚の運用から始めること。
- 評価の骨格:職種別4指標×4段階(Lv1〜4)のみ(例:衛生士=技術/接遇/協働/成長意欲)
- 面談フロー:月次10分(良かった行動→課題→次の一歩)+半期30分(評価×昇給)
- 給与連動:評価ランク→固定昇給額(S:+5,000円/A:+3,000円/B:0円/C:改善プラン)
- 目標設計:行動目標1つ+数値目標1つ(例:説明の定型フレーズ導入/キャンセル率2pt改善)
Before → After
- 属人的な評価 → 行動ルーブリックで基準を共有
- 面談が重い → 月次10分の軽い1on1へ
- 昇給が曖昧 → ランク連動の表で即決
90日スターターパック(例)
- 0〜30日:理念→行動指針→職種別4指標を定義、評価シート試作
- 31〜60日:月次1on1スタート、面談メモをテンプレで蓄積
- 61〜90日:半期評価を模擬運用→昇給テーブルを確定
ポイントは完璧主義を捨てること。まずは回し、次の半期で磨き込む——これが小規模の正解です。
20〜30名規模の中規模医院での成功事例
人数が増えたら一段深い設計が必要。役割の細分化と、等級(グレード)でのキャリアパスを見せます。
- グレード制:G1(新人)〜G5(主任)で役割・期待成果・給与レンジを明示
- 評価マトリクス:成果(KPI)×行動(バリュー)の2軸を50:50で採点
- 観察の分業:日常行動はリーダー評価、定量KPIは事務長が取りまとめ
- 教育連動:弱点に合わせて院内勉強会/外部研修/OJTの3ルートを用意
KPI例(職種別)
- 受付:来院率/無断キャンセル率/会計待ち時間/顧客コメント
- 衛生士:リコール率/説明同意率/施術時間のばらつき/患者NPS
- 助手:準備・片付け時間/滅菌手順遵守率/チーム支援件数
運用のコツ:各チームに評価リーダーを置き、月1で「評価すり合わせ会」(15分)を定例化。
これで解釈ズレを抑え、納得度を底上げできます。
「評価×患者満足度」をつなげた実行支援事例
評価が患者体験につながってこそ、医院の成長に効きます。以下は評価→NPS/再来率へ直結させた例。
- 接遇ルーブリック:初診対応、説明、見送りで各3チェック。「共感→要約→次回案内」ができれば満点。
- NPS連動:患者アンケートを月次で可視化し、チーム単位で振り返り。
- 重み付け:行動60:結果40で過度な数値偏重を回避(季節変動の影響を抑制)。
結果、説明の標準化→キャンセル率の改善/紹介経由の増加が見えやすくなり、スタッフのやりがいにも直結。
Bay3の現場支援から得られた知見
- 「1枚運用表」で回る:評価指標・面談日・昇給ルールを1枚に集約すると現場が迷わない。
- 最初は“5項目×重み”で十分:項目が多いほど形骸化。重要5項目の精度を上げる方が効果的。
- 面談は台本化:褒め→課題→約束の3ステップ台本で、フィードバックの質が均質化。
- AI活用は運用に効く:面談メモ自動要約/次期目標の草案生成で、1人あたり月30分削減が定番。
- 90日で“プロトタイプ→実戦”:完璧より、まず“回る”を優先。次の半期で磨く。
90日で「回る制度」へ。伴走します。
プロトタイプ→試運用→改訂まで、週次で実行支援。小規模〜中規模の医院に最適化します。
- 最初から完璧を目指さず運用前提で設計
- AI活用で運用負担を軽く
評価制度導入のより具体的な成功事例を知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
まとめ|制度をつくるだけでなく“育てていく”ことが大切

制度はプロダクト。作って終わりではなく、ユーザー(スタッフ)と一緒に育てることで、評価の透明性・運用の軽さ・定着と成長がそろいます。
院長が押さえるべき3つの視点
- 公平性と透明性:行動定義は観察可能に。評価→昇給テーブルは紙で配布。
- 運用の軽さ:月次10分1on1+半期30分で回る設計。項目は重要5に絞る。
- 成長への接続:評価→教育/研修→再評価のサイクルを固定。弱点は仕組みで補強。
制度構築を医院の成長戦略とリンクさせる
- 採用ブランディング:評価基準とキャリアパスを求人票に明記→応募率UP。
- 教育投資の可視化:研修→行動変化→NPS/再来率の改善をダッシュボードで共有。
- 収益モデルに接続:説明同意率・チェア稼働率・キャンセル率などのKPIを評価に反映。
制度=コストではなく、成長ドライバーとして設計する。これが選ばれる医院の共通点です。
資料請求・相談で得られる具体的サポート内容
- 現状診断:評価の偏り/運用ボトルネックを30分で見える化
- 職種別ルーブリック雛形:衛生士・受付・助手・事務向けの評価項目テンプレ
- 給与テーブル設計:評価ランク連動の昇給・賞与ルールを医院規模に最適化
- 面談キット:台本・メモテンプレ・NGワード集までセット
- 教育連動パック:弱点別の研修カリキュラムとロールプレイ台本
- 90日伴走:試運用→改善→本運用までを週次でサポート
- AI活用支援:面談ログの自動要約/目標ドラフト生成/月次KPIサマリー化
「まずは小さく回して、次の半期で磨く」。
一緒に、現場で回る制度をつくっていきましょう。
資料で一気に把握。今日から動ける設計書つき。
制度全体像/評価項目例/給与連動ルール/運用チェックリストを1冊に凝縮。