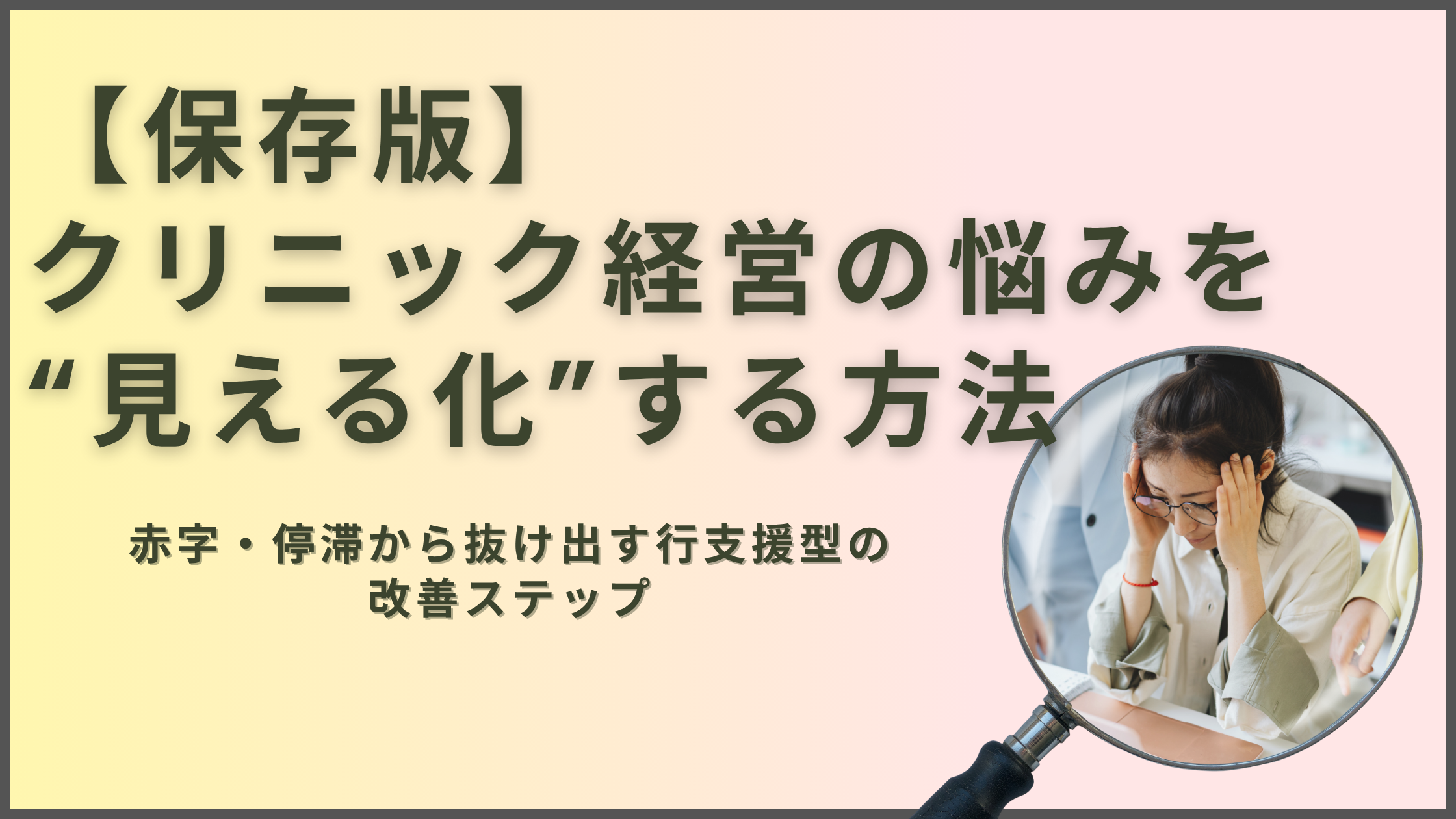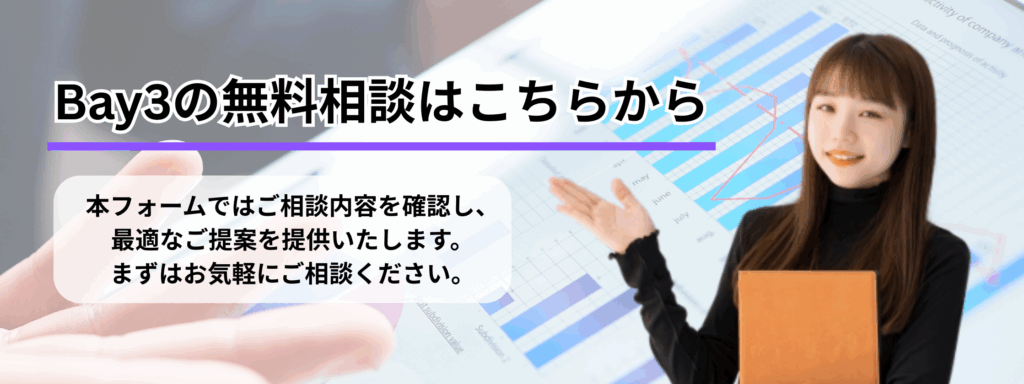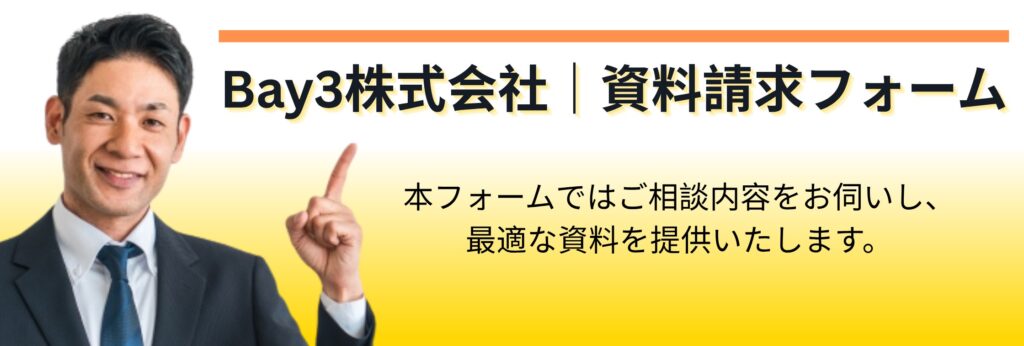開業から数年が経ち、地域に根づいてきたはずなのに——
「利益が出にくくなった」「スタッフが疲れている」「次の打ち手が浮かばない」
そんな“なんとなく停滞している”クリニックが増えています。
原因は、単なる不況や競争ではありません。
多くのケースで共通しているのは、「経営の見える化」が不十分なこと。
感覚や経験だけに頼った経営では、外部環境の変化に対応できません。
この記事では、数字と行動の両面から経営を立て直す「実行支援型の改善ステップ」を解説します。
自院の課題を“見える化”することで、赤字・停滞から脱却する具体的な方法が分かります。
なぜ今、クリニック経営に「悩み」を抱える院長が増えているのか

利益率が下がる背景|人件費・物価上昇・競合増加の三重苦
近年、クリニック経営を取り巻く環境は大きく変化しました。
特に次の「三重苦」が、多くのクリニックを圧迫しています。
- ① 人件費の上昇: 医療事務や看護師の採用難により、人件費が固定費を圧迫。
- ② 物価・光熱費の高騰: 医療材料や電気代の上昇で、1件あたりの利益率が低下。
- ③ 競合の増加: 同エリアでの新規開業が相次ぎ、患者の取り合いが発生。
このように外部環境の変化は避けられません。
しかし、本質的な問題は「外部要因」ではなく、“内部の見える化”が追いついていないこと。
損益構造・KPI(新患数・再来率・稼働率など)を把握し、早期に手を打つことが重要です。
クリニック経営の停滞を招く3つの原因
結論から言えば、多くのクリニックが伸び悩む理由は「仕組み化されていない経営」にあります。
感覚頼りの判断、属人的な運営、そして“実行されない改善策”――。
どれも一見バラバラのようでいて、根本は「見える化」と「実行体制」の欠如に行き着きます。
ここでは、経営が止まってしまう3つの典型パターンを整理します。
原因① 経営の現状を“感覚”で判断している
多くの院長が「なんとなく経営は大丈夫」と感じているうちに、数字が悪化しています。
損益やKPIが見えないまま感覚で判断していることが、停滞の最大要因です。
「患者数は減っていないはず」「経費はそこまで増えていない」と思い込んでいても、
実際には利益が出ていないケースが非常に多いのが現実です。
経営を感覚で判断していると、原因分析も打ち手もズレてしまいます。
見える経営に変えるためには、次のような視点が欠かせません。
- 売上、原価、人件費、広告費などの主要項目を「月次で可視化」する
- KPI(新患比率、再来率、単価、稼働率など)を定点観測する
- 会議で数字を共有し、次の行動を明確にする
損益やKPIを可視化していないと、正しい打ち手が見えない
経営の数字を把握していない状態では、改善の方向性が定まりません。
例えば、売上が下がったときも「患者数の減少」なのか「単価の低下」なのかが分からない。
原因が分からないまま施策を打っても、結果は運任せです。
損益計算書(P/L)や月次KPIをダッシュボード化し、
「どの数値が動けば利益が変わるのか」を明確にすることが最初の一歩です。
数字が見えれば、次の一手が“感覚”ではなく“戦略”で決められます。
原因② 会議・マネジメントが属人的になっている
次に多いのが、院長にすべてが集中してしまう属人経営です。
「院長がいないと回らない」「判断を仰がないと何も決まらない」――
この状態では、どれだけ優秀なスタッフがいてもチームは育ちません。
スタッフが自立的に動く組織をつくるためには、
「会議体」と「マネジメントの仕組み」を整備する必要があります。
- 定例ミーティングを設定し、進捗・課題・施策を共有
- 役職・担当者ごとに権限を明確化
- 目標と評価を紐づけ、行動を数値で見える化
会議設計が整うと、院長の指示がなくても現場が動けるようになります。
つまり、組織で経営する仕組みができるということです。
院長のカリスマ依存ではチームが育たない理由
院長のリーダーシップは重要ですが、すべてを背負うスタイルには限界があります。
カリスマ経営は短期的には成果を出せても、持続性が低いのが特徴です。
なぜなら、スタッフが「考える前に院長の答えを待つ」ようになるから。
結果として、成長意欲が下がり、離職リスクが高まります。
持続的な経営を実現するには、
- 院長が“決める人”から“仕組みを作る人”へシフトする
- 権限委譲と仕組み設計を通じて「考える現場」を育てる
ことが不可欠です。
原因③ 改善策を立てても“実行されない”現場構造
「改善会議はしているのに、現場が動かない」――そんな悩みも多いもの。
実は、“実行まで落とし込めていない”ことが原因です。
改善策を話し合っても、担当・期限・数値目標が曖昧だと、
誰も行動できずに「やることリスト」で終わってしまいます。
「やることリスト」で終わる経営改善の落とし穴
多くのクリニックが陥るのが、「話した=やった気になる」罠。
会議で課題を出しても、次回までに何が進んだのか分からない。
これでは、どんなに良い戦略も成果につながりません。
解決のカギは、“実行支援”の仕組み化です。
- 施策ごとに「担当者・期限・目標数値」を設定
- 会議で進捗をチェックし、達成度をKPIで評価
- 改善→実行→検証のサイクルを定例化
このように、“実行される仕組み”を整えることで、
ようやく「戦略が成果になる経営」に変わります。
こちらの記事でも、給与面での仕組み化の手順を詳しく解説しています。是非ご活用ください。
“見える化”でクリニック経営を立て直す4つのステップ

結論から言えば、停滞しているクリニック経営を再び成長軌道に乗せるには、
「数字を見える化」し、現場と一緒に実行していく仕組みが不可欠です。
ここでは、赤字や停滞から脱却したクリニックが実際に行っている、
4つの改善ステップを紹介します。
ステップ① 経営状況の“見える化”で課題を特定す
まず最初の一歩は、「経営の現状を数字で正確に把握すること」です。
多くのクリニックでは、損益やKPIが見えないまま「忙しい=順調」と思い込み、
課題の本質を見逃しています。
財務・人事・業務データを整理し、現状を数値で把
感覚ではなく、データに基づく経営判断を行うためには、
以下の“3つの見える化”が重要です。
- 財務の見える化: 売上、原価、人件費、広告費、利益率を月次で整理。
- 人事の見える化: スタッフ別の労働時間、評価、定着率を把握。
- 業務の見える化: 予約件数、キャンセル率、稼働率、患者満足度などを可視化。
こうしたデータを“見える化”することで、
「どこにムダがあるのか」「どの施策が利益に直結しているのか」を明確にできます。
ステップ② 経営計画を再構築し、KPIを設定する
現状を可視化したら、次にやるべきは「再設計」です。
目標があいまいなままでは、どれだけ会議をしても成果は出ません。
ここで重要なのが、“実現可能なKPIを設定する”という視点です。
“理想論”ではなく“実現可能な計画”を現場と一緒に作る
KPI(重要業績評価指標)は、経営者だけが決めるものではなく、
現場スタッフと一緒に設定することで初めて意味を持ちます。
例えば、
- 新患数:月100人 → 現状80人なら、まずは85人を目標に
- 稼働率:80% → 改善余地のある時間帯を特定して底上げ
- 販促費:広告費をROI(費用対効果)ベースで評価
現場の理解と納得を得たうえでKPIを設定すれば、
「数字=自分ごと」になり、チーム全体の行動が変わります。
ステップ③ 会議体・マネジメントを仕組み化する
“見える化”とKPI設定ができたら、次に必要なのは
「行動を定着させる場」です。
その中心となるのが、会議体とマネジメントの仕組み化です。
属人運営を脱し、チームで動ける仕組みを設計
院長一人に意思決定が集中していると、スピードも再現性も失われます。
これを解消するために、次の3つを整えると効果的です。
- 定例ミーティングの導入:週1回の短時間ミーティングで進捗と課題を共有
- アクションログの作成:決まった施策を「担当・期限・数値」で明確化
- 権限委譲の仕組み:現場リーダーが判断できる範囲を明確にする
このような会議設計を行うことで、院長がいなくてもチームが動ける環境が整います。
結果として、組織全体の自走力が高まり、現場の定着率も改善されます。
ステップ④ 実行支援型パートナーと伴走して改善を定着させる
最後のステップは、「外部の実行支援パートナー」との連携です。
どれだけ優れた計画を立てても、実行が続かなければ意味がありません。
そのためには、“やり切る仕組み”を作る専門家の伴走が不可欠です。
机上の提案ではなく、“実行”まで支援する体制をつくる
実行支援型パートナーは、単なるコンサルではありません。
現場に入り込み、数字と行動をつなぐ仕組みを一緒に作り、運用まで支えます。
例えば、
- 会議ファシリテーションを支援し、意思決定を加速させる
- KPI進捗をモニタリングし、改善点をフィードバック
- 経営者・スタッフ双方の行動変化を促す仕組みを構築
こうした継続的な支援によって、施策が“やりっぱなし”にならず、
組織の成長サイクルが回り続けるようになります。
結論として、
クリニック経営の立て直しは、
「数字の見える化」から始まり、「実行の仕組み化」で終わる
この4つのステップを実践することで、経営は安定し、現場は前向きに動き始めます。
そして何よりも重要なのは、「伴走してくれるパートナー」を持つこと。
それが、継続的な成長への最短ルートです。
まずは無料相談で、現状の課題を一緒に整理・相性の確認をしてみませんか?
▶ [無料で相談する]
KPIや目標設定の具体的な仕組み化についてもっと知りたい方は、こちらの記事が実践的な参考になります。
成功事例|数字と行動で赤字から脱却したクリニックの実例
結論から言えば、「見える化」と「実行支援」を組み合わせることで、経営は確実に変わります。
ここでは、Bay3が実際に支援した3つのクリニックの事例を紹介します。
どのケースも「課題の可視化 → 行動設計 → 実行支援」によって、数字が改善しています。
事例①:月次損益を“見える化”し、利益率10%アップ
このクリニックでは、毎月の収支を「なんとなく黒字」としか把握していませんでした。
しかし、実際に月次損益(P/L)を分析してみると、人件費率が40%を超え、広告費が過剰であることが判明。
そこで取り組んだのが「経営ダッシュボードの導入」。
- 売上・人件費・広告費・利益を可視化
- KPI(新患数・稼働率・キャンセル率)を毎月レビュー
- コスト削減とスタッフシフトの最適化を同時実行
結果、半年で利益率が7%→17%に改善。
数字を“見える化”したことで、経営判断の精度が上がり、迷いのない投資ができるようになりました。
事例②:会議設計でスタッフの主体性が向上
別のクリニックでは、院長が全てを決める属人経営が課題でした。
「スタッフが受け身」「改善提案が出ない」という状況で、現場の停滞感が強かったのです。
そこで、週1回の「進捗・課題共有会議」を新設。
Bay3が会議設計をサポートし、次のルールを導入しました。
- 各担当者が数字(KPI)をもとに報告
- 改善案を全員でディスカッション
- 決定事項は「担当・期限・目的」を明記
3か月後には、スタッフから自発的な改善提案が出始め、
「院長がいなくても会議が回る」状態に。
結果、施策実行率が大幅に向上し、業務効率が20%アップ。
チームの空気が前向きに変わり、離職率も低下しました。
事例③:経営相談の伴走支援で1年後に黒字化達成
開業5年目のクリニックでは、赤字が続き、「何から手をつければいいか分からない」という状態でした。
経営分析を行うと、患者数・単価・人件費・会議体すべてに改善余地があることが判明。
Bay3は「経営伴走支援」として以下を実行:
- 中期経営計画の再構築(数値目標と現場アクションをリンク)
- 評価制度と給与テーブルの設計
- 会議運営のファシリテーション支援
定例ミーティングで数字をチェックしながら、施策を毎月改善。
結果、1年後には黒字化を達成し、スタッフ定着率も25%向上。
院長自身も「悩む時間が減り、判断が早くなった」と語っています。
スタッフ育成や会議運営を安定させたい場合は、こちらの記事もあわせて読むと、定着率を高めるヒントが得られます。
経営改善を成功させるパートナー選びの3つのポイント
結論から言えば、経営改善を継続的に成功させるには、
“提案型”ではなく“実行支援型”のパートナーを選ぶことが重要です。
単発のコンサルでは一時的に良くなっても、定着しないのが現実。
ここでは、信頼できる経営パートナーを見極める3つのポイントを紹介します。
1. “実行支援”まで伴走できるコンサルを選ぶ
提案や資料だけで終わる支援では、現場に変化は起きません。
選ぶべきは、「一緒に手を動かすコンサル」です。
- 施策を立てるだけでなく、実際に現場で実行・検証してくれる
- KPIの進捗を一緒にモニタリングし、改善をサポート
- “報告を受ける側”ではなく、“共に走る伴走者”として動く
Bay3が重視しているのは、まさにこの「実行支援」の姿勢です。
現場に入り、成果が出るまで伴走することで、再現性のある経営改善が可能になります。
2. 現場データをもとに課題を可視化してくれるか
良いパートナーは、主観や感覚ではなく、「現場データ」から課題を見つけ出す力を持っています。
- 財務・人事・業務データを整理し、「今どこに課題があるか」を数値で提示
- KPIをもとに優先度を決め、施策を実行
- データを使いながら、チームの理解と納得を得る
つまり、“見える化”から始まるコンサルこそ、長期的に信頼できるパートナーです。
3. 院長・スタッフ両方に寄り添える支援体制があるか
経営改善は「数字」だけではなく、「人」が動かなければ続きません。
したがって、院長とスタッフ双方に寄り添える支援体制を持つパートナーが理想です。
- 院長には経営視点の整理と意思決定支援
- スタッフには行動変化を促す研修や仕組み設計
- 双方が納得できる評価制度や会議体の設計
Bay3のように、現場に入り、対話しながら仕組みを作る伴走型支援であれば、
「やって終わり」ではなく、「続く経営改善」が実現します。
結論として、
経営改善を成功に導くのは、「提案書の上手な会社」ではなく、
「現場を動かし、数字を変える会社」です。
あなたのクリニックにも、本気で伴走してくれるパートナーが必要です。
まとめ|数字と行動でクリニック経営を再構築する

結論から言えば、クリニック経営を立て直す最短ルートは、
「数字の見える化」と「行動の仕組み化」を両立させることです。
多くの院長が悩む経営課題は、外部環境だけでなく
「内部の仕組み」が整っていないことに原因があります。
見える化によって現状を正しく把握し、
行動を仕組み化して継続することで、経営は確実に変わります。
“見える化”こそ、経営を立て直す第一歩
「忙しいのに利益が出ない」「頑張っているのに伸びない」――
そんな悩みを解決する第一歩は、感覚経営から脱却することです。
- 売上・人件費・稼働率などの数字を可視化する
- KPIを設定し、チーム全体で共有する
- 会議で数字をもとに意思決定を行う
この「見える化」が進むと、課題の原因がはっきり見え、
「何を変えれば成果が出るのか」が分かるようになります。
数字を“見える化”することは、経営を「勘」から「戦略」に変える第一歩です。
現場と一緒に実行するから、改善が“定着”する
どんなに良い計画を立てても、「現場が動かない」ままでは成果は出ません。
経営改善は“現場と一緒に”やってこそ定着します。
たとえば、
- スタッフがKPIを理解し、自分の役割を認識している
- 会議で決まったことが「誰が・いつまでに・どのように」を明確化
- 院長とスタッフの目線が一致し、同じ方向を向いている
この状態がつくれれば、経営改善は一過性ではなく、文化として根づくようになります。
つまり、数字だけではなく「行動」と「意識」を変えることが、本当の意味での改善です。
現状を“見える化”して、経営改善の第一歩を踏み出そう
経営の悩みは、放置していても自然に解決することはありません。
大切なのは、「今の課題を数字と行動の両面で見える化」すること。
そして、その一歩を専門の伴走パートナーと一緒に踏み出すことです。
Bay3では、
- 経営データの整理(損益・KPI・業務フロー)
- 現場ヒアリングによる課題抽出
- 改善優先度の可視化
を通して、あなたのクリニックに最適な改善プランを“実行可能な形”でご提案します。
「どこから手をつければいいか分からない」
「自分の判断が正しいか不安」
そんな段階でも大丈夫です。
まずは無料相談で、現状の課題を一緒に整理してみませんか?