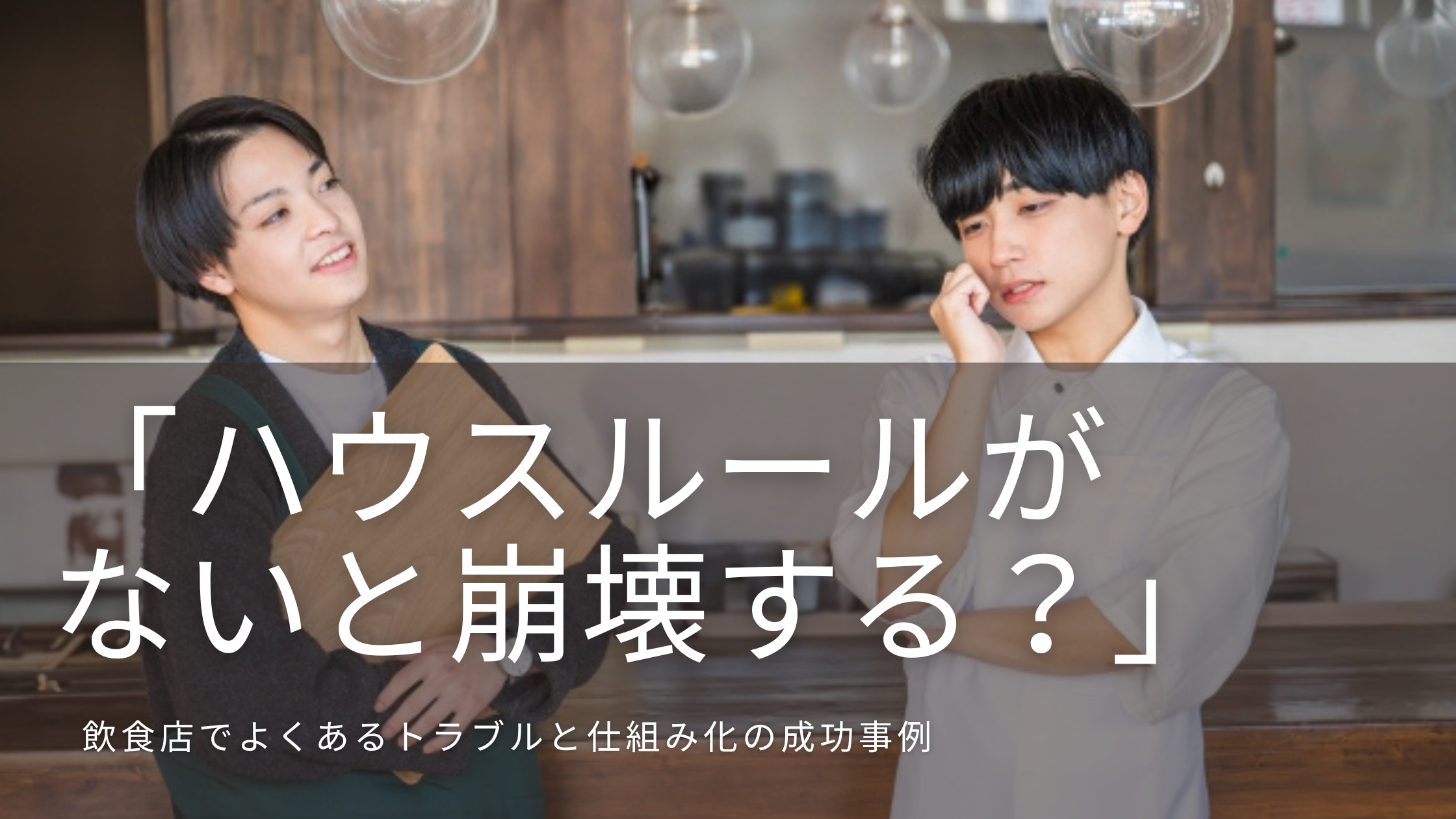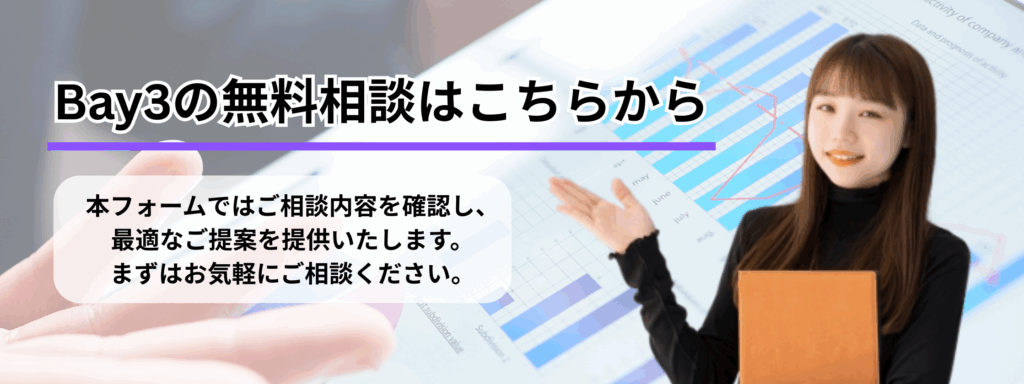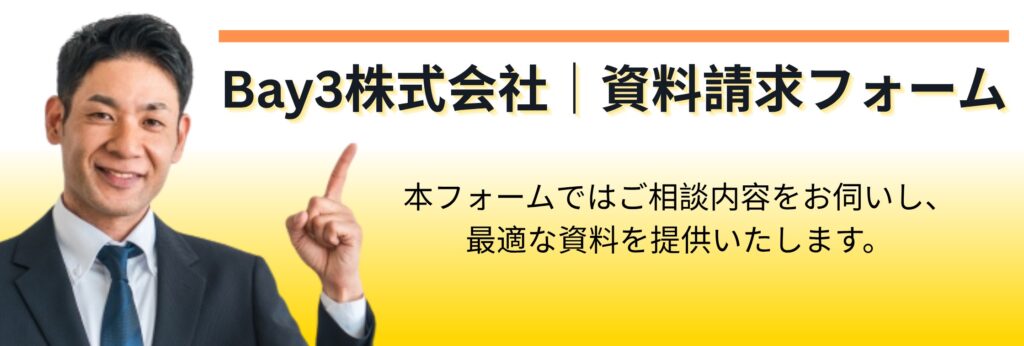「最近スタッフの遅刻が増えてきた」「接客の質がバラバラ」「注意するとすぐ辞める」——。
そんな悩みを抱える飲食店オーナーや店長は少なくありません。現場では、ルールがないことで小さな混乱が積み重なり、大きな崩壊を招くケースも。
この記事では、飲食店の運営に欠かせない「ハウスルール」について、ありがちなトラブル事例から、うまくいった成功パターン、すぐに使えるルール例までを紹介します。
実際の現場で「ある・ない」でこんなに違うのか?と感じてもらえるはず。
「言わなくても分かる」はもう通じない時代。今こそ、ルールで現場を守る仕組みを一緒につくりましょう。
▶ プロに相談しながら仕組み作りを行いたい方はこちら
そもそもハウスルールとは?飲食店が導入すべき理由
ハウスルールとは、店舗ごとの「働くうえでの当たり前」を言語化した独自ルールのこと。
勤務態度・シフト連絡・接客対応など、マニュアルではカバーしきれない“現場で大切にしている価値観”を共有するために必要な仕組みです。
ルールが曖昧なままだと、スタッフごとに対応がバラバラになり、トラブルやストレスの原因に。
とくにアルバイトや老若男女が働く飲食店では、「常識でしょ」が通じず、すれ違いや離職にもつながりかねません。
だからこそ、ハウスルールは“お店を守るための最低限の約束事”。現場の温度差を埋め、安定したチーム運営には欠かせない存在です。
会社のルール全般の重要性については、こちらの記事も合わせてご参照ください。
マニュアルとの違いは?曖昧なラインを明確にする
マニュアルは「業務のやり方」、ハウスルールは「人としてのふるまい方」を示します。
この違いをあいまいにしている店舗ほど、スタッフ同士のトラブルが多い傾向にあります。
たとえば——
どちらも大事ですが、後者のような人間関係や空気感に関わるルールは、言わないと伝わりません。
マニュアルとハウスルールはセットで運用することで、店舗の“らしさ”と一体感をつくる力になります。
「言わなくても分かる」はもう通じない
飲食店は「スピード」と「人間関係」が命。だけど、現場で起きるイライラの多くは「ルールの不一致」から。
とくに最近の若手スタッフは「どうして怒られたのか分からない」「最初に言ってくれればやったのに」と感じるケースが多数。
つまり、“言ってないこと”は、存在しないのと同じです。
- 遅刻はLINEでOK?電話がマスト?
- 私語はどこまで許される?
- 誰が何を片付ける?指示がなければやらなくていい?
これらの判断をすべて店長が個別に対応していたら、回らなくなります。
「言わなくても分かる」を捨てて、最初から共通認識にしておくことが、チーム崩壊を防ぐ第一歩です。
飲食店がルールを明文化する3つのメリット
ハウスルールを明文化するだけで、想像以上に現場のストレスが減ります。主なメリットは以下の3つです。
- トラブルが未然に防げる
「やった・やらない」「言った・聞いてない」などの摩擦が減り、スタッフ同士の信頼関係が築きやすくなります。 - 教育コストが下がる
新人に何度も説明する必要がなくなり、育成の属人化も防止。複数店舗でもルールの再現性が高まります。 - 店長・社員の負担が軽減される
都度の注意や説明が不要になり、本来やるべきマネジメント業務に集中できます。
ルールはスタッフを縛るためのものではなく、「気持ちよく働くための土台」。
だからこそ、明文化は現場を守る最もシンプルな改善策なんです。
中長期経営計画を確実に実行に移すためのステップについては、こちらの記事もご参照いただくと、より具体的に理解が深まります。
ハウスルールがないとどうなる?実際にあった“現場の崩壊”例

ハウスルールを軽視した結果、現場がじわじわと崩れていく——そんな飲食店の実例は後を絶ちません。
明文化されていない“なんとなくのルール”に頼っていると、スタッフのモチベーションが下がり、チームがバラバラになります。
ここでは、実際によくある3つの「ルール不足が招いた失敗例」を紹介します。
どれも「うちもそうかも…」と思い当たる話ばかりかもしれません。
無断欠勤・遅刻が頻発し、他スタッフの士気が低下
「また今日も連絡なしで来ない」「遅れて来たのに平気な顔」——。
そんなスタッフが増えると、真面目に働いている人ほどやる気を失っていきます。
ハウスルールがない店舗では、「連絡は何分前まで?」「遅刻は何回までOK?」といった基本のルールが曖昧になりがち。
結果として、スタッフによって対応がバラバラになり、「あの子は許されたのに、自分だけ注意された」と不満が溜まります。
- 無断欠勤を“許した”ことで他のスタッフも真似する
- 注意すると「そんなの聞いてない」と逆ギレ
- 真面目な人が辞めて、なぜか問題児だけ残る
こうなったら手遅れです。まずはルールで基準を整えることが、チームの士気を守る第一歩です。
「言った/言わない」のトラブルで現場がギスギス
店長:「この前言ったよね?」
スタッフ:「聞いてませんけど…」
——このやり取り、飲食店あるあるではないでしょうか。
ルールが口頭ベースだったり、人によって言ってることが違ったりすると、どんどん「不信感」が蓄積していきます。
- 勤務中のスマホ使用は禁止?OK?
- 賄いのルール、シフト希望の締切…誰が何を決めてる?
- 店長がいないと注意できない雰囲気が漂う
こうした状況では、チームの空気は確実に悪化します。
「言った/言わない」を無くすには、“書いてあるかどうか”が最も強い武器です。
店長に負荷が集中、回らなくなったお店の末路
ルールがない現場では、最終判断がすべて店長に集中します。
「これってやっていいんですか?」「今日のシフト、●●さんが来ないみたいです」——そのたびに判断・対応・謝罪。
気づけば店長は現場もマネジメントも全部一人で抱える状態に。
そして、ある日限界を迎えます。
- 店長が体調を崩して現場が回らなくなる
- シフト対応が属人化して引き継げない
- スタッフが育たず、“自走”できるチームが育たない
「ルールがない=全部、店長が考える」構造になってしまうんです。
ハウスルールは、店長が“いなくても回る”仕組みをつくるツール。自分を守る意味でも、今こそ見直す価値があります。
属人化から脱却し、組織の成果を最大化するステップについては、こちらの記事も参考になります。
飲食店のハウスルール成功事例|どう変わった?何が効いた?
「本当にルールで変わるの?」と半信半疑の方にこそ知ってほしい、実際の改善ストーリーを紹介します。
どれも特別なノウハウではなく、“たった一つの明文化”で現場がガラッと変わった事例ばかりです。
属人化しがちな飲食店運営も、ルールがあるだけで「仕組み」として回り始める。
その実感を持ってもらえるはずです。
ある焼肉店の例:出勤ルールの明文化で遅刻が激減
都内の焼肉店では、シフトに入っていたスタッフが「5分遅れ」「ドタキャン」することが頻発。
店長が毎回対応に追われ、他スタッフにも悪影響が出ていました。
そこで取り組んだのが、「出勤に関するルールの明文化」。
- 連絡なしの無断欠勤は即日アウト
- 遅刻・欠勤の連絡は◯時間前までに電話
- LINE連絡は原則NG(どうしてもなら要既読確認)
この3行を紙にまとめて共有しただけで、月に5〜6件あった遅刻がゼロに。
それまでは“店長の気分”と思われていた指導も、ルールがあることで納得されやすくなりました。
結果として、注意の回数も減り、スタッフの間でも声かけし合う文化が自然と生まれたそうです。
学生アルバイトの定着率が2倍に上がったカフェの工夫
とある地方のカフェでは、毎年バイトの離職が多く、半年以内にやめる人が7割近く。
その原因は「何がOKで、何がNGか分からない」という不安からくるストレスでした。
そこで、オーナーが始めたのが“ルールブックの配布”。内容はとてもシンプルで…
- お客様と話し込まない
- 休憩中のスマホ利用はOK、ただし業務時間中はNG
- 分からないことは「すみません」より「●●さんに聞いてみます」と返す
このように**「なんとなく」指導していたことを言語化しただけで、空気が一変。
「やっていいこと/いけないこと」が明確になり、スタッフの不安が激減。結果的に離職率が半減し、1年以上働く学生が倍増**しました。
「なんとなく注意」がなくなり、マネジメントの再現性がUP
チェーン展開を進めるあるラーメン店グループでは、店長ごとに指導方針がバラバラ。
同じ接客でも、ある店では褒められ、別の店では怒られる——そんなズレが混乱を生んでいました。
そこで導入したのが「接客ルールの標準化」。具体的には、
- 3ステップでの挨拶ルール(入店/注文/退店)
- クレーム対応は必ず社員が対応し、バイトには任せない
- 注意は“●●の場合は××”と事例ベースで統一
この仕組みを導入したことで、マネジメントの属人化が減少し、店長の経験年数に関わらず一定のレベルが保たれるように。
何より効果的だったのは、「なぜこれが必要か」まで含めてルールにしていた点。
“考えさせる教育”ではなく“迷わない仕組み”で、店舗運営が安定した好例です。
▶ もっと成功例を見たい方は、資料請求も是非ご活用ください
飲食店のハウスルール|最低限おさえたい10のルール項目
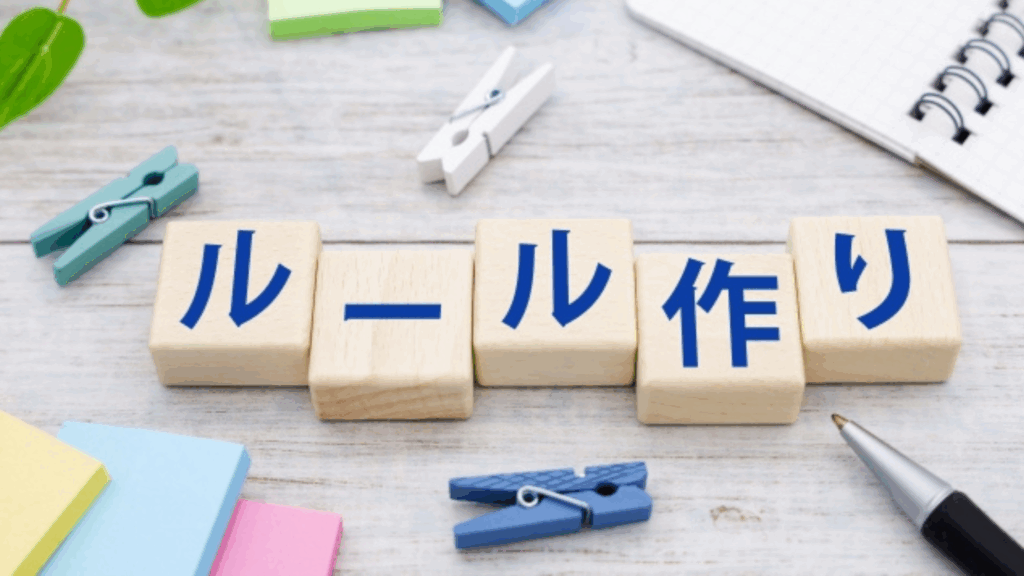
「ハウスルールを作ると言っても、何をどう決めればいいのか分からない」——そんな声をよく聞きます。
実際の現場で効果があったルールの中から、まず押さえておくべき10項目をテーマ別に整理しました。
どれもスタッフ間のトラブルを未然に防ぎ、働きやすさ・定着率をグッと上げるポイントです。
勤務・シフトに関するルール
シフト関連はトラブルの温床。明確にしておくだけで、現場の混乱はかなり減ります。
- シフト提出の締切と連絡方法(例:毎月◯日まで、LINEは禁止)
- 無断欠勤・遅刻の定義とペナルティ(例:◯回で注意、◯回で契約見直し)
- 急な休み希望への対応基準(例:病欠はOK、私用は基本NGなど)
- 「代打」依頼のルール(例:本人が探す/社員が調整)
とくに若手スタッフほど「遅れてもLINEすればいいでしょ?」と思いがち。“甘えのライン”を明確に線引きすることが大切です。
接客・サービスの共通ルール
接客ルールはお店の“顔”に直結します。細かいけれど、大事なところこそルール化しておきましょう。
- 挨拶のタイミングとトーン(例:3秒以内に“いらっしゃいませ”)
- お客様への言葉遣い(例:「了解」はNG→「かしこまりました」)
- オーダー時の確認フロー(例:復唱必須、禁煙席確認など)
- レジ対応時の笑顔・目線・お礼の言い方
「常識でしょ」ではなく、“うちではこう”を共有することがブランドを守る近道です。
清掃・衛生・制服など、店を守るルール
飲食店としての信頼性に直結するのがこのカテゴリ。意外とスタッフ任せになりがちなので、ルール化は必須です。
- 制服の着方・身だしなみ(例:エプロンの結び方/アクセサリーNGなど)
- 清掃チェック項目(例:トイレ、厨房、冷蔵庫の拭き掃除の頻度)
- 手洗い・手袋のルール(例:1時間に1回は必ず洗う/食材ごとに手袋交換)
- ゴミの分別と出し方(例:何時に誰が、どこへ)
こういったルールが徹底されると、保健所対応・クレーム防止・衛生トラブルの抑止にもつながります。
注意・指導の仕方やペナルティルール
最後に意外と忘れがちなのが「ルール違反があったときの対応ルール」。これがあると、注意がしやすくなります。
- 指導は誰がどう行うか(例:バイトには社員のみが注意)
- 注意するタイミングと伝え方(例:お客様がいない場所で/必ず理由を伝える)
- 累積ペナルティのルール(例:月◯回で注意書提出→退職勧告)
- 改善が見られた場合の評価制度(例:●ヶ月継続で表彰/昇給対象)
これにより、スタッフ間でも「指導の基準」が見えるようになり、“なんとなく叱る”がなくなります。
ハウスルールを“作って終わり”にしないために|運用・共有のコツ

どんなに良いルールでも、共有されなければ意味がありません。
「作って満足」で終わると、スタッフは「知らなかった」「聞いてない」となり、結局トラブルは繰り返されます。
ここでは、“伝える・納得させる・定着させる”ための運用テクニックを紹介します。
飲食店の現場で無理なく回るやり方に絞っているので、明日からすぐに実践できます。
ルールの周知・教育方法(スタッフミーティング/配布物/掲示など)
ハウスルールは作るより「どう伝えるか」が重要。方法はシンプルでも、“繰り返し目に触れる仕掛け”がカギです。
- 配布物として手渡す(例:入社初日に小冊子で渡す)
- 店内に掲示する(例:バックヤードや更衣室に貼る)
- スタッフMTGで定期的に読み合わせをする
- ルールを守った行動を“見える化”して褒める(例:「今週のGOOD行動」掲示)
とくに大事なのは、「伝えた前提」にしないこと。繰り返し・視覚化・対話で、少しずつ現場に染み込ませましょう。
現場が納得しやすい「ルールの決め方」
一方的に押し付けるルールは、守られません。
現場のスタッフが「自分たちで決めた」と感じるルールこそ、守られるものになります。
- 店長だけで決めず、意見をヒアリングして反映する
- 「なぜこのルールが必要か」を伝えてセットで共有する
- 違反例より“あるべき姿”を一緒に考える(ポジティブルール化)
たとえば、「スマホ禁止」ではなく「接客中はお客様に集中しようね」と伝える。
納得感とストーリーを添えることで、ルールが“自分ごと化”されます。
定期見直しで「使われるルール」に育てる
一度決めたルールも、現場の変化に応じて育てていく必要があります。
むしろ「更新されないルール」こそが、形骸化の一番の原因です。
- 年1〜2回は“現場で使われているか”の棚卸しをする
- 現場の声を集めて「変える勇気」も持つ
- 見直し時に“変更理由”も説明することで納得感UP
スタッフが「このルール、もう形だけじゃない?」と感じ始めたら要注意。
“守られるルール”は、現場と一緒にアップデートされ続ける仕組みが必要です。
まとめ|ハウスルールは“現場を守る仕組み”。まずは1つ決めてみよう
ハウスルールは、スタッフを縛るものではありません。
むしろ、「安心して働ける」「気持ちよくチームで動ける」ための共通語です。
無断欠勤、接客のズレ、言った言わないのトラブル……。
現場でよくある悩みのほとんどは、“最初にルールで決めておけば避けられた”ことばかり。
すべてを一気に整える必要はありません。
まずはひとつ、現場でよく起きる困りごとにルールをつけてみる——そこから始めてみませんか?
ハウスルールの基礎について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
今日からできる“第一歩”のルール作成例
「とはいえ、何から手をつければ…?」という方に向けて、すぐに取り組めるルール例を紹介します。
- 【出勤連絡】遅刻・欠勤の連絡は必ず◯時間前までに電話で
- 【制服・身だしなみ】勤務中は髪をまとめ、エプロンは清潔なものを着用
- 【接客】入店時は3秒以内に「いらっしゃいませ!」と笑顔で声がけ
- 【シフト】毎月20日までに希望提出、変更はLINEでなく口頭で確認
1つ書き出すことで、「あれも必要かも」「ここが曖昧だった」と気づきが広がります。
まずはA4用紙1枚に“うちの当たり前”をまとめることから、始めてみましょう。
Bay3の支援サービス|“現場目線”で一緒にルールをつくるお手伝いをします
「うちの店でもハウスルールを作りたい。でも、どこから手をつければいいのか分からない」
——そんな方にこそ、私たちBay3の出番です。
代表自身、かつて大手外食チェーンで1000名以上の組織をマネジメントし、現場の苦労も楽しさも知り尽くしてきました。
「人が辞めない飲食店」には、共通する“仕組み”があります。そしてそれは、誰でもつくれるものです。
Bay3株式会社では、飲食店の現場目線に立ったルールづくりや仕組み化を、以下のような形で支援しています。
- 現場でそのまま使える「ハウスルールテンプレート」無料DL
- 貴社の状況に合わせたルール設計やマニュアル化の個別相談(初回無料)
- 定着率・採用効率を高めるための評価制度や経営計画との連動支援
さらに、私たちは「おにぎり事業」を通じて日本の食文化と“ひとつぶの価値”も伝える活動をしています。
おにぎりがひとつぶの米でできているように、組織も一人ひとりの積み重ねでできている。
その力を最大限に活かすのが、ルール=仕組みだと考えています。
「現場がうまく回るお店にしたい」「スタッフが辞めない環境をつくりたい」
そんな思いを持つ方は、ぜひ一度ご相談ください。
▶ 【初回無料】貴社専用ルール設計の個別相談・壁打ち受付中!
現場を知っているからこそ、“机上の空論”では終わらせません。
Bay3と一緒に、“続くお店”の仕組み、つくりませんか?