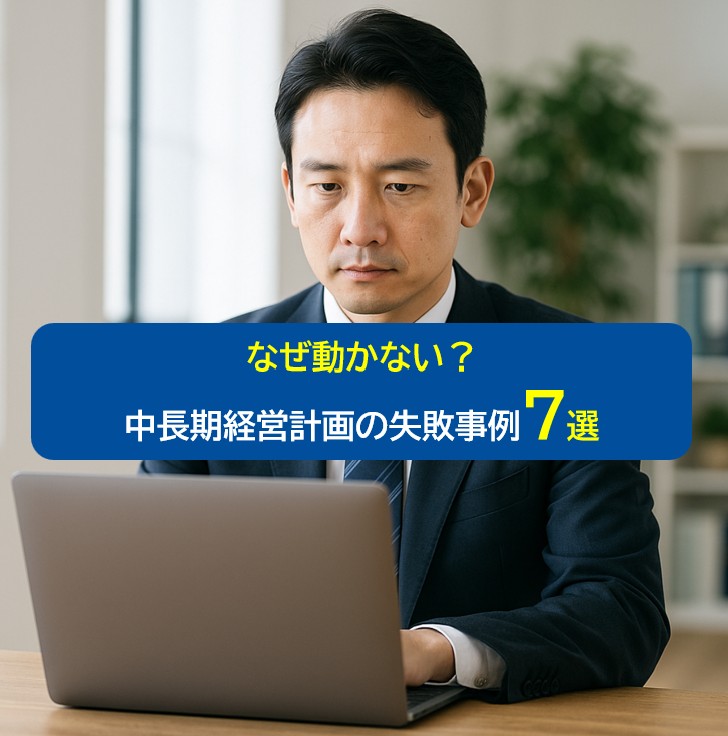「ちゃんと中長期の計画は立てているはずなのに、なぜか社員が動かない」
「作ったけど、1年経って振り返ってすらいない」
そんな“中小企業あるある”の中長期経営計画、思い当たる節はありませんか?
この記事では、中長期経営計画が“絵に描いた餅”になってしまう中小企業の失敗あるあるを7つ厳選して紹介します。
さらに、「なぜ失敗するのか?」「どうすれば“動く計画”になるのか?」まで、フランクにわかりやすく解説していきます。
「うちも同じ状況かも…」と感じた方は、ぜひ最後まで読んでください。
Bay3オリジナルの無料テンプレートと、個別相談の案内もご用意しています!
よくある失敗パターン7選|その計画、動かない理由はコレかも?
① 経営者だけで作って、現場が知らない
中長期経営計画が、経営者と一部の役員だけで完結しているケースは非常に多いです。
「現場に話してないけど、なんとなく伝わってるでしょ」という空気感が漂っている会社は要注意。
〇 現場の声が入っていないので、実態とズレた内容になりがち
〇 いざ実行段階になると、「聞いてない」「なんでやるの?」と反発を受けやすい
〇 結果として“誰のための計画なのか”が曖昧になる
実行部隊を置き去りにした計画は、当然ながら動きません。
巻き込む設計を初期段階から持つことが重要です。
② 目標が抽象的すぎて行動に落とせない
「お客様に信頼される会社になる」
「地域No.1の組織を目指す」
…これ、目標になっているようで“何をすればいいか”が全くわかりません。
〇 行動に落とせない=現場は何もできない
〇 目標の解釈がバラバラで、ズレた動きが起きやすい
〇 結果、「頑張った感」は出るが成果に結びつかない
中小企業こそ、目標は「抽象→具体→数値」に落とし込む仕組みが必要です。
H3:③ 数字(KPI)がない or 見直されていない
数字がない計画は、進捗の確認もできません。
逆に数字があっても“設定しただけで放置”している会社も失敗の温床です。
〇 「できてるのか、できてないのか」が判断できない
〇 数値にコミットしないから、危機感も生まれない
〇 見直さないまま1年が過ぎ、気づいたときには手遅れ
KPIは“見るための数字”ではなく、“動かすための数字”。
月次でチェックし、修正しながら使うことが大前提です。
④ 計画と評価制度がバラバラ
「中期経営計画では“挑戦”って言ってるのに、評価では“ミスが少ない人”が高得点」
こういった矛盾、実はかなりの中小企業で起きています。
〇 現場は「言ってることとやってることが違う」と混乱する
〇 挑戦しない社員が残り、挑戦する社員は去っていく
〇 中期計画が“かけ声”で終わってしまう
計画と人事制度・評価制度は連動して初めて本気になります。
Bay3ではここも一括でサポートしている理由がまさにこれです。
⑤ 計画が長文資料で、誰も読み返さない
Wordで30ページ超の経営計画書。
作成者以外、誰も読みません。断言できます。
〇 情報が多すぎて“どこが重要なのか”がわからない
〇 そもそも読み方のレクチャーもされていない
〇 「形だけ整えて、運用されない」の典型例に
“見せる”ための資料ではなく、“使う”ための資料を意識する必要があります。
PowerPointやスライド形式で、視覚的に伝える工夫をしましょう。
⑥ 月次の進捗レビューがない=やりっぱなし
計画って「作ったら終わり」ではなく、「育てていくもの」。
なのに、見直すタイミングがなく1年放置されるパターン、非常に多いです。
〇 やりっぱなしになると、社員も“やらなくていい”と認識する
〇 目標と現実のギャップを把握できず、対策も立てられない
〇 気づいたときには、全くズレた方向に走っていることも
月1回の中計レビュー会を“仕組み”として入れるだけで、劇的に改善されます。
⑦ 社員が「なぜこれをやるのか?」を理解していない
最後にして最大のポイントがこれ。
社員の“納得感”がない計画は、どんなに精緻でも動きません。
〇 「上から言われたからやる」は長続きしない
〇 自分ごとになっていないから、創意工夫が生まれない
〇 「とりあえずやってる」レベルから抜け出せない
「なぜこの目標が必要なのか」「自分の仕事にどうつながるのか」
そこまで伝えて初めて、計画は動き出します。
失敗の根本原因は“運用設計”がないことだった
「作って満足」の罠にハマる経営者の心理
中長期経営計画をつくると、なぜか「仕事をやりきった感」に包まれる経営者は少なくありません。
ですが、それはあくまで“スタートライン”。本当の勝負は「どう動かすか」です。
〇 「計画をつくること自体」が目的化してしまっている
〇 社内共有や進捗管理の導線が設計されていない
〇 結果、現場にはほとんど浸透せずに終わってしまう
中計を「経営陣だけの成果物」にせず、全社で運用できる体制を作らないと、作る意味すらなくなってしまいます。
行動まで落とせない“ふわっとKPI”の危険性
「売上アップ」「顧客満足度向上」「組織力の強化」——よくあるKPIですが、これだけでは現場は動けません。
重要なのは“行動に落とせるKPI”かどうか、です。
〇 抽象的すぎて、日々の業務にどうつながるかが不明
〇 「で、結局何すればいいの?」が現場の本音
〇 行動との接点がないため、進捗レビューも曖昧になる
例えば「売上目標」なら「1人当たり訪問数◯件/週」「成約率◯%」のように、日常の業務単位に落とす視点が欠かせません。
日々の業務に追われて“計画が消える”構造的欠陥
実際のところ、中小企業はリソースも少なく、日々の業務で手一杯。
だからこそ、「計画なんて見てる暇ないよ」という空気が現場に蔓延しがちです。
〇 目の前の納期・顧客対応・トラブル対応が最優先に
〇 経営計画は“机上の空論”扱いで放置されがち
〇 忙しくなるほど、中計の存在感が薄れていく悪循環
ここで必要なのは「業務に組み込む」設計。
たとえば毎月の定例会でKPIレビューを行う、会議資料に目標進捗を必ず入れるなど、“計画を日常化する工夫”が鍵になります。
「動く計画」に変えるための3つの視点
ここでは概要を解説しますが、より具体的な設計方法や進め方については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
→ 現場が動く中期経営計画の立て方|具体ステップと成功のコツ
① 経営理念・ビジョンを“現場語”に落とし込む
中長期経営計画は、経営理念やビジョンから逆算してつくられるもの。
でも、そのままの言葉で現場に伝えても、ほぼ確実に伝わりません。
〇 「社会に貢献する企業へ」→「だから、毎日の接客でどんな工夫をする?」
〇 「未来のマーケットを創る」→「今の業務で、どこを変えるべき?」
というように、現場の行動に変換された“現場語”で落とし込む必要があります。
理念やビジョンは掲げるだけでなく、「現場に浸透させてナンボ」です。
② アクションプラン×KPI×レビュー体制の設計
計画を動かすうえでの三種の神器がこちら。
「やること(アクションプラン)」「測ること(KPI)」「振り返ること(レビュー体制)」です。
〇 行動指針がないと、何から手をつけていいかわからない
〇 数値目標がなければ進捗の判断ができない
〇 振り返る機会がなければ、やりっぱなしで終わる
この3つが回り始めて初めて、「計画→実行→改善」というサイクルが回ります。
どれか1つでも欠けると、“動かない中計”に逆戻りです。
③ 社員が“納得して動ける”状態をつくる仕掛け
最後のカギは、社員が「自分ごと」として計画を捉えられるかどうか。
「やらされ感」で動く組織では、どんなに立派な中期計画でも形骸化します。
〇 目標の背景や意義をきちんと伝える
〇 意見を反映させて“共につくる”意識を持たせる
〇 「頑張ってるのに報われない」をなくす評価制度にする
この“納得感”があるだけで、社員の行動スピードも質も変わります。
だからこそ、巻き込み型で計画を設計・実行することが必要不可欠です。
【支援事例】Bay3が手がけた「動かなかった計画」の逆転ストーリー
評価制度と中計を連動し、社員が自走し始めたA社
A社では、立派な中長期計画が存在していたものの、社員の動きには全くつながっていませんでした。
原因は「評価制度との連動がゼロ」だったこと。
Bay3が支援に入ったのは、以下のポイントでした:
〇 中計のKPIを、評価制度にそのまま反映
〇 「頑張り=評価される」仕組みに切り替え
〇 現場に合った定性・定量指標を再設計
結果、社員が“自分の頑張りが数字に直結する”と実感できるようになり、計画が一気に自走モードへ。
「数字を追う=会社の目標達成につながる」実感が浸透しました。
タスクベース設計で管理部門の成果も可視化したB社
B社はバックオフィス部門が多く、営業ほど明確な数値目標が立てられない状況に悩んでいました。
「中計の中に管理部門の行動目標をどう落とし込めばいいのか?」が課題でした。
Bay3の支援内容はこうです:
〇 タスクポイント制度を導入し、業務量と質を数値化
〇 部門ごとの中期目標と日々の行動を“見える化”
〇 評価制度とセットで運用開始
管理部門でも「何をすれば貢献できるか」が明確になり、役割意識とやりがいが一気にアップ。
「中計=営業部門だけのもの」という誤解も払拭されました。
月1のレビューと会議設計で“やりきる文化”が根付いたC社
C社では、中計をつくっても「作りっぱなし・振り返らない・放置される」の三重苦。
そこでBay3は“運用”そのものを設計しなおしました。
〇 毎月のKPIレビューMTGを定例化
〇 進捗を点検するシートを役職者と共有
〇 会議体設計から支援し、「会議が動く場」に進化
この仕組みによって、「何が遅れているか」「なぜ進まないか」が毎月クリアに。
「計画は運用してこそ意味がある」という意識が社内に根付き、今では社員の口から“進捗”という言葉が自然と出るように。
まとめ|“動かない計画”には必ず理由がある
失敗事例に学べば、打ち手は見えてくる
中長期経営計画がうまくいかない会社には、共通する落とし穴があります。
まずは「中期経営計画とは何か」「どんな目的でどう活用するべきか」という基本をしっかり押さえることが、成功の第一歩です。
基礎を理解した上で、この後ご紹介する“動く計画”づくりに進んでいきましょう。
「作っただけで終わる」「現場に届かない」「数字も行動も動かない」──
そんな“あるある”を潰すだけでも、計画はグッと前進します。
〇 「現場を巻き込む設計になっているか?」
〇 「定期的に進捗を見直す仕組みがあるか?」
〇 「社員が“自分ごと化”できているか?」
この視点を持てば、失敗からの学びがそのまま“次の一手”になります。
形だけじゃない、“実行される中計”をつくるには
カギになるのは「運用まで見据えた計画設計」です。
どんなに優れた戦略も、現場で動かなければ意味がありません。
〇 KPIとアクションを連動させる
〇 評価制度・会議体・コミュニケーションとセットで設計する
〇 経営者と社員が、同じゴールに向かって動ける状態をつくる
Bay3では、計画づくりだけでなく、“動く組織”を実現するための伴走支援を行っています。
絵に描いた餅にしない――それが私たちの中計づくりです。
まずはテンプレと無料相談から始めてみませんか?
なお、「中期経営計画書をどう書けばよいのか?」を詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
「動かない計画を、動かせる形に変えたい」
そう思った今が、最初の一歩です。
〇 無料で使える“運用前提”のテンプレート
〇 自社に合った設計の壁打ちができる無料相談
〇 専門コンサルタントが、実行までしっかりサポート

「作って終わり」の時代は、もう終わりにしませんか?
まずは名前とメールアドレスで資料請求!
テンプレート資料は、下記フォームから簡単にダウンロード可能です。
〇 入力項目は「メールアドレス」だけ
〇 すぐにBay3よりPDF資料をお届けします
〇 ご希望があれば、相談の日程調整もスムーズに対応可能