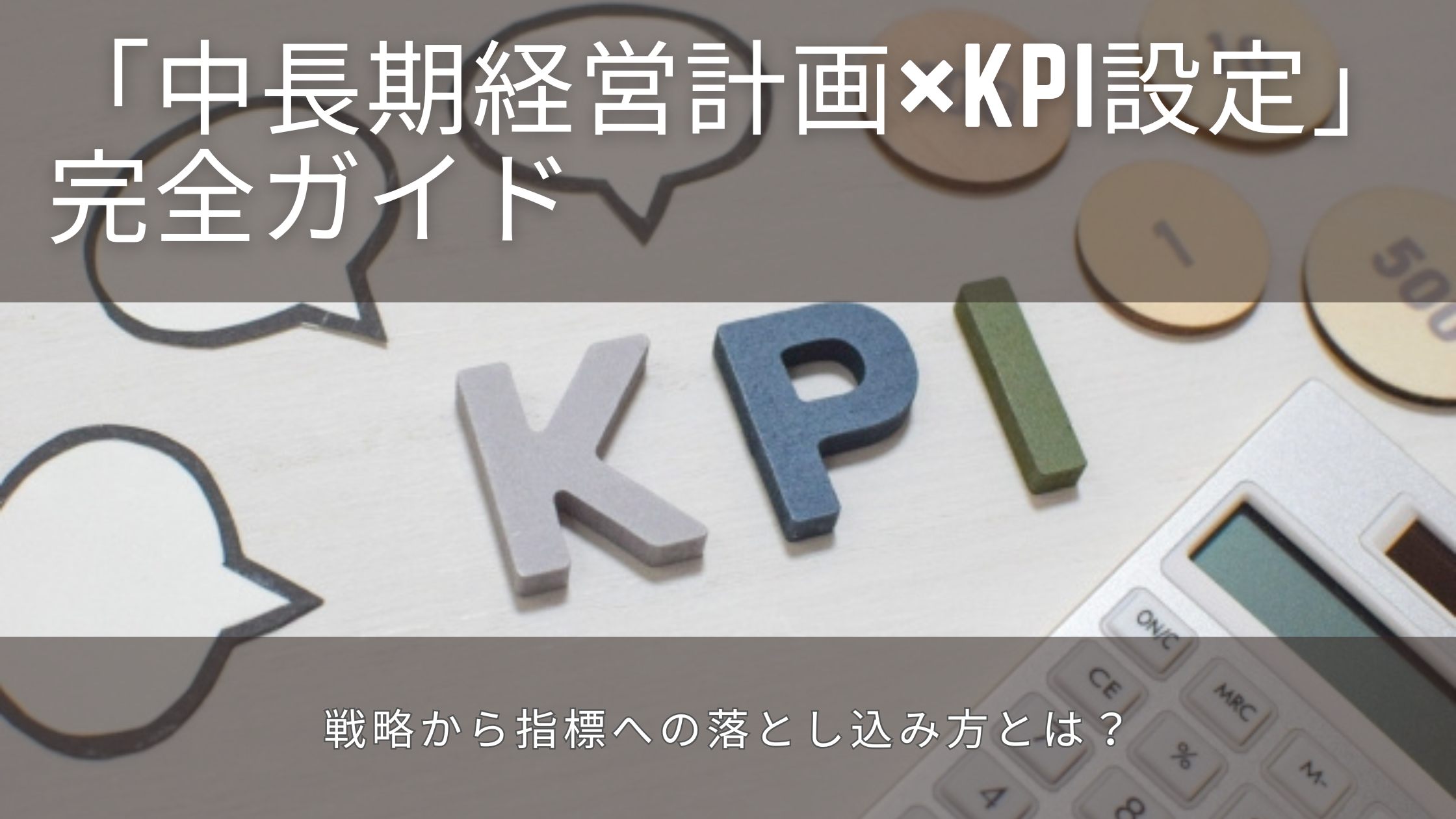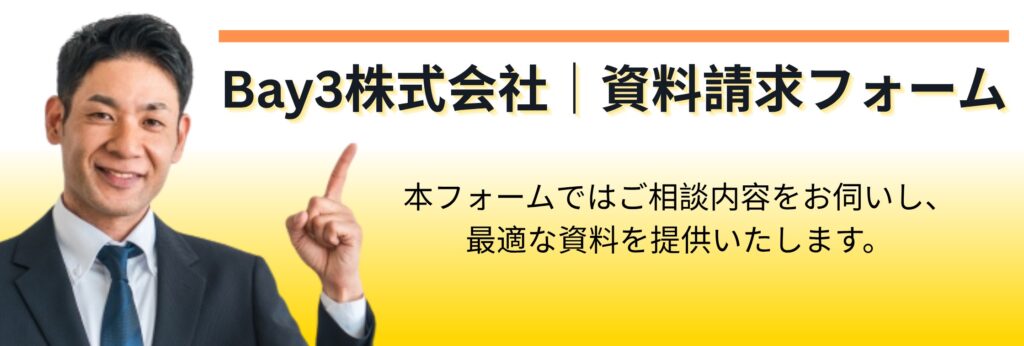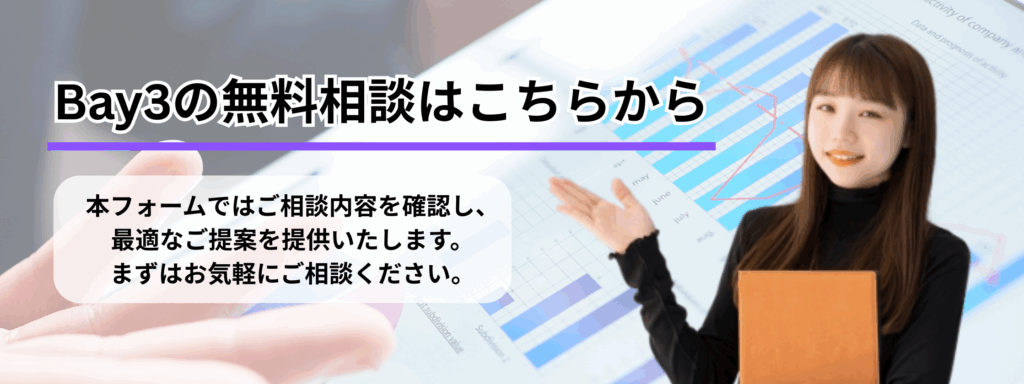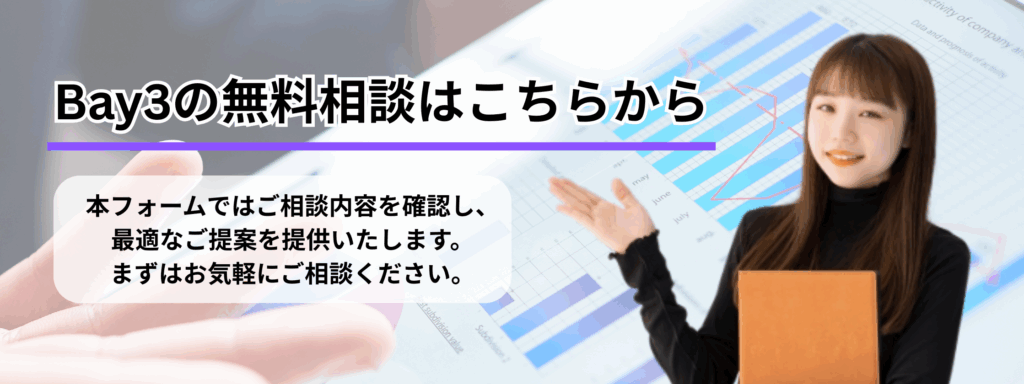「中計はあるけど、現場で何も動いてない気がする…」「KPIは作ったけど、数値管理で終わってる…」
そんな違和感を抱える経営者・管理職の方、多いのではないでしょうか。
せっかく中長期経営計画をつくっても、KPIと連動していなければ絵に描いた餅。逆に、KPIが経営の“指針”として機能すれば、日々の行動が戦略とつながり、組織が前に進みます。
本記事では、
- 「KPIが形骸化する原因」
- 「KPIと中計の正しいつなげ方」
- 「戦略からKPIまでのブレイクダウン設計」
- 「現場で“動く計画”を作る方法と事例」
を現場目線で解説します。
「そろそろ“ちゃんとした中計”を作りたい」
「KPIがバラバラで困っている」
「上場や開示対応に向けて整備したい」
そんな方に向けた、実践型の完全ガイドです!
なぜ今「中長期経営計画」と「KPI設定」が注目されているのか
経営者やマネージャーから「中計つくったけど、誰も見てない」「KPI決めたのに、現場がピンときていない」という声をよく聞きます。
でもそれ、あなただけではありません。いま多くの企業が“中計とKPIのズレ”という同じ壁にぶつかっています。
では、なぜこのタイミングで「中長期経営計画」と「KPI設定」が再注目されているのか?
その背景にあるリアルな経営課題から紐解いていきましょう。
背景にある経営課題:目標があっても実行されない理由
「ビジョンも数値目標も掲げた。でも、社内が動かない」。
この現象には、いくつかの共通パターンがあります。
- 数字やスローガンが抽象的で、現場に落とし込めていない
- 目標の“意味”や“背景”が社員に伝わっていない
- KPIと日々の業務がリンクしておらず、動機づけにつながらない
つまり、「戦略と実行」の間に設計の断絶があるんです。
このギャップを埋めない限り、いくら中計を整えても、机上の空論に終わってしまいます。
形骸化する中計・KPIに共通する落とし穴とは
よくあるのが、以下のような“あるある落とし穴”。
- 毎年フォーマットを埋めて終わる「中計テンプレ病」
- 他社を真似して作った「うちには合わないKPI」
- 部門ごとに指標がバラバラで、全体像が見えない状態
- 数字だけで管理し、行動・習慣・仕組みが伴っていない
これらに共通するのは、「KPIが目的化している」こと。
KPIはあくまで“行動の方向づけ”であり、「何をどう達成したいのか」を語る戦略ストーリーの一部であるべきなんです。
「戦略と行動をつなぐ設計」が求められている
今の時代、「スピード感ある経営」や「自律的な組織」が求められる中で、
トップダウンで作った中計やKPIだけでは通用しなくなってきました。
必要なのは、以下のような戦略と行動をつなぐ“設計力”です。
- 戦略→中計→KPI→現場アクションという一本の“見える導線”を引く
- 指標が“自分ごと”になるよう、ストーリーや背景もセットで伝える
- KPIが日常の会議・行動・振り返りに自然と組み込まれている
つまり、「伝えるKPI」ではなく、「動くKPI」へ。
これが、今まさに多くの企業が取り組み始めている“脱・形骸化”の本質です。
多くの企業が抱える中長期経営計画の課題については、こちらの記事も参考にすると理解を深められます。
中長期経営計画とKPIの正しい関係性|目的と構造を整理しよう

「KPIがうまく機能していない」と感じたら、まず見直したいのが「中計とのつながり」。
KPI単体で意味を持つのではなく、中長期経営計画(中計)の“分身”として設計されているかどうかが重要です。
ここではまず、中計とKPIの違いを整理しながら、正しい関係性を見ていきましょう。
中計とは何か?短期計画・事業戦略との違い
「中計=数字目標」と思っていませんか?
実はそれ、かなりもったいない中計の使い方です。
中期経営計画とは、簡単に言えば「3〜5年後に自社がどうありたいか」を描く成長ストーリーのこと。
ビジョンと現実のギャップを埋める“橋”として、事業戦略や重点施策を設計します。
- 短期計画:1年スパンの売上・利益・施策目標(手段に近い)
- 中計:3〜5年先の状態を描いた“戦略的地図”
- 事業戦略:競合との違いや、どう勝つかの設計(中計の中核)
つまり中計は、「夢」ではなく「現場につながる未来図」。
この未来図があるからこそ、KPIにも“向かうべき方向性”が宿るのです。
KPIとは何か?KGI・指標・OKRとの違い
「とりあえず売上目標」「稼働率をKPIにした」…それ、本当にKPI?
KPI(Key Performance Indicator)は、日本語にすると「重要業績評価指標」。
ただの数値ではなく、目標に向かって“今”注視すべき行動・成果を可視化するための羅針盤です。
ここで、よく混同される指標も含めて整理しておきます。
- KGI(Key Goal Indicator):最終ゴール(例:売上10億円)
- KPI:KGIに向かうための中間指標(例:月間新規商談数)
- OKR(Objectives and Key Results):目的と成果でチームを動かす枠組み(Googleなどが活用)
KGIだけでは「今、何をすべきか」がわからない。
KPIは、その間を埋めてくれる“今を動かす数字”なんです。
【図解】戦略→中計→KPI→アクションの構造フロー
KPIを設計するには、まず全体構造を押さえるのが先決です。
以下のような流れで、「戦略→行動」までを一本でつなぐことが成功のカギ。
- 経営ビジョン(ありたい姿)
↓ - 中長期戦略(差別化ポイント・重点事業など)
↓ - 中期経営計画(3年後の定量・定性ゴール)
↓ - KGI(最終成果目標)+KPI(達成プロセスの進捗指標)
↓ - アクションプラン(日常の業務・会議・行動)
このフローを意識せずにKPIを作ると、数字が“戦略から浮いた存在”になりがち。
逆に、この流れに沿って設計すれば、KPIが「戦略の翻訳」になり、行動に直結するようになります。
中長期経営計画の具体的な作成手順を知りたい方は、こちらの記事も合わせてご参照ください。
戦略からKPIへ|中長期経営計画を実行可能にする落とし込みステップ
「中計もKPIもあるのに、なぜか進まない」
多くの企業がこの悩みにぶつかっています。その理由はシンプルで、戦略が現場の行動に“落ちていない”から。
ここでは、「戦略→中計→KPI→現場アクション」へとつなぐ具体的な落とし込みステップを4段階で解説します。
Step1:戦略テーマと成果目標の明確化
まず最初にやるべきは、「うちの勝ち筋はどこか?」をはっきりさせること。
戦略が曖昧なまま数値だけ追っても、現場は動けません。
- どの領域に集中するのか(例:新規開拓?既存深耕?人材育成?)
- 何をもって成果とみなすのか(売上?件数?満足度?)
- それは3〜5年後、どんなインパクトをもたらすのか?
この「戦略テーマ×成果目標」のペアが、全ての指標設計の起点になります。
とくに中小・ベンチャー企業ほど、「選ばない戦略」は命取りになりやすいので要注意です。
Step2:KPIの設計ポイント(指標/レンジ/現場との接続)
次にKPIを設計していきますが、ここでやりがちなのが「なんとなく作った指標」問題。
KPIは“測れば変わる行動”であるべきで、ただの数値では意味がありません。
設計時のポイントは以下の通り:
- 指標の種類:成果型(結果)かプロセス型(行動)かを明確にする
- 目標値のレンジ設計:1点ではなく、達成率80%・120%など“幅”を持たせて柔軟に
- 現場との接続:そのKPIが「どの行動に変わるのか?」を言語化する
たとえば「商談件数」なら、「週何件アポを入れる必要があるのか」まで落とし込む。
こうすることで、数字が“行動の引き金”になります。
Step3:評価制度・PDCAとの連動で“回る”仕組みに
KPIを作っても、会議で報告するだけでは意味がありません。
本当に大切なのは、“KPIが評価・行動・改善サイクルに組み込まれていること”。
- 評価制度と連動させる:KPI達成度が評価・報酬にリンクしているか?
- 日常会議に組み込む:KPIごとの進捗確認を習慣化する
- 振り返り文化をつくる:数字の上下を“なぜ?”で分析し、次に活かす
KPIが「ただの報告項目」から「組織のエンジン」に変わるには、この連動設計が不可欠です。
Step4:KPI未達時の見直しと再設計プロセス
どんなに綿密に作っても、KPIがうまく機能しないことはあります。
大切なのは、未達だったときに“感情論”で責めるのではなく、仕組みとして見直す姿勢です。
- そもそもKPIが行動に直結していたか?
- 目標値が高すぎたり、逆に甘すぎたりしなかったか?
- 外部環境の変化(市況・人材・顧客動向)に対して柔軟に見直せるか?
定期的にKPIの“健全性”をチェックするサイクルを設けておくと、数字に振り回されず、「自分たちで調整できる経営」が実現できます。
中長期経営計画を確実に実行に移すためのステップについては、こちらの記事もご参照いただくと、より具体的に理解が深まります。
成功する企業はここが違う!KPI設定と中長期計画の実践事例
KPIや中計を導入したものの、「数字だけが残り、行動が変わらない…」というケースは多々あります。
逆に、戦略・指標・現場の動きをしっかりつなげた企業は、着実に成果を出しています。
ここでは、実際に成果につながった3つの企業事例を紹介します。
どれも“ありそうな失敗”を乗り越えたリアルなストーリーです。
【事例1】属人的営業から“指標ドリブン”に変えたBtoB企業
あるBtoBメーカーでは、営業担当ごとの力量に大きなバラつきがあり、「属人化から抜け出せない」ことが課題でした。
そこで、以下のようなステップで“指標ドリブン営業”へと転換:
- 中計で「3年後に粗利率を5%改善」という成果目標を設定
- KPIとして「月間アプローチ件数」「初回商談→見積率」「失注理由の分類率」を導入
- 各KPIがCRMに自動反映され、日報文化を撤廃して「数字と行動が同期」する仕組みに
- 週次の営業会議で、数値変化をもとに“行動そのもの”を改善対象にした
結果、営業の属人性が減り、「なぜ売れた/なぜ失注した」が見える営業組織へと進化。
数字で語る文化が根付き、マネジメントの納得度も大きく向上しました。
【事例2】現場KPI×人事制度で離職率を改善したサービス企業
全国展開のサービス業では、「定着率の低さ」「拠点長の感覚マネジメント」が悩みの種。
そこで取り組んだのが、中計と評価制度を連動させたKPI設計でした。
- 中期計画の重点テーマに「人材の定着と育成」を明記
- KPIとして「入社3ヶ月定着率」「面談実施率」「育成計画の提出率」を導入
- これらKPIを管理職評価に反映する設計に変更(≠売上至上)
- 現場での「感覚ベースの育成→仕組みベース」への転換を図った
半年後には、離職率が前年比で▲15%を記録。
何より、「KPIが“育成の後押し”になる」と現場からも声があがり、自律的に育成が回る組織文化が生まれつつあります。
【事例3】投資家への開示を見据えた中計ストーリー設計
とある上場準備中のベンチャー企業では、「中計は出したが、投資家に刺さらない」と悩んでいました。
そこで着目したのが、「数値の整合性」ではなく、「ストーリーとしての一貫性」。
- まずは“ビジョン→戦略→KPI”のつながりを図解+文章で明示
- 各KPIがどのフェーズで改善されるかをタイムライン形式で整理
- リスクと仮説の前提条件も開示資料に記載し、質問対応の質を向上
- 「このKPIがこうなれば、売上がこう伸びる」ロジックを一本化
結果として、VCとの面談でも「納得感がある」「経営陣の意思が伝わる」と評価され、資金調達の成約スピードが加速しました。
↓「成功する中長期計画作成」のための無料相談も行っています
よくある課題とその乗り越え方|中計・KPI運用の“あるある”と処方箋

「ちゃんと作ったはずなのに、KPIが回らない」「中計を誰も見てない」──
これ、珍しい話ではなく、多くの企業が陥る“中計・KPI運用の落とし穴”です。
ここでは、よくある3つのつまずきパターンとその対処法を紹介します。
現場でも経営でも使える、リアルな処方箋を用意しました。
【課題1】KPIが“数字の羅列”になっている
「KPIはこれとこれとこれ…」と、とりあえず数値を並べたけど、結局どこを見ればいいかわからない。
こんな“KPI迷子”状態、けっこうありがちです。
このパターンの問題点:
- 指標が多すぎて、優先度がつかめない
- 目的や背景が説明されておらず、意味が伝わらない
- 結果指標ばかりで、行動につながらない
【処方箋】
KPIを“絞って、意味をつけて、行動に落とす”ことが大事です。
- 重点テーマごとに「最重要KPIは1つ」に絞る
- 「なぜその数字を見るのか?」をセットで伝える
- 結果だけでなく、プロセス指標(例:面談実施率、対応速度など)も組み込む
数字はあくまで会話のきっかけ。「何をどう変えるか?」まで言葉にすることが肝です。
【課題2】現場が他人事で、KPIが機能しない
KPIを決めたのに、現場が無反応…。「また数字だけ決められた」と思われていませんか?
このパターンでよくあるのは:
- KPIが“経営層だけの話”になっている
- 指標が日々の業務と関係なく、実感がない
- KPIに触れる機会が少なく、記憶にも残らない
【処方箋】
KPIを“自分ごと”にするために、以下を実践しましょう。
- KPI設計に現場の声を取り入れる(ワークショップ形式など)
- 「この数字が上がると何が変わるか?」をストーリーで共有する
- 朝礼・会議・評価など“日常”にKPIを埋め込む
KPIは掲示するものではなく、「使うもの」。
現場の行動や選択を後押しする“道しるべ”にすることがポイントです。
【課題3】環境変化に弱く、修正できない中計
環境が変わったのに、中計がそのまま。気づけば“陳腐化した未来図”になっていませんか?
よくあるパターン:
- コロナや法改正、競合の台頭などを織り込めていない
- KPIが変化に対して硬直的で、柔軟に動けない
- “計画を守ること”が目的になってしまっている
【処方箋】
中長期計画だからこそ、“変化を前提とした柔軟設計”が必要です。
- 年1回ではなく、四半期ごとのKPIレビュータイミングを設定
- 「修正=失敗」ではなく、「更新=適応」と再定義する
- シナリオプランニング的に、リスクや外部変化をあらかじめ組み込む
「見直せる計画=動かせる組織」。
硬直的な中計ほど、時代に置いていかれるスピードは速いです。
どうすれば「現場で動く」計画とKPIになるのか
では最終的に、どうすれば“机上の計画”を“動く計画”にできるのか?
Bay3が現場でよく使う視点はこちら:
- KPIは「行動」と「感情」で設計する
→ 数字だけでなく、現場がどう感じるかまで考慮する - 「合意形成」→「習慣化」→「制度化」の3ステップで定着させる
→ 初めはワークショップ、次に定例化、最後は評価と連動 - KPI設計そのものが“対話のきっかけ”になる
→ 上から与えるのでなく、現場とつくるプロセスに価値がある
数値ではなく、「誰が」「なぜ」「何のために」このKPIを追うのか。
そこまで設計できて、ようやくKPIは生きた“行動設計図”になります。
まとめ|中長期経営計画×KPIを成功に導くために大切なこと

中期経営計画とKPI設定は、どちらも「経営の地図」と「現在地」を示すツールです。
でも、どれだけ精緻につくっても、それが“実行”されなければ意味がありません。
最後に、KPIと中計を本当に「動くもの」にするための視点をまとめておきます。
「実行される設計図」をつくる視点を忘れない
KPIや中計がうまくいかない多くのケースは、“設計図が現場で使われていない”という点に集約されます。
- 作ることが目的になっていないか?
- 設計が複雑すぎて、現場が理解できていないのでは?
- 現実の変化に合わせて、見直せる柔軟さはあるか?
「伝えるための資料」ではなく、「動かすための設計図」。
この視点を常に持ち続けることが、形骸化を防ぐ最大のポイントです。
自社に合ったKPIを設計し、現場で回すために
他社事例を参考にするのは大切ですが、そのまま真似するだけでは機能しません。
本当に必要なのは、「自社にとって意味があるKPI」を選ぶこと。
- 数字を“現場の行動”に変換できる指標か?
- 現場が納得できる背景や文脈があるか?
- 評価制度・会議体・日々の行動とつながっているか?
「売上」「稼働率」「顧客数」といった一般的なKPIも、文脈次第で刺さり方は変わります。
“自分たちの言葉”で語れるKPIをつくることが鍵です。
まずはできるところから、小さく試してみよう
中期経営計画やKPI設計というと、「一気に全社導入しなきゃ」と構えてしまいがちですが、
最初から完璧を目指す必要はありません。
- まずは1部署、1テーマだけで試してみる
- 現場の反応を見ながら、指標や伝え方を調整する
- 成功例が出たら、そこから横展開していく
KPIも中計も、“走りながら育てていく”ほうがうまくいきます。
まずは小さく始めて、実感を得ることが最大の突破口です。
▶無料テンプレート・相談はこちら
「中期経営計画やKPIを作ってみたいけど、何から始めればいいかわからない」
そんな方に向けて、すぐに使えるテンプレート&無料相談をご用意しています。
- KPI設計の思考整理ワークシート
- 中計ストーリーの構成テンプレート
- 現場への落とし込み方のガイド付き
\まずは“自社に合った設計”を一緒に考えてみませんか?/