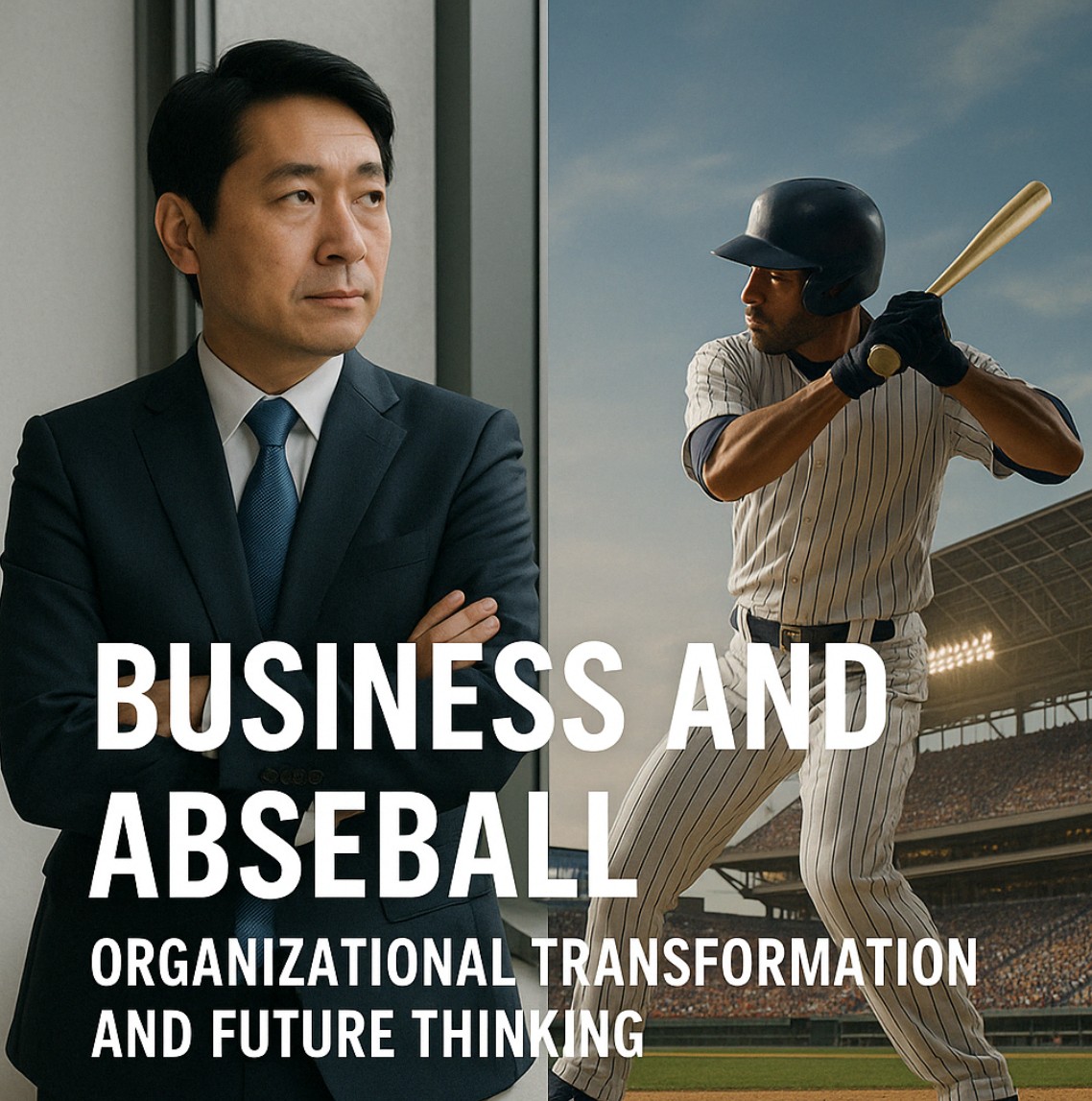この記事は、2025年4月20日の日経新聞の記事を基に作成しました。
2025年3月、東京ドームの異変
東京ドームにできた異例の大行列。日本人メジャーリーガーの凱旋に、全国からファンが押し寄せる光景は、かつてのプロ野球人気を彷彿とさせました。
しかし、4月20日付の日本経済新聞では、こうした熱狂をあえて冷静に見つめ直す視点が紹介されています。
この30年、日本のプロ野球は世界との競争にどう向き合ってきたのか?
「変われなかった理由」は“組織文化”にあった
記事では、日本のプロ野球が直面する構造的課題として、以下の点が指摘されていました。
- サークル内で安心して完結する意思決定
- 世界の潮流(マーケティング・データ活用)への対応の遅れ
- ファン目線ではなく、球団目線のまま変化しきれなかった
- 海外と比べた圧倒的な収益構造の差
たとえば、米メジャーリーグでは主力選手の平均年俸が約7〜8億円超。
一方、日本のプロ野球では1軍選手の平均年俸は約4,800万円と、大きな差があります。
この収入格差は、今後さらに拡がる可能性も指摘されています。
これは、企業経営にも通じる話
Bay3では、中小企業の中期経営計画づくりを支援していますが、
プロ野球界の課題は、多くの企業が抱える構造と驚くほど似ています。
- 社内の常識で意思決定が完結してしまう
- 外部環境の変化に、本気で向き合うタイミングを先送りにしている
- 「このままでいい」という同調圧力に支配され、新しい挑戦が起きない
その結果、市場の変化に乗り遅れ、気づけば“成長できない体質”になってしまっている。
これは、決してプロ野球だけの話ではありません。
仲間内のルールを見直すタイミング
記事では、こんな一文も印象的でした。
「ピンチをチャンスに変えるには、“仲間内のルール”を見直すことから始めるべきだ」
これはまさに、中期経営計画の原点でもあります。
中計とは、単なる数字目標ではありません。
「3年後、自社はどんな姿でありたいか?」という未来像を描き、
その実現のために、「今のやり方や常識をどう変えるか?」を問い直すプロセスなのです。
「3年後、どんな会社でありたいか?」という未来の姿を描き、
それを実現するために「今の組織や常識をどう変えるか?」を考える時間です。
“サークルを超える”勇気が未来を変える
プロ野球が今、変革を迫られているように、
多くの企業にも「変化への対応力」が問われています。
もちろん、変わることは怖い。
けれど、「変えないこと」のリスクの方が、もっと大きいのです。
Bay3は、経営者の皆さんとともに、
「理想の未来」から逆算して、“変化のシナリオ”を描くお手伝いをしています。
組織の“変化対応力”が未来を分ける
中小企業の多くが、こうした課題を抱えています:
- 日々の業務に追われ、本質的な変革に手が回らない
- 成功体験に縛られ、新しいチャレンジが生まれにくい
- 経営情報が共有されず、未来を語る人が限られている
このような“閉じたサークル”を乗り越えるには、
外部とつながり、変化を受け入れる勇気が必要ではないでしょうか。
Bay3の視点:ピンチをチャンスに変えるために
「ピンチはチャンス」——これは経営でも同じです。
多くの中小企業が、人口減・原価高騰・人材難という“構造的ピンチ”に直面しています。
そんな中で、問われているのはただ一つ:
あなたの会社は、どう変わろうとしているのか?
- 中期経営計画をつくってみる
- 若手と未来を語る機会を増やす
- 外部の知見やデジタルの力を取り入れてみる
仮に社内に“大谷翔平のようなスター人材”がいたとしても、
その人が力を発揮できる環境が整っていなければ、価値は育ちません。
まとめ:閉じた「サークル」から一歩踏み出そう
プロ野球の事例から私たちが学べるのは、
“変化し続ける組織”だけが、ファンや人材から選ばれ続けるということです。
Bay3は、これからも経営者の皆さんとともに、
「変わりたい」という想いに伴走し、未来をつくるパートナーであり続けます。
本記事では、「変化に向き合う企業のあり方」について、プロ野球界の事例をもとにご紹介しました。
もし御社でも、組織づくり・育成環境・中期経営計画の策定に関して感じていることがあれば、
ぜひ率直なご意見をお聞かせください。
匿名でのご相談も受け付けております。
まずは一歩、変化に向けた声を聞かせていただければ幸いです。