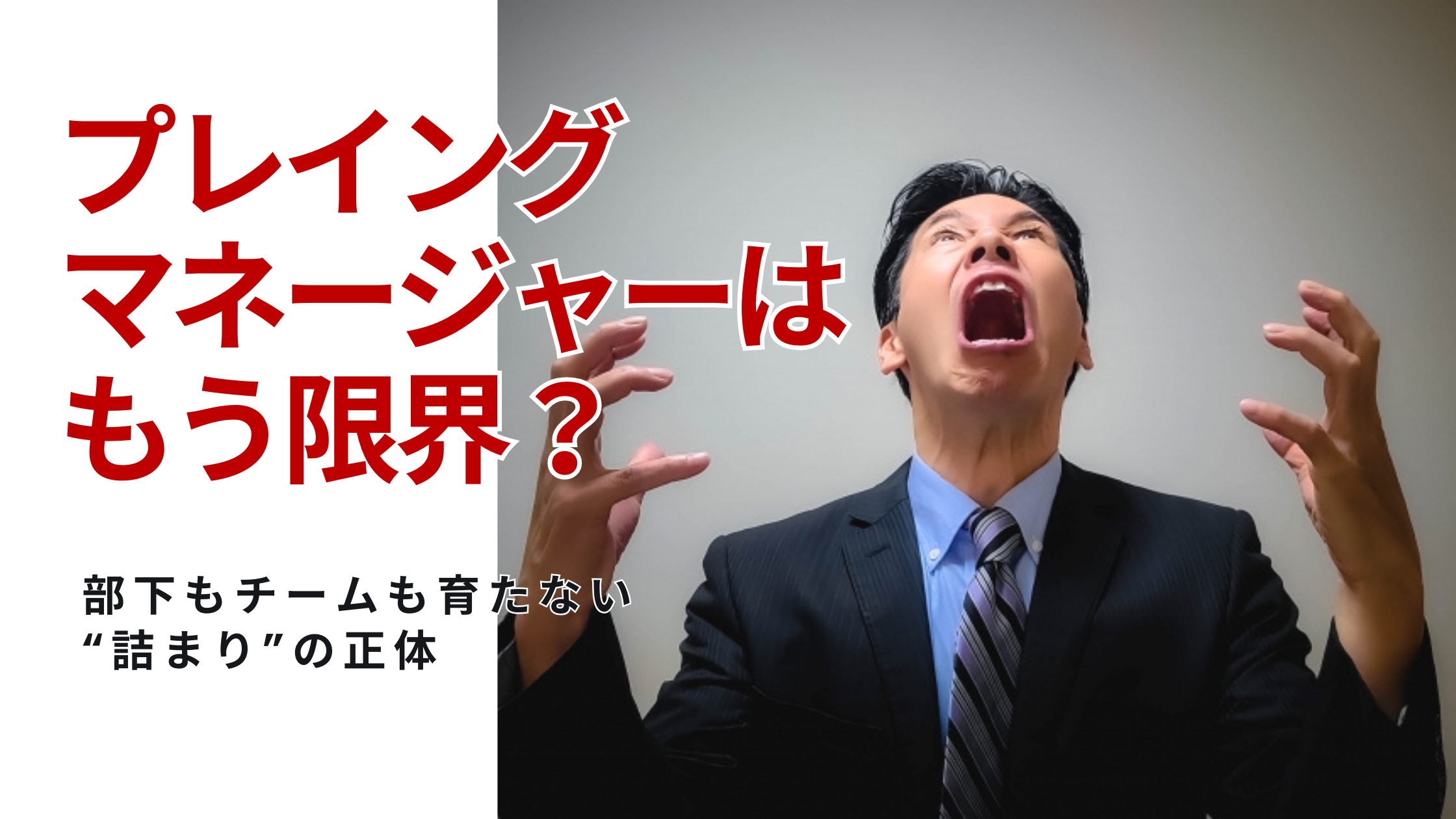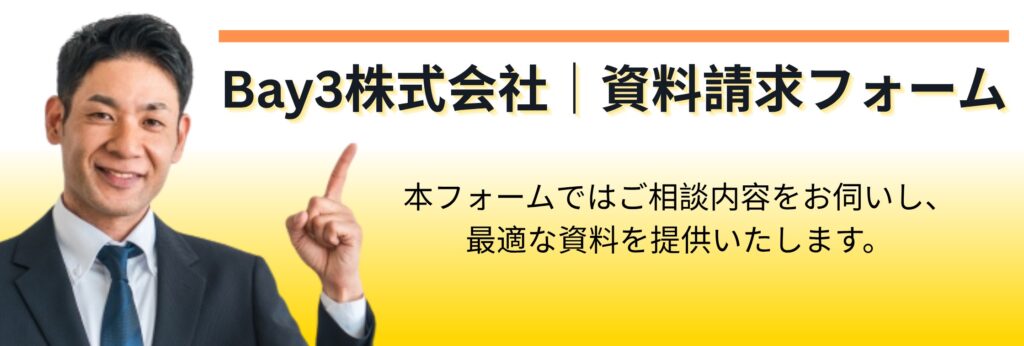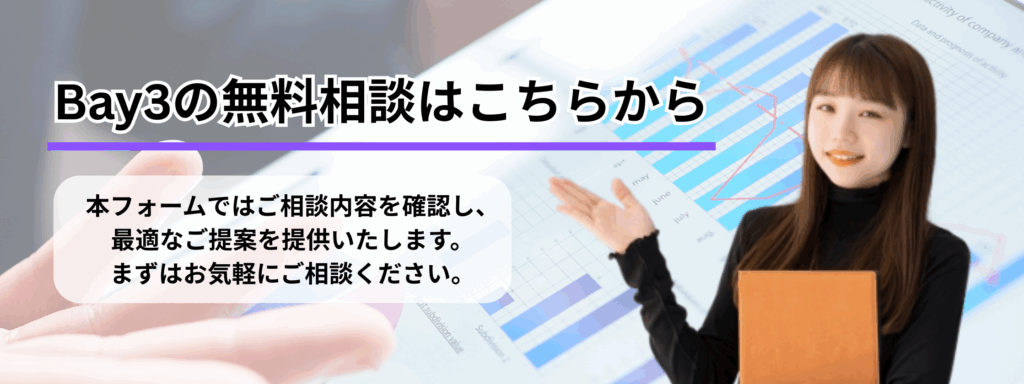「プレイヤーとしても、マネージャーとしても、100点を求められている気がする」 「気づけば、チームのボトルネックは自分になっていた」 そんな“詰まり”を感じているプレイングマネージャーの声は、今や珍しくありません。
片方では「現場を動かしてくれ」と言われ、もう片方では「部下を育てて成果を出せ」と求められる。 その結果、残業は増え、判断も遅れ、チームの成長は止まってしまう。
本記事では、プレイングマネージャーの限界が叫ばれる背景と、現場・組織が抱える課題を整理。 「育つチーム」に変えるための現実的なヒントとアプローチを、具体事例とともにお届けします。
なぜ今「プレイングマネージャー体制」が限界を迎えているのか
プレイングマネージャーは、現場とマネジメントの両方を担う“要”の存在。 一見すると理想的な体制に思えますが、実はこの構造こそが、組織の“詰まり”を生む温床になっています。
限界が叫ばれる背景には、「期待値の高さ」と「構造的な無理」が存在します。 ここではまず、プレイングマネージャーの役割と矛盾、そして制度としてのほころびを見ていきましょう。
プレイングマネージャーとは?役割の理想と現実
プレイングマネージャーとは、プレイヤー(実務者)として業務をこなしながら、マネージャー(管理者)としてチームを牽引する存在です。
理想としては以下のような状態が求められています:
- 自ら手を動かして成果を出しつつ
- 部下の育成・評価・マネジメントを行い
- チーム全体のアウトプットを最大化すること
しかし現実には、
- 業務量が多く、マネジメントの時間が確保できない
- 部下との1on1や育成は“後回し”になりがち
- 成果が属人化し、チーム力が伸びない
というように、「プレイもマネジメントも中途半端になってしまう」ジレンマに苦しむ声が後を絶ちません。
プレイヤー業務とマネジメント業務、両立の“矛盾”
プレイヤー業務とは「短期的に結果を出す仕事」。 マネジメント業務とは「中長期的に人とチームを育てる仕事」。
この2つを同時に担うプレイングマネージャーは、常に以下のような矛盾と戦っています:
- 今すぐ数字を作れと言われるが、部下育成の時間は取れない
- 会議・報告・目標管理など“管理業務”も降ってくる
- 結局、プレイヤーとして自分が頑張るしかなくなる
結果として、「チームを見渡す時間も余裕もない」「育てるより、自分がやった方が早い」という悪循環に陥り、メンバーの成長が止まります。
「指示も実務も自分だけ」になりがちな構造的課題
問題は、個人のスキルではなく「構造」にあります。
プレイングマネージャー体制には、以下のような根本的な課題があります:
- 権限や役割分担があいまいで、すべての矢印が1人に集中する
- プレイヤーとしての成果は見えやすく、マネジメントの評価が曖昧
- プレイをやめると「仕事していない」と思われる文化が根強い
こうした環境では、誰も「マネジメント専念」ができず、プレイヤーとしての忙しさに飲み込まれていきます。
特に中小企業では、人数や層の少なさから「プレイング前提の組織設計」になっているケースが多く、制度や評価の設計から見直す必要が出てきます。
プレイングマネージャーの負担を軽減し、組織全体の力を高めるには、こちらの記事も参考になるでしょう。
現場で起きている“詰まり”の正体
プレイングマネージャー体制の限界が表面化すると、まず現場に“詰まり”が発生します。 業務が止まり、判断が滞り、チームのパフォーマンスがじわじわと落ちていく。 その根底には、「一人の詰まり=チーム全体の停滞」という構造的なリスクが潜んでいます。
「自分が詰まる=チームも止まる」負のループ
プレイングマネージャーが抱える仕事は、以下の通り山盛りです。
- 自分の数値目標の達成
- 部下の育成と1on1・フィードバック
- チームの進捗管理と報告資料の作成
- トラブル対応や現場のフォロー
この中でどれか1つでも滞ると、他もすぐに連鎖的に崩れていきます。
例えば「今週はプレイヤー業務が詰まった」となると…
- 部下へのフォローや相談対応が後回しになる
- メンバーが不安になり、自律的に動けなくなる
- マネージャー自身がさらに手を動かさざるを得なくなる
- 結果としてまた詰まる…
というように、“自分が詰まった瞬間にチームが止まる”状態が常態化してしまいます。
属人化・育たない部下・疲弊する管理職の実態
この負のループが続くと、以下のような問題が起こります。
- 部下の仕事が細分化されず、マネージャーだけが全体を見ている
- トラブル対応がすべて管理職に集中する
- 育成の余裕がなく、メンバーが“指示待ち”化していく
- 組織が育たず、何かあるたびに「マネージャー頼み」になる
結果、マネージャーは常にキャパオーバー。 「疲れているのに休めない」「辞めたくても辞められない」状態に追い込まれ、精神的にも肉体的にも疲弊します。
特に中小・ベンチャー企業では、業務の引き継ぎが属人化しがちで、「あの人がいないと回らない」という状況が慢性化しやすいのです。
「チームの成果が上がらない」その背景にあるもの
プレイングマネージャー本人は一生懸命プレイしているのに、なぜか「チームの成果が出ない」。 その原因は、マネジメント不全だけではありません。
- メンバーの目標や役割が不明確
- チームとしての戦略が存在しない
- 各自がバラバラに動いていて“足し算”になっていない
つまり、“チーム”として動けていないのです。
本来マネージャーが設計すべき「方向性の共有」「役割分担」「意思決定の支援」が抜け落ち、プレイ優先の毎日に流されていく。 気づけば、組織の生産性も士気も下がっている――。 そんな悪循環に、あなたの現場も陥っていないでしょうか?
「限界」を招く組織構造とマネジメントの壁
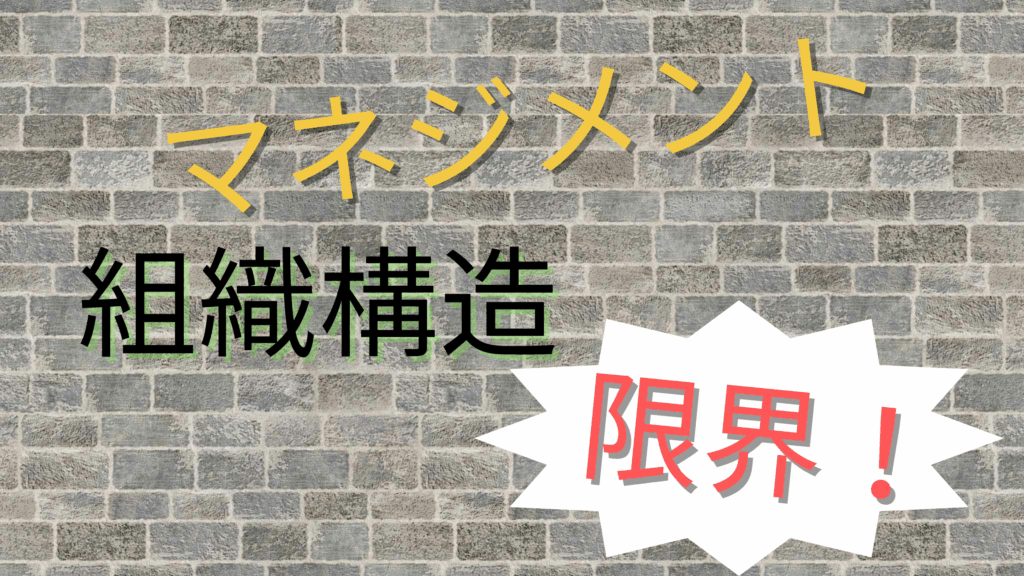
プレイングマネージャーが疲弊し、成果もチーム力も上がらない背景には、個人の問題ではなく「組織構造」に原因があるケースが多くあります。 中小・ベンチャー企業で特に多く見られる“プレイング体制の限界”を引き起こす壁をひも解いていきましょう。
なぜ中小・ベンチャーでプレイング型が多いのか
「まだ人数が少ないから」「現場を知っている人に任せたいから」 そうしてプレイングマネージャー体制が生まれた会社は少なくありません。
- そもそもマネジメント専任の余力がない
- 人材育成よりも“今の売上”が最優先
- 経営層と現場が近く、暗黙知が多い
こうした環境では、「とりあえずできる人が全部やる」体制になりがちです。
しかし人数が増えたり、事業が拡大したりすると、個人プレイでは限界が来る。 そのタイミングで「仕組み」がないことが、大きなボトルネックになります。
評価・役割定義・分業が曖昧な組織のリスク
プレイングマネージャーが抱えるフラストレーションの多くは、「役割があいまい」「評価されない」ことにあります。
- 自分だけやたら仕事が多いのに、給与は変わらない
- チームの成果を上げても、誰の手柄かわからない
- マネジメントの頑張りが“見えない”ため評価されにくい
- 部下にも何を任せていいかわからず、結局自分がやる
こうした状態が続くと、「自分ばかり損している」「何のためにやっているのか分からない」と感じるようになります。
マネジメントが曖昧なまま“気合いと根性”で乗り切ろうとすると、いつか限界がきてしまうのは当然です。
経営と現場の期待ズレがもたらす“板挟み構造”
プレイングマネージャーが最も苦しむのが、「上と下の両方から期待される」こと。 たとえばこんな状態、思い当たりませんか?
- 経営からは「メンバーを育てて自走させてほしい」と言われる
- 現場からは「忙しいから、マネージャーも手を動かして」と求められる
- 自分が手を動かすと「育成ができてない」と言われ、育成に時間をかけると「プレイが足りない」と言われる
この「どちらの期待にも応えられない」状態が、マネージャーを消耗させ、離職の引き金にもなります。
本来は役割と権限を明確に定義し、上位者が支援・評価を整えるべきところ。 それが設計されていないまま、“現場力”に頼ってしまうことが、限界を生む最大の構造要因といえるでしょう。
👉 Bay3では”詰まり”の正体解明、解消に向けた無料相談も行っています。
どうすれば抜け出せる?限界突破のアプローチ
「プレイングマネージャーはもう限界」──。 そう感じたときに必要なのは、“がんばり続ける”ことではなく、「役割の再定義」と「仕組みの見直し」です。
ここでは、個人でできる工夫から組織的な支援まで、具体的な打ち手を紹介します。
業務分解と“やらないこと”の明確化
最初に取り組むべきは、「何でも屋」状態からの脱却です。 そのために効果的なのが、業務の“棚卸し”と“やらないことリスト”の作成。
- 自分がやっている業務を書き出し、所要時間・重要度・代替可能性を整理
- 「自分がやらなくてもいい」業務をピックアップ
- 本当に時間を使うべき「マネジメント業務」「意思決定業務」に集中できるようにする
やるべきことを増やす前に、“引き算”をすること。 これが、余白を生み、チームに目が向けられる最初の一歩です。
「育てる・任せる」チームマネジメントへの転換
プレイングマネージャーが限界を突破するには、「成果を自分で出す」から「成果が出る仕組みを育てる」へとマインドを切り替える必要があります。
- 小さな業務からでも、メンバーに任せてみる
- 任せる前に“判断基準”や“完了の定義”を共有する
- 結果だけでなく、プロセスを見てフィードバックする
- 「育てる」時間をスケジュールに組み込む(あと回しにしない)
育成・任せることは、手間がかかります。でもそれを避け続けると、ずっと「自分が詰まる」構造のままです。 自走するメンバーが増えることで、最終的には自分の負担も大きく減っていきます。
制度・仕組み・評価の再設計で現場を支える
最後に必要なのが、マネージャーの努力を「個人の頑張り」で終わらせないための、組織的な支援です。
- 「マネジメントの成果」も評価に反映される仕組みをつくる
- プレイとマネジメントをバランスよく担えるよう、役割を明確にする
- チーム単位の目標・KPI・会議体を整え、“チームで動く”構造に
- 育成や引き継ぎの仕組みを整え、属人化を防ぐ
マネージャーが疲弊してから「なんとかしなきゃ」と動くのでは遅いのです。 経営・人事側が「仕組みで支える」「頑張りを見える化する」ことが、持続可能なマネジメントを実現する鍵となります。
マネジメントを仕組み化し、組織全体の成果を最大化する具体的な方法は、こちらで詳しく解説しています。
実践企業の事例に学ぶ、体制転換のリアル

【事例1】営業部門|“売れる課長”が抜けた途端に業績が落ちたチーム
状況・背景|「数字を持ちながらチームを見る」限界に直面
BtoB向けIT企業で、営業課長が4名の部下を率いていた。彼はチーム内で圧倒的な実績を誇り、重要な商談はほぼすべて自ら担当。部下は「同行すれば正解が得られる」という依存状態になり、育成や判断力の強化は後回しになっていた。 ところがある日、課長が体調を崩して1ヶ月の休職に入った。すると、チームの売上は50%以上落ち込み、現場では「◯◯さんがいないと仕事が回らない」と混乱が広がった。
取り組み・施策|マネージャーの役割を“育てる”にシフト
- KPIを個人単位からチーム単位に切り替え、メンバー全員が成果に責任を持つ体制へ
- 毎週の育成ミーティングで、部下の課題や支援方針を言語化・共有
- 評価制度に「育成指標(同行件数・フィードバック回数・成約サポート率など)」を組み込み、マネジメントも正当に評価
また、メンバーにも「ひとり1商談の主担当」制度を導入。成功・失敗を問わず、商談を自ら進めることで当事者意識を育てた。
結果|チーム売上は3ヶ月で回復。課長の残業時間も大幅削減
チームは属人構造から脱却し、部下たちも自走するようになった。課長自身も「自分で売る」役割から「売れる人を育てる」役割へシフト。残業時間は月60時間から20時間に減少し、「やっと休めるようになった」と本人も安堵している。
【事例2】エンジニア組織|“万能リーダー”の属人化がチームの成長を止めていた
状況・背景|「技術も人も任せる相手がいない」状態
社員30名のスタートアップで、開発チームのマネージャーは元CTO経験者。要件定義から設計、実装、レビュー、新人教育まで、すべてを自分で担っていた。「自分でやったほうが早い」との思いから任せる文化は育たず、部下は裁量も責任もない状態に。 その結果、若手の離職が続き、チームの開発スピードも低下。マネージャー自身も「時間がない」「考える余裕がない」と疲弊していた。
取り組み・施策|育成と分業前提の“役割再設計”を実施
- 業務棚卸しを実施し、「やらないこと」を明確化(例:レビュー頻度の見直し、教育はOJT担当制へ)
- プロジェクトごとに「技術責任者」と「育成担当」を設定し、マネージャーの関与を段階的に削減
- 評価制度に「育成貢献」「スキル伝承」「プロジェクト完遂力」などの項目を追加
さらに、マネージャーのKPIも「技術成果」から「チームのアウトプット最大化」へと見直し、育成への注力を促進した。
結果|半年でリーダー層が3名育成され、開発速度も向上
知見の属人化が解消され、レビューや技術相談も複数人で対応可能に。若手の定着率も上がり、「すべて自分でやる」体制から脱却できた。マネージャーは中長期の技術設計に注力できるようになり、「仕組みで回る実感がある」と語っている。
【事例3】人事制度改革でプレイングマネージャー支援を強化した製造業
状況・背景|「現場に任せたが、育っていない」中間管理職の疲弊
従業員100名規模の中堅製造業では、多くの現場リーダーがプレイングマネージャーとして実務とマネジメントを兼任。しかし、昇格後の研修や支援制度はなく、育成や改善活動も現場任せ。評価も曖昧で、がんばりが報われない構造が蔓延していた。 その結果、離職が続出。「若手が育たない→ベテランが抜けられない→さらに疲弊」という負のサイクルが深刻化していた。
取り組み・施策|マネジメント支援を“制度ごと”見直し
- 評価制度を刷新し、「現場管理」「育成支援」「改善提案」などを定量・定性の両面で明文化
- プレイングマネージャー向けに、マネジメント研修や業務棚卸ワークショップを実施
- 任せる文化を育てるため、サブリーダー制度とOJTガイドラインを導入
とくに「実務だけで評価されない」点を是正し、「育成」「改善」など組織貢献が評価に直結するよう再設計した。
結果|管理職の離職ゼロ&提案件数が3倍に。育成文化が根付いた
制度改革から1年で、現場からの改善提案数は3倍に増加。育成に関する目標設定も浸透し、マネジメントの質が向上。「役割が明確になった」「部下と向き合う時間が増えた」といった声が現場から相次いだ。属人的な管理から脱却し、定着と自走が実現しつつある。
今回の事例のような人事評価制度の刷新については、こちらの記事も合わせてご参照ください。
まとめ|プレイングマネージャー“卒業”で組織はどう変わる?

「ひとりで抱えない」仕組みが成果と育成を生む
プレイングマネージャーがすべてを抱える体制は、一見すると効率的に見えて、実は大きなリスクをはらんでいます。「あの人がいないと回らない」「若手が育たない」「いつも誰かが疲弊している」——そんな状況を変える鍵は、属人化からの脱却と、チームで成果を出す仕組みづくりです。
育成指標や分業体制、明確な役割定義を整えることで、マネージャー自身も余白を持ち、チーム全体の生産性が上がる好循環が生まれます。
マネージャーを“燃え尽きさせない”経営のあり方
「現場をよく見てくれている人だから」と、なんとなくマネージャーを任せていませんか? 実は、プレイングマネージャー体制が限界を迎えている企業ほど、評価・役割・裁量の設計が曖昧な傾向にあります。頑張っても評価されず、部下は育たず、結果的に現場の責任者が消耗して離職する…それでは本末転倒です。
経営や人事が主導し、「どう支えるか」「どう育てるか」の視点で制度を見直すことが、マネージャーの力を最大化する第一歩になります。
まずはチームの“詰まり”から可視化してみよう
プレイングマネージャー体制がうまくいっていない組織には、共通して「詰まり」が存在します。意思決定の遅れ、役割の不明確さ、任せられない空気…。それらは個人の努力では解消できません。
だからこそ、まずはチームのどこで“詰まり”が起きているのかを可視化し、言語化するところから始めてみてください。属人化の構造を解きほぐせば、組織全体が軽く動き出します。
▶無料相談・診断チェックリストはこちら
プレイングマネージャー体制の見直しや、役割・評価設計に関するお悩みは、専門家への相談が近道です。
以下の無料チェックリストでは、現状の「詰まり」や「限界サイン」が見える化され、次に取るべき一歩がわかります。