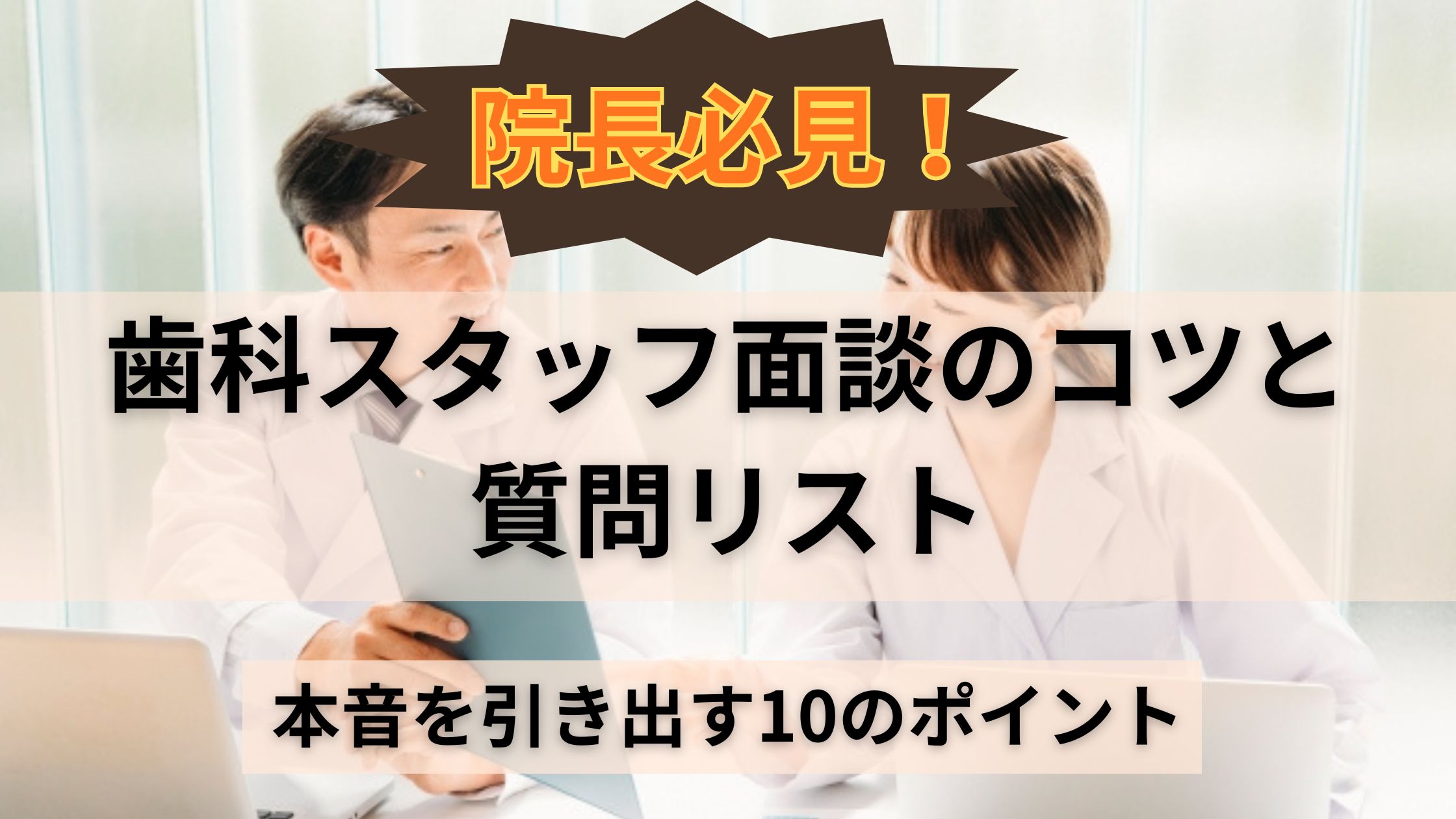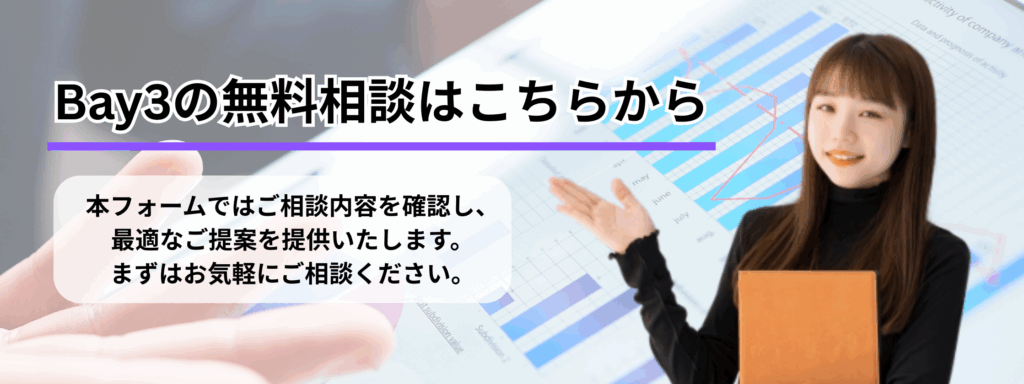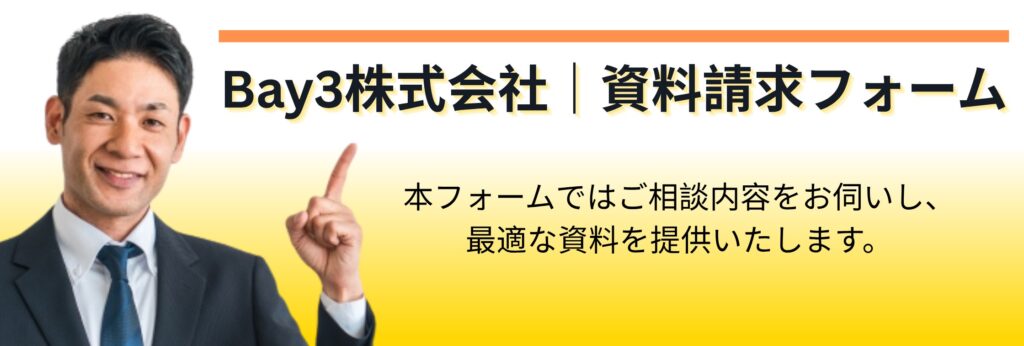「面談をしても本音が出ない」「話が続かない」「形式だけになっている」——そんな悩みを抱える院長へ。
この記事では、歯科医院でのスタッフ面談を“信頼構築と成長支援の時間”に変えるためのコツと質問リストを解説します。
本音を引き出す聞き方、評価とモチベーションを両立させるポイントまで、現場で使える具体例を紹介します。
なぜスタッフ面談がうまくいかないのか?
多くの院長が陥る「3つのNGパターン」
歯科医院での面談がうまく機能しない理由の多くは、やり方そのものにあります。ここでは、現場でよく見られる3つのNGパターンを紹介します。
●①雑談で終わる/目的が曖昧なまま始める
目的を定めずに始めると、話が脱線し、面談の成果が見えなくなります。
「最近どう?」といった雑談から入るのは悪くありませんが、ゴール設定がないと行動につながりません。
→面談の冒頭で「今日は〇〇を目的に話したい」と共有し、テーマを明確にしましょう。
●②一方的に評価を伝えるだけ
「伝えるだけの面談」になっていませんか?
院長が話しすぎると、スタッフが意見を出す余地がなくなり、本音が出ません。
→「あなたはどう感じてる?」と質問を投げかけることで、対話のバランスを整えましょう。
●③改善点ばかりで“承認”が足りない
注意点や課題ばかりを指摘すると、スタッフのやる気が下がります。
まずは「よかった点」「前回より成長した点」を伝えることから始めましょう。
→「褒める→理由→次の課題」の順に伝えると、受け入れやすく、信頼関係も深まります。
面談が機能しない本当の原因とは
表面的なやり方だけを直しても、面談の質は上がりません。根本的な原因は「仕組み」と「関係性」にあります。
●①スタッフが“話しても意味がない”と感じている
せっかく話しても「何も変わらない」と思われてしまうと、本音は出てきません。
→面談の冒頭で「前回話してくれた件、こう変えたよ」と報告し、信頼を積み重ねましょう。
●②面談のルール・頻度が決まっていない
忙しさに流されると、面談が“思いつき”で終わりがち。
→「月1回」「1人30分」「記録を残す」など、実施ルールを定めて継続しましょう。
定期的に行うことで、スタッフの安心感も高まります。
●③院長が“評価者モード”になりすぎている
評価と成長支援を同じ面談でやろうとすると、“査定の時間”になってしまいます。
→成長面談では「評価」ではなく「対話」を重視し、質問の比率を7割にするのが理想です。
面談を成功に導く5つのステップ

歯科スタッフ面談を「何となく行う時間」から、「信頼と成長を生む時間」に変えるには、段階的な設計が欠かせません。
ここでは、どの医院でもすぐ実践できる“5つのステップ”を紹介します。
ステップ①目的を明確にする(信頼構築or評価or成長)
面談を始める前に、まず「何のために話すのか」を明確にしましょう。
信頼構築のためなのか、評価のためなのか、成長支援のためなのかによって、質問の内容もトーンも変わります。
- 信頼構築面談日頃の感謝やモヤモヤの共有
- 評価面談目標達成度や成果を確認
- 成長面談今後の挑戦やキャリアパスを一緒に考える
目的を事前にスタッフへ伝えることで、「今日は何を話す時間か」が明確になり、安心感も生まれます。
ステップ②話しやすい環境を整える(時間・場所・雰囲気)
スタッフが「本音で話せる」環境づくりが、成功する面談のカギです。
診療後の疲れたタイミングや、他のスタッフの目がある場所では、どうしても話が浅くなります。
- 静かで落ち着ける空間(個室・休憩室など)
- 時間は15〜30分を目安に確保
- テーブルをはさんで正面より、斜めに座ると心理的圧が減る
“安心して話せる場”を作ることが、すべての前提です。
ステップ③質問リストを準備しておく(テンプレート化)
面談の質を安定させるためには、質問をテンプレート化しておくのが有効です。
毎回同じ質問項目をベースにすることで、比較や振り返りも容易になります。
おすすめの質問軸は次の3つです。
- 「現状」…今の仕事の状況・課題
- 「感情」…どんな気持ちで働いているか
- 「未来」…これからどう成長したいか
質問リストは“会話の土台”。自由に話を広げられる余白も大切です。
ステップ④フィードバックは“評価”より“承認”を優先
面談を「できていない点の指摘」にしてしまうと、モチベーションが下がってしまいます。
まずは「承認」から始めるのが鉄則です。
- 「〇〇を意識して動いてくれて助かった」
- 「この対応、患者さんにも伝わってたよ」
といった具体的なフィードバックを伝えることで、相手は“見てもらえている”と感じます。
承認から始まる会話は、その後の課題指摘もスムーズになります。
ステップ⑤記録と次回アクションを必ず残す
面談は“やりっぱなし”にせず、記録を残すことが重要です。
内容を見返せる形で残しておくと、次回の面談にもつながりやすくなります。
- 面談シートやExcelで「話した内容」「次回の目標」「フォロー時期」を記録
- 定期的に振り返りを行い、達成できた点を承認
この「見える化」が、成長実感と信頼関係を育てるポイントです。
面談を仕組み化する際は、目標設定と成長支援を連動させることが重要です。
こちらの記事もご活用ください。
\面談が“形だけ”になっていませんか?/
スタッフ面談を「信頼構築と成長支援の時間」に変えるために、Bay3では“現場で定着する面談の仕組み化”を支援しています。
評価制度や教育体制と連動した面談の導入で、離職率を下げ、チーム力を高める医院が続出中。
本音を引き出す「10の質問リスト」【テンプレート付き】
面談の目的が明確でも、質問が曖昧だと深い話にはつながりません。ここでは、歯科スタッフの本音を自然に引き出す10の質問リストを紹介します。そのままテンプレートとして活用できる内容です。
① 最近の仕事でうまくいったことは?
成功体験を話してもらうことで、前向きな雰囲気を作れます。小さな成果でも言語化することで、自信につながります。
② 今、困っていること・悩んでいることは?
課題やストレスを把握することで、早期フォローが可能になります。「今だから話せることある?」と優しく聞くのがコツです。
③ 医院やチームへの要望はある?
現場での気づきを吸い上げることで、改善のヒントが得られます。「こうなったらもっと働きやすいと思う?」と建設的に促しましょう。
④ 成長したい分野や挑戦したいことは?
スタッフのモチベーションを引き出す質問です。「どんなスキルを伸ばしたい?」など、将来の方向性を一緒に考える時間に。
⑤ 上司や同僚との関係で気になる点は?
人間関係の悩みは離職の大きな要因。信頼関係を築くために、「ここだけの話で大丈夫だよ」と前置きを入れると安心して話してもらえます。
⑥ 患者さん対応で感じたこと・改善したいことは?
患者満足度を上げるためのリアルな視点が得られます。「印象に残った患者さんは?」と聞くと、自然に話が広がります。
⑦ 仕事をもっとやりやすくするには何が必要?
現場改善の具体的な意見を引き出せる質問です。「こういうツールがあったら便利」「業務の流れを見直したい」などの声を拾いましょう。
⑧ 医院の方針について思うことは?
経営側の考えとのギャップを確認するチャンスです。「方針で分かりにくいところある?」と柔らかく聞くと率直な意見が出やすくなります。
⑨ 1年前の自分と比べて、成長を感じる点は?
“過去との比較”は自己肯定感を高める効果があります。院長から「確かに成長してるね」と承認を加えると、信頼が深まります。
⑩ 次の面談までに取り組みたいことは?
行動の落とし込みをサポートする質問です。「次はどんなチャレンジをしたい?」と聞いて、具体的な目標に結びつけましょう。
信頼関係を深める“聞き方”のコツ

面談は「話す」より「聞く」時間に価値があります。院長がどんな姿勢で耳を傾けるかで、スタッフの本音の深さが変わります。ここでは、信頼関係を育てる4つの“聞き方のコツ”を紹介します。
“沈黙”を怖がらず、待つ時間を作る
面談中に沈黙が訪れると、多くの院長はつい埋めようと話してしまいます。しかし、その沈黙こそが“本音が出る前の間”です。スタッフが考えている時間を尊重し、「ゆっくりで大丈夫だよ」と促すだけで、思考が整理され、心の奥の言葉が出てきます。
- 「今どう感じた?」と聞いた後は、10秒待ってみる
- メモを取るふりをして“待つ姿勢”を見せる
- “話を引き出す”よりも、“出てくるのを待つ”ことが信頼の第一歩
“共感”と“要約”で安心感を与える
相手の話をただ聞くだけではなく、「受け止めています」というサインを出すことが大切です。共感と要約を意識すると、スタッフは安心してさらに深く話せるようになります。
例:
スタッフ「忙しくて手が回らない日が多くて…」
院長「そう感じるのは無理もないね。今の体制では負担が大きいもんね。」
“評価”ではなく“質問”で導く
面談は評価の場ではなく、成長を導く対話の場です。「できていない理由」を探るより、「どうすれば良くなるか」を一緒に考える姿勢を持ちましょう。
- NG例:「なぜできなかったの?」
- OK例:「次に同じことが起きたら、どう対応したい?」
質問で導くことで、スタッフ自身が考え、成長の実感を持つようになります。「問いかける力」が院長の面談力を大きく左右します。
“できている点”から話を始める
面談冒頭にネガティブな話をすると、スタッフは防御的になりがちです。まずは“できていること”を具体的に伝え、安心感をつくってから課題に触れましょう。
例:
「〇〇さん、最近患者さんへの声かけが丁寧になったね。」
「滅菌作業の流れがすごく安定してる、助かってます。」
面談でモチベーションを上げるための工夫
「問題解決の場」ではなく、「モチベーションを育てる場」として面談を活用することは、離職防止にもつながります。ここでは、スタッフのやる気を引き出す4つの工夫を紹介します。
“承認の言葉”を3倍にする
スタッフが前向きに行動できるかどうかは、“どれだけ承認されているか”で決まります。改善点を1つ伝えるなら、その前後で3つの承認を伝えるのが理想です。
- 「助かった」「ありがとう」「あの対応良かったね」
- “行動”を具体的に褒めることで、再現性が生まれる
承認の積み重ねが、スタッフの自己肯定感と定着率を高めます。
“成長の実感”を一緒に振り返る
スタッフ自身が“できるようになったこと”を自覚できるようサポートしましょう。「前は苦手だったけど、今は自然にできてるね」とフィードバックするだけで、成長を実感できます。
面談では「どんなことができるようになった?」と質問し、“過去との比較”で成長を可視化するのがポイントです。
“次に目指す姿”を一緒に描く
モチベーションを持続させるには、「次にどんな姿を目指すか」を共有することが大切です。一方的に目標を与えるのではなく、“一緒に決める”姿勢が信頼を生みます。
- 「次はどんなスキルを伸ばしたい?」
- 「どんな役割を担えると嬉しい?」
目標設定を共に考えることで、スタッフが自分の成長を“自分事”として捉えるようになります。
評価とフィードバックを切り分ける
評価の話を面談の中心にしてしまうと、スタッフは防御的になり、本音を話さなくなります。そのため、評価と面談を“別の時間軸”で設けるのがおすすめです。
- 面談:感情・成長・方向性の共有
- 評価:数値・成果の確認
この2つを切り分けることで、スタッフは安心して話し、院長も建設的な対話がしやすくなります。これらの工夫を取り入れることで、面談は「管理の時間」から「成長と信頼の時間」に変わります。
スタッフ面談を仕組み化して“定着”させる

面談を継続的に機能させるためには、院長の意識や努力だけでなく、仕組み化が不可欠です。「面談をやる時期がバラバラ」「内容が属人的」という状態では、いずれ形骸化してしまいます。ここでは、面談を医院の文化として定着させるための4つのポイントを紹介します。
面談シート・記録フォーマットを整える
まず重要なのは、「記録が残る」仕組みを整えることです。どんなに良い面談をしても、内容を覚えておくだけでは再現性がありません。
- 話した内容(課題・要望・気づき)
- 承認・改善のフィードバック内容
- 次回までの目標・アクション項目
紙ではなく、Googleスプレッドシートやクラウド管理にすることで、共有・更新が容易になります。「記録が残る=次の面談の質が上がる」ことを意識しましょう。
面談を“業務”としてスケジュール化
「忙しくてできなかった」を防ぐには、面談を業務スケジュールに組み込むことがポイントです。
- 月初の第1週に全スタッフ面談を実施
- 1人15〜30分を固定枠で設定
- 院長のGoogleカレンダーで事前に確保
こうした“予定の見える化”を行うことで、スタッフも「次の面談で話せる」と安心し、信頼関係が深まります。
院長だけでなく、リーダーも面談を担う
全ての面談を院長が行うのは現実的ではありません。むしろ、リーダー層を巻き込むことでチーム全体の主体性が育ちます。
- 院長:方向性やビジョン、成長支援の確認
- リーダー:日常の課題・行動フィードバック
このように役割を分担すると、スタッフ一人ひとりが「見てもらえている」という実感を得られ、定着率が高まります。
評価制度や教育計画に面談結果を連動させる
面談成果を“次の行動”につなげるためには、評価制度や教育体制と連動させることが重要です。面談で出た課題や目標を、研修・OJT・評価項目に反映することで、PDCAが回り始めます。
- 「接遇改善を目標」とした場合、次回研修テーマに設定
- 「リーダーを目指したい」意欲を評価制度に反映
このように面談=人材育成の起点として位置づけると、医院全体が継続的に成長していきます。
面談を継続的に機能させるには、人材育成全体の仕組みが重要です。
こちらの記事で、育成体制の整え方を確認しておきましょう。
成功事例|面談改革で離職率が下がった歯科医院
面談を単なる「評価」から「信頼構築」に変えた医院では、スタッフの定着率や満足度が大きく向上しています。ここでは、実際に成果を出した3つの事例を紹介します。
事例①:面談月1回で定着率が80%→95%に改善
ある医院では、以前まで年2回の形式的な評価面談しか行っていませんでした。スタッフの不満や本音が拾えず、離職率も高止まりしていたのです。
そこで「月1回の面談日」を固定し、信頼ベースの面談を導入しました。
- 「できたこと・頑張ったこと」から話を始める
- 毎回“1つの行動改善”を決めて次回確認
結果、スタッフが安心して意見を言えるようになり、1年で離職率が15%→5%に改善しました。
事例②:本音面談でチーム力が向上し、クレーム減少
別の医院では、「スタッフが意見を言わない」ことが課題でした。院長が“評価中心”の面談から“傾聴中心”に切り替えた結果、チームの雰囲気が大きく変化しました。
- 面談の最初に「感謝している点」を伝える
- 改善点は一緒に原因を探り、責めない姿勢を徹底
これにより、スタッフ同士の連携が強化され、クレーム件数が半減しました。職場の空気が前向きになり、「話しても大丈夫」という安心感がチーム全体に広がりました。
事例③:面談と評価制度を連動させ、生産性UP
最後に紹介する医院では、面談内容を評価制度と連動させたことで、業務効率とモチベーションが同時に向上しました。
- 面談シートの内容を評価シートに反映
- 行動目標を給与テーブルの基準に紐づけ
スタッフが「努力が正当に評価される」と実感できる仕組みが整い、チーム全体の生産性が向上。「評価の納得感があるから頑張れる」という声が多く上がりました。
面談制度だけでなく、人事評価制度から離職率を改善した事例は、こちらの記事でも紹介しています。
まとめ|面談は“管理の時間”ではなく“信頼の時間”
スタッフ面談の本質は、“管理”ではなく“関係構築”です。1回1回の面談が、医院の文化と信頼を育てる投資になります。
本音を引き出すには「質問の質」と「聞く姿勢」が鍵
良い面談とは、「何を聞いたか」よりも「どう聞いたか」。質問の質と、相手を受け止める姿勢が本音を引き出します。形式よりも、1対1の対話を重ねることが信頼の基盤になります。
面談を仕組み化すれば、離職防止と成長支援が両立する
面談をルーティン化し、教育・評価制度と連動させることで、定着と成長の両立が可能になります。継続は信頼をつくり、信頼が成果を生みます。属人的なマネジメントから“仕組み化された育成”への転換が、強い組織の鍵です。
まずは“1対1の10分面談”から始めよう
最初から完璧を目指す必要はありません。1人10分、短時間でも「話を聞く時間」を持つことで、スタッフの心が動きます。そこから信頼が芽生え、医院全体が前向きに変わっていくのです。
面談は「評価」ではなく「対話」。その積み重ねこそが、“辞めない職場”をつくる最大の仕組みです。
\「スタッフの本音を引き出す面談」を仕組み化しませんか?/
「面談をやっても続かない」「信頼関係が築けない」と悩む院長にこそおすすめです。
まずは無料相談で、あなたの医院の課題を“見える化”してみませんか?