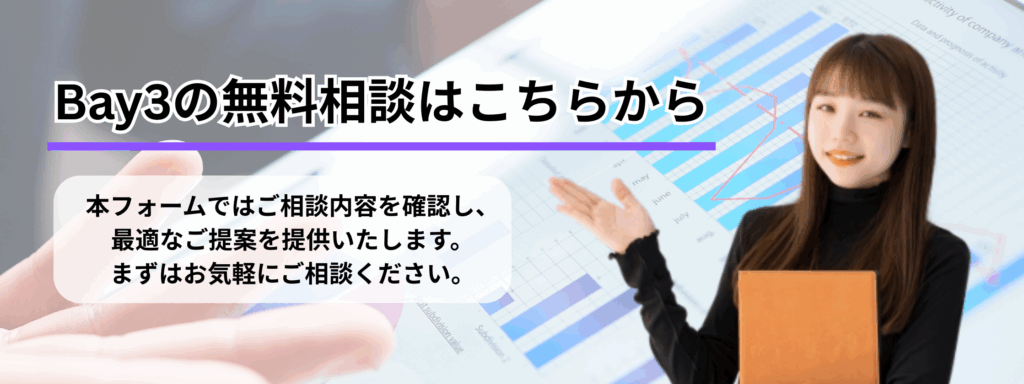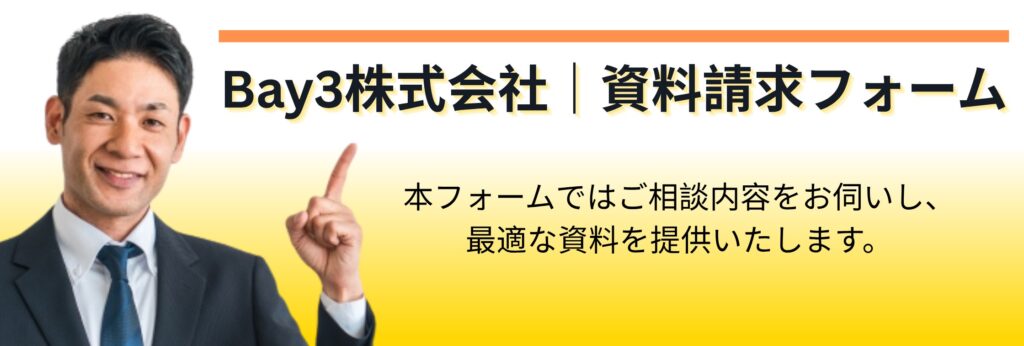人手不足が続く歯科業界。せっかく採用した歯科衛生士が1〜2年で辞めてしまう――そんな悩みを抱える院長は少なくありません。
「給与も悪くない」「教育にも力を入れているのに」と感じているなら、問題は“マネジメントの仕組み”にあるかもしれません。
この記事では、歯科衛生士が辞めてしまうリアルな理由から、離職率を下げる“実行できるマネジメント改革”までを、データと現場の視点で徹底解説します。
なぜ歯科衛生士はすぐ辞めてしまうのか? 離職の理由と院長が知るべき現場のリアル
歯科衛生士の離職は、個人の性格や忍耐力の問題ではなく、職場構造の中に隠れた要因が関係しています。
ここでは、特に1〜2年で辞めるスタッフが多い背景を3つに整理します。
1〜2年で離職する歯科衛生士が多い3つの背景
① 職場の人間関係がストレスの温床になっている
離職理由の約6割に関係していると言われるのが人間関係のトラブル。
小さな不満が積み重なり、次第に「もう続けられない」と感じるケースが多く見られます。
具体的な現場の声としては、
- 「忙しいとき誰も助けてくれない」
- 「先輩の指導がきつい」
- 「院長が特定のスタッフばかり信頼している」
といったものが挙がります。
これらは“個人の性格問題”ではなく、仕組みで防げるマネジメント課題です。
たとえば以下のような取り組みが有効です。
- 明確な役割分担とフォロー体制をつくる
- 感謝を言葉にする文化を定着させる
- 「助け合いルール」や朝礼での共有時間を設定する
人間関係を“偶然の相性”に任せず、仕組みで整えることが離職防止の第一歩です。
② 教育・指導の属人化で成長実感を得られない
教育が人に依存していると、「何を基準に評価されているのか分からない」という不信感につながります。
特に新人や若手は「自分が成長できているか」を実感できないと、早期退職しやすい傾向があります。
改善策としては以下の通りです。
- OJTチェックリストや進捗管理シートを作成
- 教育担当を固定して、フォロー体制を一本化
- 月次面談で「できるようになったこと」を可視化
属人化をなくすだけで、スタッフは「自分は認められている」と感じやすくなります。
成長の“見える化”こそ、離職を防ぐカギです。
③ 院長とスタッフの「想いのズレ」がモチベーション低下を招く
院長が「医院を良くしたい」と思うほど、現場との温度差が生まれやすくなります。
たとえば、
- 院長:「効率を上げて生産性を高めたい」
- スタッフ:「スピードよりも丁寧なケアを大事にしたい」
この“価値観のズレ”が摩擦を生み、スタッフのやる気を奪います。
改善のポイントは「背景をセットで伝える」こと。
- 「売上を上げたい」ではなく「スタッフの待遇を上げたいから売上を伸ばそう」
- 「患者数を増やしたい」ではなく「地域の信頼を得るために発信を強化しよう」
“目的”を共有するだけで、スタッフの受け取り方は大きく変わります。
データで見る歯科衛生士の離職率と業界全体の課題
歯科衛生士の平均勤続年数は約7年。
しかし、20代では3年以内に約4割が退職しているとも言われます。
その背景には、次のような構造的な課題があります。
- 教育体制や評価基準が医院によってまちまち
- キャリアパスが不透明で、先が見えない
- 院長自身がマネジメント研修を受けたことがない
- 女性スタッフのライフステージへの配慮不足
これらの課題を放置すると、「辞める理由」よりも「辞めざるを得ない環境」ができてしまいます。
データから見えるのは、“人が続く医院”には共通したマネジメントの型があるということです。
離職要因の整理には、こちらの記事も併せて参考にしてください。
院長が見落としがちな“離職の理由”とマネジメントの落とし穴
歯科衛生士が辞める原因の多くは、“院長が悪い”のではなく、院長が見えていない構造的な問題にあります。
ここでは、特に定着を阻む3つの落とし穴を見ていきましょう。
原因①:「指示・管理型マネジメント」では人は育たない
多くの院長は「自分が動けば早い」と考え、つい“指示・管理型”になりがちです。
しかし、現代のスタッフは「納得して動きたい」タイプ。
命令ではなく、“共に考える姿勢”が求められます。
たとえば、
- 「早くして」ではなく「患者さんが安心できる対応を意識してみよう」
- 「こうして」ではなく「なぜそれが大事なのか」を伝える
マネジメントは“伝える技術”ではなく、“聴く姿勢”から始まるのです。
院長の言葉ひとつが現場の空気を左右する
同じ言葉でも、トーンやタイミングで伝わり方は180度変わります。
- 「できてないじゃないか」→ 責められたと感じる
- 「次はこうしてみようか」→ 成長を期待されていると感じる
現場の空気は院長の一言で変わる。
“否定”ではなく“促す”言葉を選ぶことが、チームの信頼を築く第一歩です。
原因②:評価制度・キャリアパスが曖昧なまま放置されている
「どこまで頑張れば給与が上がるのか」「昇格基準が分からない」――
これがスタッフの離職理由として非常に多く挙げられます。
以下のような状態は要注意です。
- 評価制度はあるが、運用されていない
- 面談が形骸化している
- キャリアの先が見えない
この状態では、スタッフは不安を感じてしまうだけです。
まずは評価・昇給・キャリアの基準を“見える化”することが大切です。
歯科衛生士が「この先が見えない」と感じる瞬間
- 「リーダーになりたいけど、どうすればいいのか分からない」
- 「自分の評価がどこで決まっているのか知らない」
こうした声が出た時点で、離職のサインです。
等級制度・評価基準・キャリアマップを整備し、
「今どの位置にいるか」「次に何を目指すか」を共有しましょう。
透明性を出すためには、以下記事の5ステップが有効です。
原因③:「感謝」や「承認」が形にならない職場文化
人は「給与」よりも「感情の満足」で動くものです。
どんなに待遇が良くても、「ありがとう」がない職場では長続きしません。
モチベーションは“感情の満足度”で決まる
- 小さな感謝を言葉にする
- 月1回の「感謝ミーティング」を設ける
- スタッフ同士で「ありがとうカード」を送り合う
こうした小さな仕掛けが、チームの空気を温かくし、離職を防ぎます。
文化として“感謝が循環する職場”を作ることが、マネジメント改革の本質です。
離職率を下げるための“マネジメント改革3ステップ”
歯科衛生士の離職率を下げるには、「給与を上げる」だけでは不十分です。
スタッフが安心して働き続けるには、“仕組み・評価・感情”の3方向から整えるマネジメント改革が必要です。
ここでは、すぐに実践できる3つのステップを紹介します。
ステップ①:スタッフの声を“見える化”する仕組みを作る
離職の最大の原因は、「不満を言える場がない」ことです。
多くのスタッフは“辞める理由”を最後まで言わずに退職します。
だからこそ、早い段階で小さな違和感を吸い上げる仕組みが欠かせません。
1on1面談・匿名アンケートで課題を可視化
スタッフの声を「データ」として蓄積するには、以下のような方法が効果的です。
- 1on1面談を月1回実施し、業務だけでなく感情面もヒアリング
- 匿名アンケートで「院長には言えない本音」を集める
- 回答内容を院長・リーダーが共有し、改善アクションを明確化
たとえば、「人間関係の不安」や「教育の偏り」は、1on1で拾えば大きな離職を防げます。
重要なのは、「聞いて終わり」ではなく、“改善までの流れを見せる”ことです。
スタッフは「聞いてもらえた」より、「改善してくれた」ときに信頼を感じます。
ステップ②:教育・評価制度を再構築して“納得感”を生む
離職防止のカギは、スタッフが成長を実感できる環境を整えることです。
「どれだけ頑張っても評価が変わらない」「何を基準に見られているか分からない」
こうした“評価の不透明さ”が、モチベーション低下と離職につながります。
定性×定量のハイブリッド評価で公正さを担保
評価制度は、「数字(定量)」と「姿勢・協働(定性)」の両面から整えるのが理想です。
評価の仕組み例:
- 定量評価:診療アシスト数、スケーリング件数、患者満足度など
- 定性評価:チーム貢献、報連相、後輩育成などを5段階でスコア化
- 総合評価:定量・定性を合算し、昇給・表彰・キャリアパスに反映
こうした仕組みを導入すると、「なぜ自分が評価されたのか」が明確になります。
結果、納得感と公平感が生まれ、「辞めたい」が「もっと頑張りたい」に変わります。
ステップ③:感謝と役割を伝える「承認文化」をつくる
どんなに制度を整えても、「ありがとう」がない職場では人は続きません。
マネジメントの最終目的は、スタッフが“自分の存在意義を感じられる環境”を作ることです。
小さな成功を言葉にして伝える仕組みを日常化
承認文化を育てるには、「仕組み」として日常に組み込むのがコツです。
例えば、以下のような取り組みが効果的です。
- 朝礼で「昨日のありがとう」を1人ずつ伝える
- “Good Jobノート”を設置し、感謝を書いて共有
- 週1回の“フィードバックタイム”でポジティブコメントを出し合う
小さな承認が積み重なることで、「院長に認められている」「仲間に必要とされている」と感じるスタッフが増えます。
人は給与ではなく、“承認”で定着する――これがマネジメント改革の核心です。
制度を整える前に、“今どこでつまずいているのか”を把握することが第一歩です。
👉 無料で診断してみる(1分で完了)
院長ができる“女性が続けられる職場づくり”3ステップ

現在、歯科衛生士の約99%は女性。
そのため、ライフステージの変化に対応できる職場づくりが、離職率低下の大きなカギを握ります。
ここでは「女性が安心して働き続けられる環境」をつくるための3ステップを紹介します。
ステップ①:女性スタッフの声を“聴く場”を定期的に設ける
女性スタッフは、仕事よりも「人間関係」や「働きやすさ」に敏感です。
院長が定期的に声を聴くことで、離職を未然に防げます。
「匿名アンケート」「個別ヒアリング」で本音を引き出す
効果的なのは、“安全に本音を話せる場”を作ることです。
例えば次のような方法があります。
- 匿名アンケートで不満や提案を自由記述できるようにする
- 個別ヒアリングで「困っていること」を1人ずつ確認
- 意見共有ミーティングで、改善点をチームで話し合う
「院長が聞いてくれる」という信頼が生まれれば、スタッフは安心して続けられます。
ステップ②:ライフステージの変化に柔軟な「勤務体系」がある
女性スタッフにとって、“長く続けられるかどうか”は働き方の柔軟性で決まります。
固定勤務や長時間労働のままでは、結婚・出産・育児期に退職が増えるのは当然です。
産休・育休・週休2.5日制やシフト柔軟化など現場実例を紹介
最近では、以下のような取り組みを行う歯科医院が増えています。
- 週休2.5日制・時短勤務制度を導入し、家庭と両立をサポート
- 育休復帰支援制度で、復職後の業務量を段階的に調整
- フレックスタイム制や曜日固定勤務でライフスタイルに合わせた働き方を実現
こうした柔軟な制度があるだけで、「ここなら続けられる」と感じるスタッフが増加します。
ステップ③:女性リーダーを育成し、“共感型マネジメント”を根付かせる
離職防止のためには、「院長だけがマネジメントする体制」からの脱却が不可欠です。
現場の悩みを最も理解できるのは、同じ立場で働く女性スタッフだからです。
リーダーが女性スタッフのロールモデルになる
共感型マネジメントを根付かせるために、次のような仕組みを整えましょう。
- 女性リーダーに教育担当・面談担当を任せる
- リーダー研修でフィードバック・承認スキルを強化
- キャリアパス制度に「リーダー職」を明記し、目標を見せる
「私もこの先、あの先輩みたいになれる」――
そう思える“ロールモデル”の存在が、最も強力な定着力になります。
給与を“辞める理由”ではなく“続ける理由”に変える方法
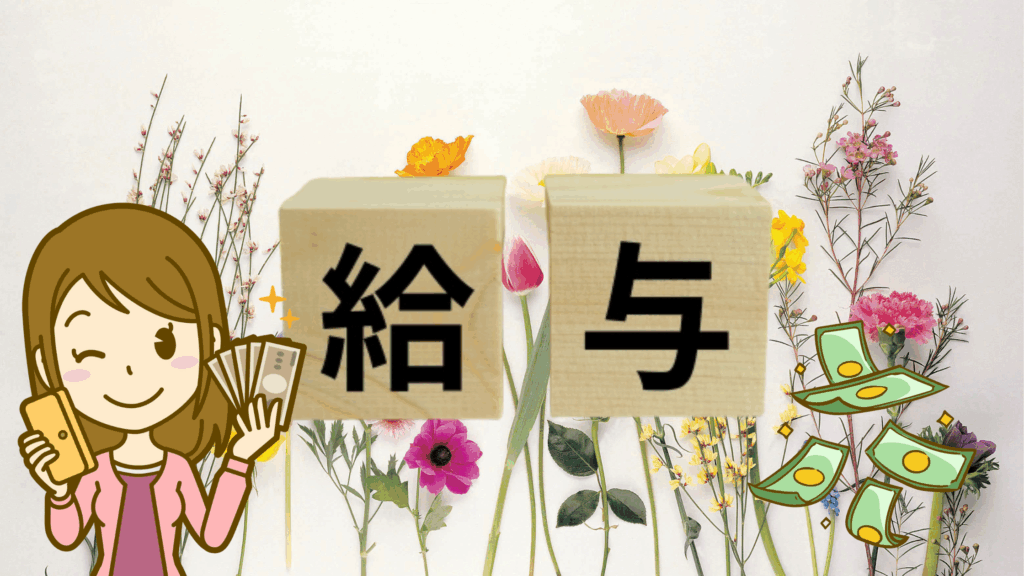
給与はモチベーションの根幹です。
しかし、多くの院長が勘違いしているのは、「給与=金額の多さ」だけではないということ。
実際、離職理由の多くは「給与が低い」ではなく、“納得できない”にあります。
つまり、給与を「辞める理由」から「続ける理由」に変えるには、透明性・将来性・対話性の3つが欠かせません。
ここでは、そのための3つのステップを紹介します。
① 定量×定性の評価制度を導入して公平性を担保
給与の不満の多くは、「何を基準に決まっているのか分からない」ことから生まれます。
そのためには、評価制度を定量+定性の両軸で設計することが重要です。
「頑張り」も「成果」も数値化するスキーム設計
公平な評価制度のポイントは、“努力”と“成果”のどちらも見逃さない仕組みです。
- 定量評価:担当患者数、スケーリング件数、リコール率、売上貢献度など
- 定性評価:チームワーク、後輩指導、患者対応の丁寧さなどをスコア化
- 加点方式で、日々の行動や貢献を積み上げて可視化
このように、数値化×可視化することで、感覚ではなく「納得できる評価」が実現します。
歯科衛生士が「頑張りを見てもらえている」と感じられれば、給与への満足度は自然と上がります。
② 等級・キャリアパスを明確化して将来像を提示
人は「この先に成長の道が見えない」とき、離職を考えます。
給与は金額よりも、「上がっていくイメージ」を持てるかどうかが大切です。
「3年後にどうなれるか」を見せるだけで離職は減る
キャリアパス制度を導入することで、スタッフに“未来の姿”を描かせることができます。
- 等級制度を明確化(例:初級→中級→リーダー→主任→マネージャー)
- 各等級で求めるスキル・行動・責任範囲を具体的に記載
- 「何を達成すれば昇給・昇格できるのか」を見える化
たとえば「3年後にリーダーになれる」「主任手当がつく」といった具体的な道筋があるだけで、
離職率は劇的に下がります。
“今の努力が未来につながっている”という感覚が、モチベーションの源泉になるのです。
③ 定期フィードバックで“給与への納得度”を高める
評価制度やキャリアパスを整備しても、「伝え方」が間違えば効果は半減します。
大切なのは、スタッフが自分の成長を院長と一緒に確認できる環境を作ることです。
査定前後の1on1で信頼関係を構築
給与や評価に関する話は、単なる「結果通知」ではなく、対話の機会に変えることが重要です。
おすすめの流れは以下の通りです。
- 査定前に「自己評価面談」を実施し、スタッフ自身に振り返ってもらう
- 院長からの評価と照らし合わせ、ギャップを言語化
- 「今後どう伸ばしていくか」を一緒に決める
このプロセスを通じて、スタッフは「院長は自分をちゃんと見てくれている」と感じます。
結果として、給与=信頼のバロメーターとなり、定着率が高まります。
定着率アップに成功したクリニックの事例
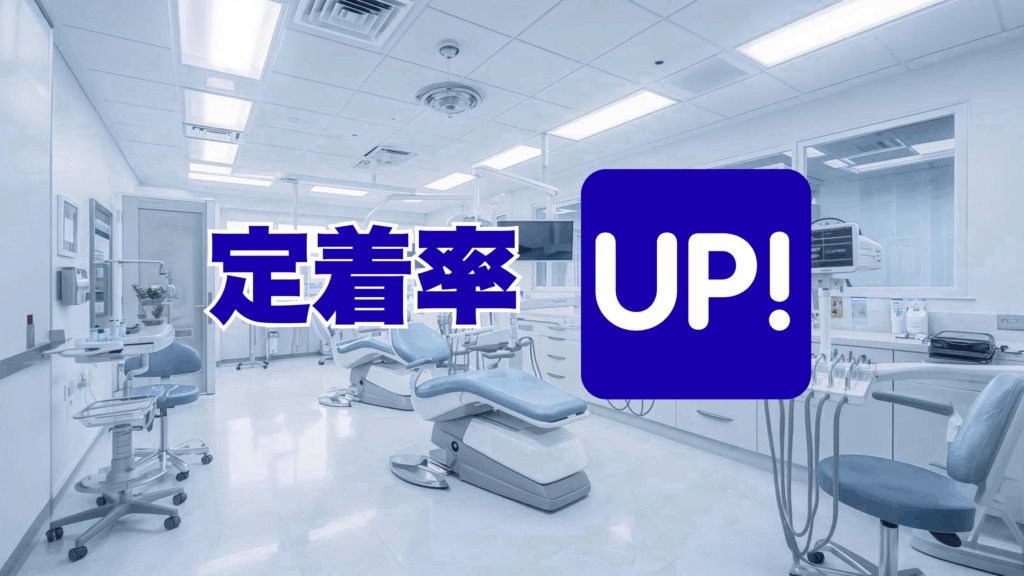
制度や評価を整えることで、本当に離職率は下がるのか?
ここでは、実際にマネジメント改革に取り組み、成果を上げた歯科クリニックの事例を紹介します。
事例①:教育マニュアル化で新人が3年定着
新人教育が属人的だったクリニックでは、入社1年以内の離職が続発していました。
そこで、業務マニュアルを動画+チェックリスト形式で整備。
- 教育担当を固定化
- 成長段階を「見える化」
- 院長・スタッフ全員が同じ基準でフォロー
結果、「誰が教えても同じ品質で育つ仕組み」ができ、
新人の定着率が1年で40%→90%に改善しました。
事例②:1on1導入で「院長が話しやすい」と評価が向上
ある医院では、スタッフが「院長に話しかけづらい」と感じていました。
そこで、月1回15分の1on1ミーティングを導入。
- 「最近どう?」から始まるカジュアルな会話
- 業務の相談だけでなく、個人的な話題もOK
- 院長が“聞き役”に徹するスタイル
結果、「院長が話を聞いてくれる」「意見を言いやすい」と評価が急上昇。
その後、離職者ゼロを半年間継続し、“心理的安全性”の高い職場を実現しました。
事例③:評価制度刷新で“やりがいの見える化”を実現
別のクリニックでは、給与の決め方が曖昧で、スタッフの不満が多発。
そこで、定性×定量のハイブリッド評価制度を導入しました。
- 数値目標+行動指標を設定
- 月次フィードバックで成長を可視化
- 昇給基準を「公開ルール化」
導入から半年後、「頑張りが報われる」と感じるスタッフが増加。
やりがいの“見える化”がモチベーションを生み出し、定着率が大幅改善しました。
教育・マネジメントの仕組みづくりに関しては、こちらの記事で新人教育から定着までの流れを体系的に紹介しています。
今日からできる!院長が実践すべき5つの改善ポイント
離職率を下げるための“マネジメント改革”は、明日からすぐにできる小さな行動の積み重ねから始まります。
制度を整えるのも大切ですが、現場の空気を変えるのは日々のコミュニケーションです。
ここでは、どんな院長でも今すぐ実践できる「5つの改善ポイント」を紹介します。
1. “感謝”を口に出して伝える習慣をつくる
最もシンプルで、最も効果的なのが“感謝の言葉”です。
「ありがとう」「助かったよ」と口に出すだけで、スタッフの表情は確実に変わります。
多くの院長が「感謝しているけど、わざわざ言うのは照れくさい」と感じていますが、
実は“言葉にしない感謝”は伝わっていません。
- 日報や朝礼で「昨日ありがとう」を1つ伝える
- 小さな成果や気づきを拾って言葉にする
- 忙しい時こそ「おかげで助かった」と言う
これを続けるだけで、職場の空気が柔らかくなり、離職率が自然に下がる土台ができます。
2. 会議・ミーティングを“指導”から“共有”型へ
多くのクリニックでは、「院長が話し、スタッフが聞くだけ」の会議が定着しています。
しかし、それでは現場の本音もアイデアも出てきません。
“共有型ミーティング”とは、スタッフ全員が発言できる形に変えること。
- 月1回の振り返り会を設定し、「良かったこと・改善したいこと」を各自が発表
- 議題の半分を「スタッフ発信型」にする
- 「院長が評価する場」ではなく、「現場が学び合う場」に変える
このスタイルに変えるだけで、主体性・心理的安全性・チーム意識が一気に向上します。
3. 教育担当を固定化し、属人化を防ぐ
新人教育が“教える人によってバラバラ”なのは、離職を招く典型的な構造です。
院長自身が全員を見きれないのは当然のこと。だからこそ、教育担当者の固定化が鍵になります。
- 先輩スタッフの中から教育リーダーを任命
- 育成チェックリストや研修スケジュールを整備
- 院長は“育成のフォロー役”に徹する
「誰に聞けばいいか分からない」「教え方が毎回違う」というストレスを減らし、
新人の安心感を高めることができます。
結果、教育コストも離職率も同時に下がるという効果が得られます。
4. スタッフの成長を“見える数字”でフィードバック
人は“成長が感じられない環境”にいると、やる気を失います。
それを防ぐためには、感覚ではなく数字で成果を伝えることが重要です。
例えば、
- スケーリング件数、リコール率、診療補助数などをグラフ化
- 前月比・前年同期比を可視化して共有
- 「〇〇さんは○○が5件増えたね!」と具体的にフィードバック
このように数字で「成長」を見せることで、スタッフは自信を持ち、
「自分の頑張りが見えている」と感じます。
モチベーションアップと自己肯定感の向上につながる重要な一手です。
5. 自分のマネジメントを定期的に振り返る
最後に見直すべきは、「院長自身のマネジメント」です。
スタッフの変化を求める前に、自分の関わり方を客観的に振り返る習慣を持つことが大切です。
- 月1回、信頼できる外部コンサルやマネージャーと“経営面談”を実施
- 自分の発言・指導スタイルを録音やメモで振り返る
- 「最近、感謝を伝えたか」「褒めた回数」をチェック
小さな気づきの積み重ねが、院長自身の成長を促します。
院長が変わると、スタッフの行動も変わる——それが、定着率向上の本質です。
まとめ|「人が辞めない歯科医院」は“文化”で決まる

離職率を下げるために必要なのは、評価制度や給与だけではありません。
本当に大切なのは、「人を中心に据えた仕組み」が文化として根づいているかどうかです。
文化は“気持ち”ではなく、“仕組みを通じて定着する行動パターン”としてつくられます。
「関係性」と「成長実感」を仕組みで支えることが定着を左右する
多くの離職要因は、「人間関係が悪い」「成長を感じられない」という“感覚的な不満”です。
しかし、それを感情論で解決しようとすると、再現性が生まれません。
重要なのは、
- 評価制度で成長を可視化する
- 面談や1on1で関係性を仕組みに組み込む
- 教育やキャリア支援を仕組みで継続させる
という「文化を支える構造」を設計することです。
関係性も成長実感も、“仕組みの中で自然と生まれる環境”を整えることで、初めて長期的な定着につながります。
“ありがとう”と“聞く仕組み”が離職防止の第一歩
マネジメントの第一歩は、「感謝」と「傾聴」を習慣化できる仕組みに落とし込むことです。
たとえば、
- 月次1on1で「感謝・成果・課題」の3項目を共有
- スタッフ評価シートに「ありがとう欄」を設ける
- 朝礼で“良かった行動”を1人ずつ紹介
このように、感謝や対話を“仕組みとして運用”することで、院長の想いが継続的に伝わります。
結果として、「自分の働きが見えている」「理解されている」と感じるスタッフが増え、自然と離職が減っていきます。
まずは“仕組み化された1on1”から始めよう
最初に取り入れるべき仕組みが、1on1ミーティングです。
感覚的な面談ではなく、「目的・頻度・記録」が明確な仕組みとして運用しましょう。
- 月1回15分でも、定期的に行うことを“ルール化”する
- 話した内容をシートで共有し、次回に活かす
- 成果・行動・感情の3軸で整理する
1on1を「人と話す時間」ではなく、「現場の声を仕組みで吸い上げる場」と定義することで、
経営判断にも直結するデータが蓄積されます。
それが“仕組みで文化を育てる”第一歩になります。
マネジメント改革の本質は、「人を仕組みで動かす」ことではなく、「仕組みを使って人と文化を育てる」ことです。
Bay3株式会社が提唱する“現場伴走型支援”の価値も、まさにこの点にあります。
制度やツールはゴールではなく、「人が成長し続ける文化を支える土台」です。
その仕組みを活かせる院長こそ、真に“人が辞めない医院”をつくるリーダーなのです。
制度を“作って終わり”にせず、仕組みを活かして人と文化を育てる。
その一歩を、私たちと一緒に始めませんか?
Bay3株式会社は、現場に入り込み、制度設計から実行まで伴走するコンサルティング会社です。
👉 無料で相談する(オンライン対応可)