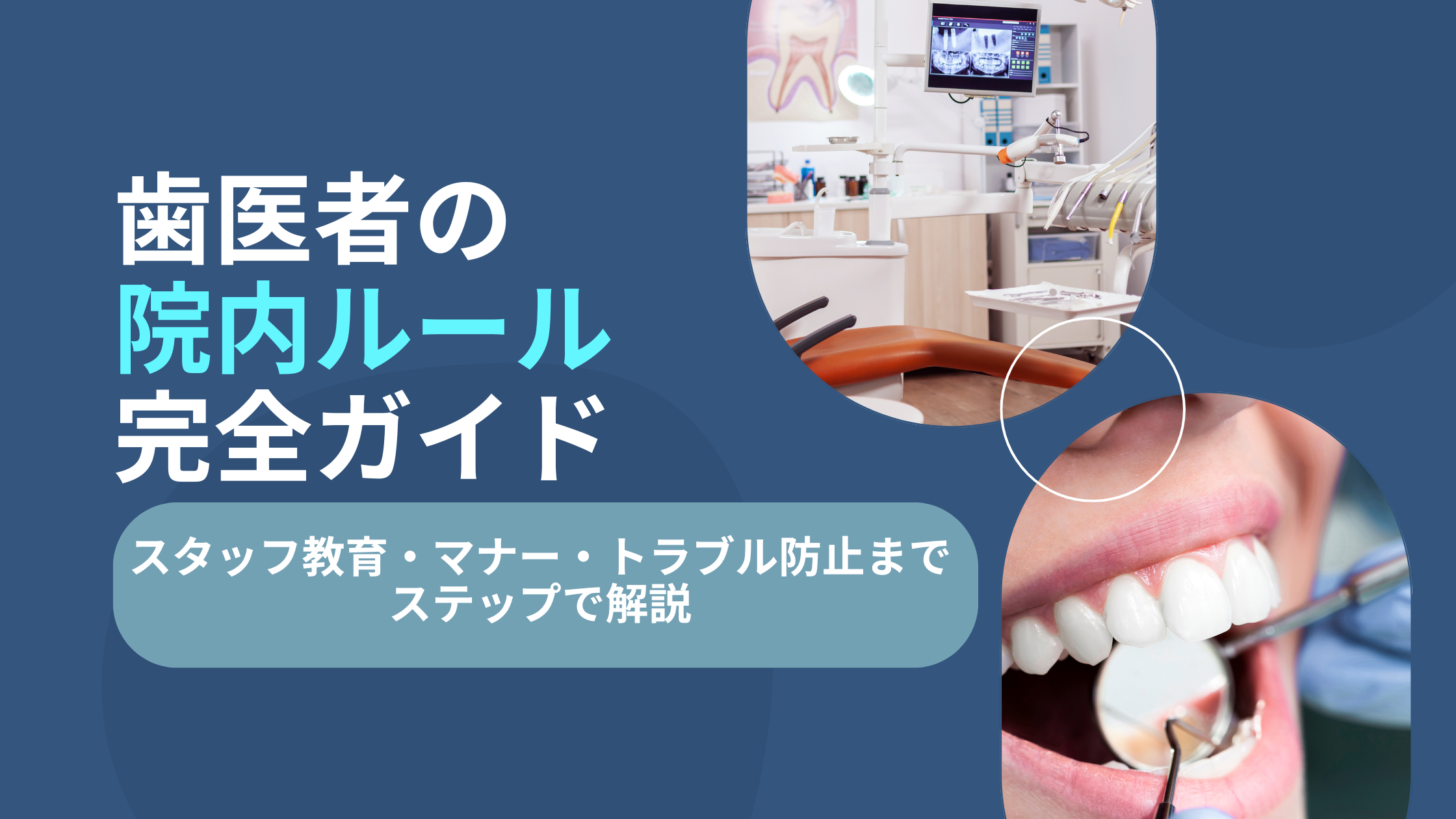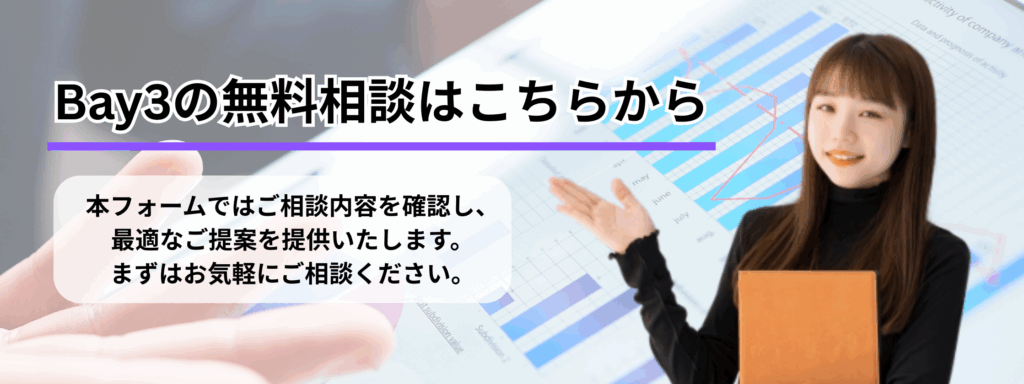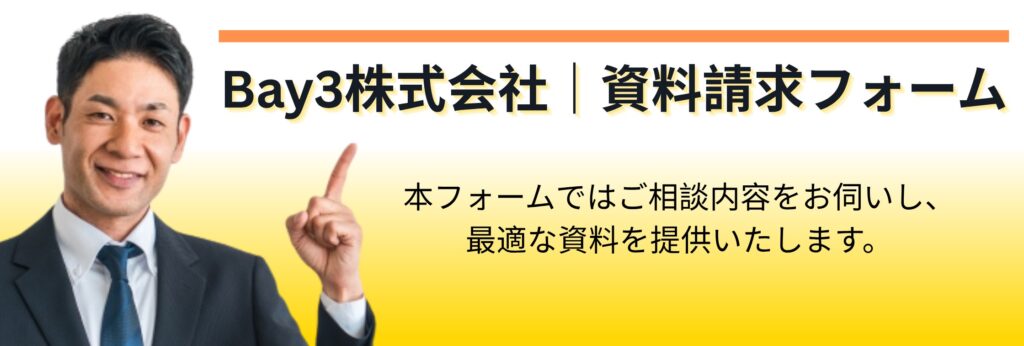「スタッフによって対応が違う」「マナーや言葉遣いでクレームが出た」「感染対策のルールが曖昧」——そんな課題を感じていませんか?
本記事では、歯科医院の院長・経営者が知っておくべき院内ルールの作り方を、5つのステップで体系的に解説します。
マナー・トラブル防止・法令遵守まで、現場で“実際に機能するルール設計”を徹底ガイドします。
なぜ歯科医院に「明確なルール」が必要なのか
トラブルの9割は“ルールのあいまいさ”から生まれる
トラブルの原因は、「ルールがないから」ではなく、ルールがあいまいだからです。
たとえば、以下のようなケースは多くの医院で見られます。
- クレーム対応を誰が行うか曖昧
- キャンセル時の説明がスタッフごとに違う
- SNSでの発信ルールが決まっていない
このような状態では、対応のばらつきが発生し、患者からの信頼を失うリスクが高まります。
さらに「新人は教わる人によってルールが違う」といった声が出れば、現場の不満も蓄積します。
明確なルールを文書化して共有するだけで、対応の一貫性が保たれ、“誰が対応しても安心”な医院運営が実現します。
つまり、ルール整備とは「トラブルを減らす」だけでなく、「スタッフを守る仕組み」でもあるのです。
院内ルールが「離職率」と「患者満足度」に与える影響
歯科医院における離職率の高さは、業界共通の悩みです。
その多くは「人間関係」や「指示のあいまいさ」に起因しています。
ルールが明確でないと、スタッフは不安を感じ、やりがいを失ってしまうのです。
一方で、ルールを整備している医院では次のような変化が見られます。
- 役割と責任範囲が明確になり、無駄なストレスが減る
- 評価基準がはっきりし、スタッフが納得感を持って働ける
- 教育体制が整い、新人が早期に定着する
さらに、患者満足度の向上にもつながります。
どのスタッフが対応しても「安心感がある」「説明がわかりやすい」と感じてもらえれば、口コミや紹介での来院が増加。
結果的に、ルール整備は医院のブランド力アップと経営の安定化につながります。
ルールを整備することで得られる3つの効果(再現性・信頼・効率)
院内ルールを整えることで得られる効果は、単なる“マナーの統一”にとどまりません。
医院運営全体の基盤を支える、3つの経営効果があります。
【1】再現性が高まる
- 誰が対応しても同じ品質で診療・接客ができる
- 教育コストが削減され、業務の属人化を防止
【2】信頼が生まれる
- 感染対策・情報管理・マナーが統一されることで、患者からの安心感が向上
- スタッフ間の信頼も生まれ、チームワークが強化される
【3】効率が上がる
- 判断基準が明確になるため、迷いが減り、業務スピードが向上
- トラブル対応にかける時間が減り、生産性の高い医院運営が可能に
つまり、院内ルールとは「縛るもの」ではなく、人と医院を守る仕組み。
これが整えば、院長も現場も余裕を持って本来の“診療”に集中できます。
歯科医院の院内ルールづくり【5ステップで体系化】

歯科医院のルールづくりは、「思いついた順に作る」のではなく、理念から現場運用までを体系的に整えることが重要です。
ここでは、現場で機能し、スタッフ全員が自分ごととして動けるルール設計を、5つのステップでわかりやすく解説します。
ステップ①:医院理念と行動基準を明確にする
まず最初に取り組むべきは、「ルール」よりも前にある理念の明確化です。
なぜなら、理念が曖昧なままルールを作ると、現場が「何のために守るのか」を理解できず、形骸化してしまうからです。
医院の「価値観」を言語化し、判断基準を共有する
医院の理念は、“経営者の想いを現場が判断に使える言葉”に落とし込むことがポイントです。
たとえば、
- 「患者に安心を届ける」=笑顔・傾聴・清潔を重視
- 「チームで支える医療」=報連相・協力・感謝を明文化
理念が定まったら、日常行動に変換して共有します。
例:
- 「患者さんの前ではマスク越しでも笑顔を意識」
- 「報告は“その日のうちに”が原則」
このように、理念を“現場の判断基準”に変えることで、スタッフが自律的に動ける文化が育ちます。
ステップ②:現場の業務ルールを整理する
次に必要なのは、「誰が・何を・どの手順で行うか」を明確にすることです。
現場では、口頭伝達や経験頼りの業務が多く、スタッフによって作業手順が異なるケースがよくあります。
受付・診療補助・滅菌など、職種別マニュアルを整備
職種ごとにマニュアルを作成する際は、以下の3要素を意識しましょう。
- 業務フローの可視化
→ 受付対応・診療補助・滅菌など、タスクを順序立てて整理。 - 写真・図解を活用
→ 新人が見てもすぐ理解できるように、ビジュアル化する。 - 更新しやすい仕組み
→ 紙ではなく、Googleドキュメントやクラウド管理を活用。
特に歯科医院では、感染対策・器具管理・診療補助といった業務が細分化されているため、
「属人化を防ぐためのルール整備」が、医院全体の安定運営につながります。
ステップ③:マナー・接遇ルールを定義する
技術力だけでなく、「接遇マナー」は医院の信頼を左右する大きな要素です。
患者対応がスタッフごとに違えば、「あの人は感じがいいけど、別の人は冷たい」と印象がバラつき、口コミ評価にも影響します。
言葉遣い・身だしなみ・報連相の“統一ルール”を明文化
マナーは“センス”ではなく、“ルール”として明文化しておくことが大切です。
以下のように項目別で基準を作ると共有しやすくなります。
- 言葉遣いルール:患者には「お名前+様」で呼ぶ、専門用語は使わない
- 身だしなみルール:髪色・爪・アクセサリーなどを写真付きで明示
- 報連相ルール:「困ったときは必ず院長かリーダーに即報告」
スタッフが迷ったときに立ち返れる「判断軸」があると、接遇品質が安定します。
ステップ④:教育・研修でルールを“浸透”させる
せっかく作ったルールも、「共有して終わり」では機能しません。
ルールを“文化”として根づかせるには、教育とフィードバックの仕組みが必要です。
OJT+定期面談で“伝える仕組み”を構築
おすすめは、「OJT(現場教育)」と「定期面談」を組み合わせた運用です。
- OJTでの実践学習:先輩がマンツーマンで手順・接遇・考え方を伝える
- 定期面談で振り返り:月1回、ルール理解度・課題・改善を共有
さらに、研修ノートやチェックリストを活用して“学びを見える化”することで、
「できること・できていないこと」が明確になり、教育効果が倍増します。
教育の型づくりは、こちらの手順が実装に役立ちます。
ステップ⑤:定期見直しと「ルール運用会議」で改善する
最後のステップは、「ルールを作って終わり」にしないことです。
現場の状況や人員が変われば、ルールもアップデートが必要です。
スタッフの声を反映し、現場で機能するルールへアップデート
ルール運用を改善するには、“現場の声”を定期的に吸い上げる仕組みが欠かせません。
月1回程度の「ルール運用会議」を設け、以下のような議題で話し合うと効果的です。
- ルールが守られていない原因の共有
- 新人が困っているポイントの把握
- 改善案をスタッフ自身が提案
これにより、スタッフがルールに“自分ごととして関わる”ようになり、自然と定着が進みます。
トップダウンではなく、全員で育てるルール運用こそ、持続する仕組みの鍵です。
トラブル防止のために守るべき“10の基本ルール”
院内ルールの目的は「スタッフを縛る」ことではなく、医院を守り、信頼を築くための仕組みです。
特に歯科医院では、クレーム・感染・情報漏えいといったリスクが日常的に発生します。
ここでは、トラブル防止に欠かせない10の基本ルールを、重要テーマ別に整理して解説します。
クレーム対応・SNS投稿・患者対応の危険ライン
歯科医院におけるクレームやトラブルの多くは、「対応の一言」「SNSでの不用意な投稿」から発生します。
患者との信頼を守るためには、日常のふるまいに明確な基準を設けましょう。
主なリスクとルール例:
- クレーム対応ルール
・感情的に反論せず、「事実確認→報告→対応決定」の手順を守る
・その場で判断せず、院長・リーダーへのエスカレーションを徹底
・クレーム内容は必ず「記録」に残す - SNS投稿ルール
・患者やスタッフが写った写真は必ず本人の許可を得る
・個人情報や診療内容に関する投稿は禁止
・医院アカウントの運用は管理者を限定 - 患者対応ルール
・患者を呼ぶ際は必ず「〇〇様」
・否定的な言葉(「無理です」「わかりません」など)は避ける
・困った時は必ず上司・先輩へ報告
Point:
トラブルを防ぐ最大の方法は、“現場判断を減らす仕組み化”です。
マニュアルに沿って対応できる状態を整えることで、スタッフの心理的負担も軽減されます。
感染防止・衛生管理・個人情報の取り扱い
感染対策や個人情報保護は、法律に基づいた「義務」です。
一人の油断が医院全体の信用を失墜させるため、ルールの徹底は最優先事項です。
感染防止ルール:
- 患者ごとに器具の滅菌・グローブ交換を徹底
- 使用後の器具は“滅菌前エリア”に一時保管し、導線を分ける
- 診療台・ドアノブなどは患者ごとにアルコール清拭
衛生管理ルール:
- 洗浄・消毒・滅菌のフローを「見える化」した掲示物で共有
- ゴミ分別・廃棄物処理ルールをスタッフ全員に再周知
- 定期的な内部監査を実施し、記録を残す
個人情報保護ルール:
- カルテ・レセプト情報は常に施錠管理
- スマートフォン・USBメモリなどでのデータ持ち出しは禁止
- 患者名・症状を第三者が聞こえる場で口にしない
Point:
感染防止や情報管理の“見えないルール”こそ、掲示・記録・教育で習慣化させましょう。
厚労省ガイドラインに基づく法的チェックポイント
歯科医院は、医療機関として医療法・個人情報保護法・広告ガイドラインを遵守する義務があります。
無意識のうちに違反してしまうケースも多く、経営リスクを防ぐには定期的な確認が不可欠です。
要チェック項目:
- 医療広告規制
・「日本一」「絶対治る」といった誇大表現は禁止
・ビフォーアフター写真は“治療内容と条件”の明記が必須
・口コミ掲載は患者の同意が必要 - 診療情報管理
・カルテの保存期間(5年間)を遵守
・患者情報の電子管理にはアクセス制限を設定 - 感染防止体制の届出
・外来環境体制加算を算定している場合は、感染管理者の配置が必須
Point:
ルール整備は“法律対応”と“現場対応”をセットで考えること。
制度改定時には、歯科医師会や専門コンサルと連携し、最新情報にアップデートしましょう。
法令順守を現場運用へ落とすには、こちらの記事で会議・評価の設計も確認しましょう。
「ルールを破ったとき」の対応方針と再発防止策
どんなにルールを整備しても、「うっかり」や「判断ミス」は起こります。
重要なのは、「再発を防ぐ仕組み」を持つことです。
対応ステップ:
- 事実確認:感情的に叱責せず、経緯を丁寧にヒアリング
- 再教育:該当ルールの背景を再共有し、理解度を確認
- 改善記録:再発防止策をマニュアルに反映
- 再発チェック:1〜2週間後に再確認を実施
Point:
“罰則”ではなく“改善”に焦点を当てることが、信頼と定着を生むポイントです。
ミスを責める文化ではなく、学びに変える仕組みを整えましょう。
「マニュアルを作ったのに守られない…」という悩みを抱える医院は少なくありません。
大切なのは、ルールを“共有”ではなく“浸透”させる仕組みを作ることです。
“掲示”ではなく“対話”で浸透させるマニュアル運用法
多くの医院が、ルールを紙にして掲示するだけで満足してしまいます。
しかし本当に大事なのは、「なぜそのルールが必要なのか」を対話で伝えることです。
効果的な浸透ステップ:
- 月1回の「ルール共有ミーティング」を実施
- 1テーマ10分で“背景と目的”を説明
- スタッフから改善提案を募る
Point:
「理解させる」よりも「納得してもらう」ことが、行動変容の鍵です。
新人教育を仕組み化する「トレーニングマップ」
新人教育の属人化を防ぐためには、誰が見ても進捗がわかるトレーニングマップを導入しましょう。
作成のポイント:
- スキル項目を「知識・実践・応用」の3段階で整理
- 教育担当を明確にし、チェック欄で進捗を可視化
- 毎週のOJTでマップを更新
例:
| 項目 | 担当 | 進捗 | コメント |
| 滅菌手順 | 衛生士A | ✅ | 翌週に再確認 |
| 受付応対 | 受付長B | ⏳ | 電話応対に課題あり |
Point:
「教える人が変わっても品質が変わらない」状態を作ることが、新人定着の第一歩です。
現場が動きやすい「チェックリスト化・見える化」のコツ
ルールは“守らせる”ものではなく、“自然と守れる”形にするのが理想です。
チェックリスト化と見える化で、行動定着をサポートしましょう。
実践例:
- 開院前・閉院後のチェックリストを共有(清掃・器具確認など)
- 感染対策ポスターやマニュアルを現場動線に掲示
- 月次で「達成率」をホワイトボードに記載
Point:
「誰でも・いつでも・すぐ確認できる仕組み」が、トラブルゼロの医院をつくります。
リーダー層の育成と“ルールの守らせ方”のポイント
ルールを浸透させるのは、院長一人の仕事ではありません。
現場のリーダーや主任が“日常の中で自然に指導できる環境”が理想です。
リーダー育成のコツ:
- 注意ではなく「なぜそれが大事か」を伝える
- ミスが起きたときは一緒に原因を探る
- スタッフの意見を拾い、上層部にフィードバックする
Point:
ルールを守らせるリーダーではなく、「ルールの意図を伝えられるリーダー」を育てましょう。
その姿勢こそ、組織文化としての“信頼”を生み出します。
成功する歯科医院が実践する「院内ルール運用のコツ」

院内ルールを「作ること」は誰にでもできます。
しかし、本当に成果を出している歯科医院は、“運用”の部分に力を入れています。
ここでは、スタッフが自発的にルールを守り、チームとして機能するための仕組みづくりを紹介します。
成功する医院は“ルール運用”に力を入れています。
あなたの医院も、機能する仕組みを一緒に。
👉 無料相談で現状を診断
スタッフが“自分ごと化”する仕組みづくり
ルールを浸透させる最大のポイントは、「守らされるルール」から「自分たちで守るルール」へ変えることです。
理由:
ルールを押し付けられると、スタッフは「監視されている」と感じてしまいます。
一方で、ルールづくりに自ら関わると、「医院の一員としての責任感」が生まれます。
実践例:
- 新しいルールやマニュアルを作る際は、必ずスタッフ代表を巻き込む
- 「なぜこのルールが必要か」をディスカッションする時間を設ける
- 意見を反映した箇所には「提案:○○さん」と記載して可視化
Point:
現場で使われるルールほど、スタッフが関与して作ったものです。
「一緒に作るプロセス」こそ、最も強い浸透施策になります。
定期ミーティングでルールをアップデートする文化
ルールは一度作って終わりではありません。
時代の変化や新しいメンバーの加入に合わせて、定期的にアップデートする文化を持つ医院が成果を出しています。
おすすめの運用方法:
- 月1回の「ルール運用会議」を開催
→現場で困っている点・改善したい点を共有 - 議題は“改善前提”で設定(例:「報連相の遅れ対策」など)
- 更新履歴をマニュアルに追記して“進化するルール”を見える化
Point:
会議を通じて「ルール=現場を良くする道具」という認識を根づかせましょう。
話し合いを習慣化することで、スタッフの主体性とチーム力が育ちます。
ルール運用で成果を出した歯科医院の成功事例
ルールを“運用”まで落とし込んだ医院は、スタッフ定着・患者満足の両面で成果を上げています。
ここでは、実際に成果を出した2つの事例を紹介します。
例①:マニュアル整備で新人定着率90%達成
ある歯科医院では、新人教育の属人化が課題でした。
ベテランごとに教え方が違い、入社3カ月以内の離職が相次いでいました。
そこで導入したのが、職種別のマニュアルとトレーニングマップ。
・受付・滅菌・診療補助などを5分単位で明文化
・教育担当を固定せず、誰でも教えられる体制に変更
・月1回の“習熟度チェック会”で進捗を見える化
結果、1年以内の離職率が10%未満に改善。
「誰でも同じように教えられる環境」が整い、院内教育の質が大幅に向上しました。
例②:SNSガイドライン導入でクレームゼロを実現
別の医院では、スタッフ個人のSNS投稿が原因で患者からクレームが発生。
すぐにSNSガイドラインと情報管理ルールを整備しました。
実施内容:
- 投稿可否の判断基準を明確化(例:「個人を特定できる情報NG」)
- 院内研修で「SNSトラブルの事例」を共有
- 週次で運用状況をモニタリング
結果、クレーム件数はゼロになり、医院アカウントのフォロワーも増加。
「信頼される発信」がブランディングにもつながりました。
スタッフ教育やルール浸透の仕組みをさらに深めたい方は、こちらの記事でも参考になります。
ルール設計から運用まで伴走支援する「実行支援型コンサル」とは
多くの医院では、「ルールを作ったけれど、結局使われない」という壁にぶつかります。
そんなときこそ頼りになるのが、“実行支援型コンサルティング”です。
単なるアドバイスではなく、現場に入り込み“実際に定着させる”支援が特徴です。
コンサルに頼るべきタイミングと範囲
以下のような状況に当てはまる場合、外部の専門家にサポートを依頼するタイミングです。
よくある課題:
- ルールを作ったが、スタッフが守っていない
- マニュアルが古く、現場とかけ離れている
- 教育・評価・仕組みの整合性が取れていない
- クレームや離職が増えており、改善策が見えない
サポート範囲の一例:
- 院内ルール・マニュアル設計
- スタッフ教育・評価制度設計
- 会議体・コミュニケーション設計
- 定着支援(運用伴走・現場コーチング)
Point:
「自分たちで作る」から「一緒に動かす」へ。
行動レベルまで落とし込むことが、実行支援型の最大の価値です。
“実行支援型”と“提案型”の違い
提案型コンサルは「やり方を教える」、
実行支援型コンサルは「一緒にやる」。
この違いが、成果の出方を大きく左右します。
| 項目 | 提案型コンサル | 実行支援型コンサル |
| 役割 | 改善提案を行う | 現場に伴走し実行支援 |
| 成果 | 企画書・指示書 | 行動変化・仕組み化 |
| 特徴 | 短期的・理論中心 | 長期的・現場密着 |
| メリット | 専門知識の獲得 | 定着・再現性の確保 |
Point:
医院運営の課題は「知る」ではなく「やる」で変わります。
だからこそ、実行まで支援してくれるパートナーが重要です。
Bay3株式会社が支援する「院内ルール定着プロジェクト」
Bay3株式会社では、「ルールを作る→教育で浸透→仕組みで定着」という3段階で医院をサポートしています。
事例①:ルール×教育体制の構築でチーム力向上
ある医院では、スタッフ間の情報共有がうまくいかず、トラブルが頻発していました。
Bay3は、ルール整備と教育体制を同時に設計。
- 行動指針を可視化
- トレーニングマップを導入
- 月次の「チームミーティング」で課題共有を習慣化
結果、スタッフ間の連携ミスが激減。
“チームで動ける医院”へと変化しました。
事例②:理念と行動基準の明文化でクレーム減少
別の医院では、院長の考えが現場に伝わらず、対応のばらつきが課題に。
Bay3は、理念と言葉遣い・行動基準を明文化し、全員で共有する仕組みを導入。
- 「医院理念ブック」を全員に配布
- 定例ミーティングで毎回“理念を読む”時間を設置
結果、クレーム件数が半減し、スタッフ満足度も上昇しました。
Point:
Bay3の支援は“制度を作る”だけでなく、現場に根づく文化を育てることに重きを置いています。
まとめ|ルールは“作る”だけでなく“活かす”ことが重要

院内ルールは、医院を守る“盾”であると同時に、成長を支える“土台”でもあります。
ルール整備は“経営基盤づくり”の第一歩
ルールはスタッフを縛るものではなく、医院を強くする経営ツールです。
「マネジメントの仕組み=ルール」として捉えることで、離職率・クレーム・業務効率のすべてが改善します。
スタッフとの対話から現場に根づく文化を育てよう
掲示ではなく、対話で伝える。
ルールは共有よりも「共感」で定着します。
日々のミーティングや面談を通じて、スタッフと一緒に“医院の形”を磨き続けましょう。
Bay3の無料相談で、あなたの医院の課題を「見える化」
「うちの医院のルール、これでいいのかな?」
そんな疑問を感じたら、Bay3株式会社の無料相談を活用してください。
Bay3は、
- 院内ルール・教育・評価制度の現場定着支援
- 実行支援型の伴走で“仕組みの運用”までサポート
- あなたの医院の課題を「見える化」し、解決策を一緒に設計
まずは“現場の声”から課題を整理し、未来に続く仕組みづくりを始めましょう。
ルールは“作る”だけでなく“活かす”時代へ。
今すぐ、あなたの医院の課題を可視化。
👉 Bay3に無料で相談する