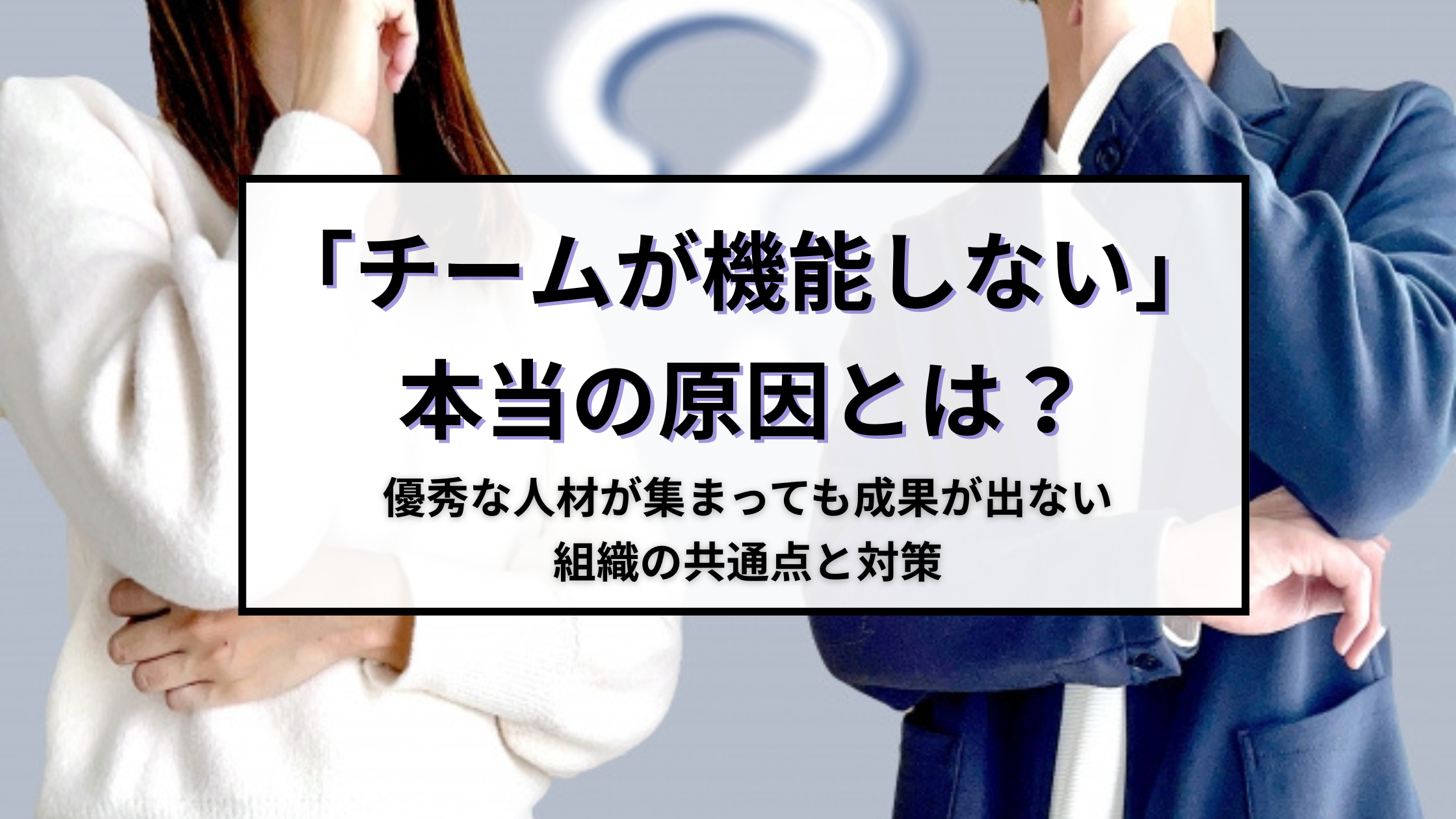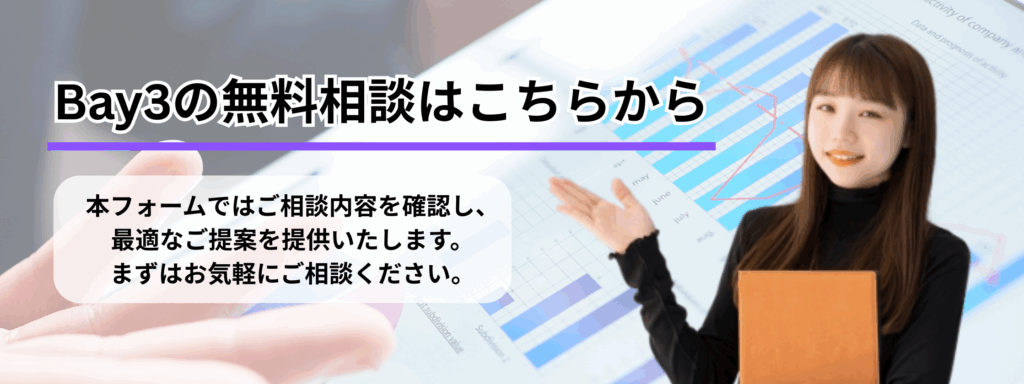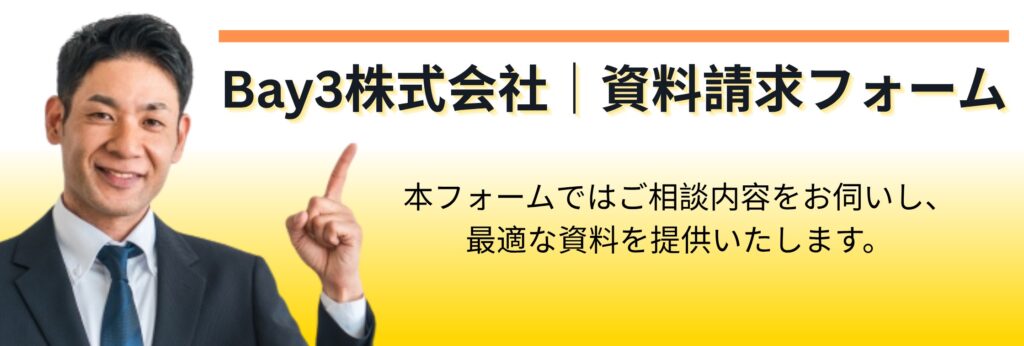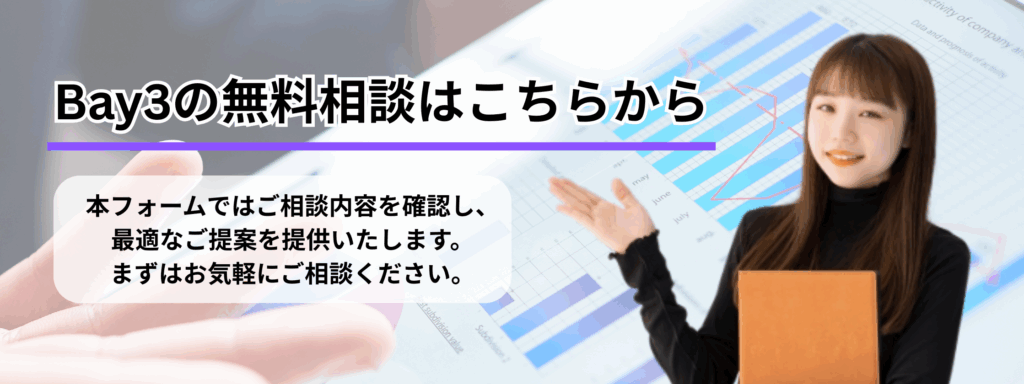「なぜうちのチームはうまくいかないんだろう?」 それなりに経験のあるメンバーを揃えたはずなのに、なぜか目標に向けて一枚岩にならない。
口では連携やチームワークと言っていても、実際はバラバラに動き、成果は出ず、関係性もどこかギスギス。
プレイングマネージャーとして走りながら悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
結論:「チームが機能しない」のは“個の力不足”ではなく、“構造のズレ”に原因があります。
- メンバー間の目標や役割の認識がズレている
- 「自分の仕事だけ」で完結してしまい、協働が生まれない
- リーダーが背負いすぎて、全体のマネジメントが滞っている
- 評価が曖昧で、頑張る意味が見えにくい
- 心理的安全性がなく、発言や報告がしづらい空気になっている
これらはすべて、構造や文化、仕組みの見直しで改善可能です。
本記事では、そうした「チームが機能しない原因」を整理し、現場で実践できる改善策やマネジメントのヒントまでご紹介します。
同じ悩みを抱えるリーダー・マネージャーの方の参考になれば幸いです。
なぜ「チームが機能しない」と感じるのか?|現場でよくある悩みと兆候

「なんとなく最近チームの空気が悪い」「会議しても前に進んでいない気がする」 そんな違和感を放っておくと、気づいた時には深刻な“チーム不全”に陥ってしまうことも。
このセクションでは、現場でよく見られる兆候や、放置が招くリスクを整理します。
崩壊の前に見えてくる“チーム不全”のサイン
いきなりチームが崩れるわけではありません。 多くの場合、小さな違和感やズレが“予兆”として現れます。
- 会話や報告が減り、「空気を読む」文化が強くなる
- チームメンバー同士の関係が表面的で、相談や協力が生まれない
- リーダーの指示待ちが常態化し、自発的な行動が少ない
- 成果が出ていないのに「問題ないです」と形式的な報告が続く
- Slackや会議で誰も発言しない。リアクションも薄い
こうしたサインが出てきたら、「チームは機能している」とは言えません。 むしろ、“うまく回っているフリ”をしている状態とも言えます。
チームワークが悪い職場に共通する行動パターン
「うちはチームワークが悪いわけじゃない」と思っていても、実際には“協力している風”の職場も多いのが現実です。
以下のような行動が見られる場合、要注意です。
- 成果が個人単位で語られ、チーム単位の振り返りがない
- 「この人に頼めば何とかなる」と、特定メンバーに負荷が集中
- 問題が起きても「誰の責任か」が焦点になり、改善につながらない
- 人によって働き方や目線がバラバラで、共通言語がない
- 会議で発言するのはいつも同じ数人
チームワークとは、「仲が良い」ことではありません。 「共通の目的に向かって行動し、相互に補完し合うこと」が機能している状態です。
それが欠けたとき、どんなに優秀な個人が集まっていても、組織としては機能しないのです。
「チーム崩壊」と「機能不全」はどう違うのか?
「崩壊」と「機能していない」は似ているようで、段階が違います。
チームが機能していない状態: ⇒ 意思疎通が薄く、連携が取れておらず、成果に結びついていない状態 ⇒ 外から見ると一見「普通」に見えるケースも多い
チームが崩壊している状態: ⇒ メンバーの離脱や対立、心理的安全性の喪失など、明確な破綻が起きている状態 ⇒ 信頼関係も役割分担も壊れ、改善に多大なコストがかかる
まとめ:「機能不全」は崩壊の一歩手前。 早期に気づいて手を打てば、十分に回復できるフェーズとも言えます。
逆に、ここを見過ごしてしまうと、人が辞め、信頼が失われ、業績にも直結する深刻な状態に陥ります。
チームの「なんとなくうまくいかない」状態を放置しないために、こちら事例も参考に、早期の問題発見に努めましょう。
機能しないチームの特徴とは?|“心理的安全性”が崩れた組織に起こること
「最近、みんな静かすぎないか?」 「会議で誰も発言しないのは、なんでだろう?」
そんな空気感に心当たりがあるなら、それは心理的安全性の低下かもしれません。
心理的安全性とは、自分の意見を安心して言える・助けを求められる状態のこと。 この土台が崩れると、いくら制度や目標が整っていても、チームは機能しません。
ここでは、心理的安全性の欠如によって起こる具体的な“機能不全の特徴”を整理します。
信頼関係がないと生産性はどう下がるか
心理的安全性が低いチームでは、「余計な気を遣う」ことにエネルギーが奪われます。
- 意見を出すより「反論されないように」話す
- 失敗を隠す・謝らない文化が根づく
- ミスを恐れて挑戦しない
- 指示待ち・確認過多でスピードが落ちる
その結果、本来の仕事ではなく“空気を読む”ことが主な業務に。 生産性が下がるのは当然の流れです。
信頼関係は「仲が良いかどうか」ではなく、相手の意図を信じて建設的に向き合える関係性かどうか。 仕組みや制度以前に、「ここで話しても大丈夫」という感覚があるかが、成果の前提になります。
モチベーションが低下する“人間関係の歪み”
チーム内の信頼が崩れると、メンバーの意欲にも連鎖的に悪影響が出ます。
- 質問すると「またか」と冷たい反応
- 助けを求めると「自分で考えて」と突き放される
- 他人の成果を認めない、称賛しない
- 評価の基準が見えず、「何を頑張ればいいか分からない」
こうした状態では、自分の努力が報われるイメージが持てず、モチベーションが自然と下がっていきます。
特に中堅層や新卒社員は、「どうせ何をしても変わらない」と感じてしまうと、徐々に“心が離れる”のが特徴です。
組織文化・構造が悪循環を加速させる理由
チームがうまくいっていないとき、個人を責めがちですが、問題の本質は“文化”や“構造”にあることが多いです。
- 意見を出すと「空気が読めない」と思われる
- 忙しさが常態化し、振り返る時間がない
- 上司が正解を持っている前提で会話が進む
- 形式だけの面談や1on1で“本音”は語られない
こうした土壌では、誰もが防御モードになり、協働ではなく“自己保身”が優先されます。
つまり、個人のスキルではなく、組織そのものが「動けないチーム」をつくってしまっている状態。 構造と文化の両輪を見直さない限り、どんなに頑張っても悪循環から抜け出せません。
失敗するチームにありがちなパターンと兆候
機能不全に陥るチームには、いくつか共通する“あるある”があります。
- 表面的には穏やかで、トラブルが見えにくい
- 会議はあるのに、議論や意思決定が起きていない
- リーダーが現場の声を拾えていない
- 一部のメンバーだけが疲弊している
- 新人が定着しない(辞める理由が不明)
このような兆候が出てきたとき、問題はすでに「起きている」段階ではなく、「蓄積している」段階。 早めに気づいて手を打つことで、崩壊を未然に防ぐことができます。
「チームが機能しない」原因を可視化する|洗い出しと改善のアプローチ

チームの問題は、感覚や雰囲気では語れても、構造的に把握されていないことがほとんどです。
「なんとなくうまくいっていない」の正体を明らかにしない限り、改善は進みません。
このセクションでは、現場で実践できる課題の洗い出し方法から、チーム再構築のステップまでを解説します。
現場で実践できる“チーム課題”の棚卸し方法
まずは、チームに起きている“詰まり”を言語化することがスタートです。
以下のようなフレームで、業務や関係性を棚卸ししてみましょう。
- チームの目的とKPIは明確か?
- 各メンバーの役割と期待値はすり合っているか?
- 業務の流れに“属人化”や“ブラックボックス”はないか?
- 課題や改善提案が、現場から吸い上げられる構造になっているか?
- 誰かが「無理して回している」業務はないか?
ポイントは、人のせいにせず「構造」で語ること。 業務フロー図や担当マトリクスを使いながら、目に見える形で“チームの全体像”を整理しましょう。
対話・フィードバックが停滞を打破する鍵
可視化と並行して、メンバー間の対話を“習慣”として根づかせることも大切です。
- 1on1を「報告」ではなく「対話」の場に変える
- チームで「うまくいってないこと」を言える空気をつくる
- フィードバックを“人”ではなく“行動”に向ける
- 成果以外のプロセスや貢献も言語化して伝える
特に現場では、忙しさを理由にフィードバックが後回しになりがち。 ですが、リアルタイムな対話こそが、チームのズレやストレスを未然に修正する一番の手段です。
集団心理・関係性を踏まえたチェックリスト
チームが崩れる時、多くは「雰囲気」で気づくのが遅れます。
そこで役立つのが、集団心理や関係性の“兆候”をチェックする視点です。
以下のような問いを定期的に振り返るだけでも、チームの状態を見える化できます。
- 会議で全員が発言しているか?
- 誰か一人に仕事が偏っていないか?
- 問題が起きたとき、個人ではなく「仕組み」を振り返っているか?
- 失敗を共有できる空気があるか?
- 新人や若手が意見を言える場があるか?
これは定性的な“心理的安全性”の測定にもつながるチェックポイント。 感覚ではなく、実態に基づいてチームの健康状態を見直せます。
崩壊を防ぎ、機能回復につなげるプロセス設計
問題を見える化したら、次は「どう立て直すか」です。
ポイントは、一気に変えようとせず、段階的に“プロセス”を設計すること。
- 最初は「今ある課題を出し切る場」を設ける
- 次に「やること」「やらないこと」の整理
- メンバーと一緒に“チームのありたい姿”を描く
- 目標/役割/会議体/評価の再設計に着手する
- 小さな成果を積み上げて、成功体験を共有する
「課題→構造→行動→文化」の順で設計すると、持続的に機能するチームが育ちます。 最初の一歩は、“課題がある”ことをオープンにできる環境づくりから始まります。
チームを立て直すには?|崩壊からの再生と組織強化の具体策

「うまくいっていないのは分かってる。でも、何から手をつければ…」 チームが機能不全に陥っているとき、リーダーや上司はプレッシャーと迷いの中にいます。
ただ、チームはゼロからつくり直さなくても、“整え直す”ことができる組織体。
このセクションでは、崩壊からの立て直しに必要な具体的な行動と仕組みづくりを紹介します。
自社組織の状況に合わせた組織強化についての資料は、
こちらからお問い合わせください↓↓
リーダー・上司が果たすべき役割とは
まずは、リーダー自身が役割を再定義する必要があります。
マネジメントの本質は「指示を出すこと」ではなく、チームが機能する土台を整えることです。
- 課題を放置せず“言語化”して伝える
- 「できていないこと」を責めず、「どうなりたいか」に目を向ける
- 会議や1on1の質を上げ、“関係性づくり”の時間にする
- プレイヤー業務を一部手放し、チーム全体の進捗に向き合う
ポイントは、「まとめ役」ではなく「機能させる役割」にシフトすること。 “チームを動かす仕組みを考える人”として立ち位置を変えることが、再生の第一歩です。
信頼関係を築き直す行動と仕組み
一度崩れた信頼は、「がんばろう」では回復しません。
大切なのは、日々の行動と仕組みで信頼を“積み直す”ことです。
- 雑談やフィードバックを「ついで」ではなく“設計された場”にする
- メンバーの話を「聞く側」にまわる時間をつくる
- 意見を引き出す問いかけ(Why型ではなくHow型)を意識する
- 貢献や努力を見逃さず、定期的に“見える形で”称賛する
信頼とは、気持ちではなく“体験”の蓄積。 特に業務外の時間(振り返り・感謝・安心できる会話)こそ、信頼回復の最大の投資先です。
ビジョンと目的を“現場レベル”で再定義する
ビジョンや目的があっても、「現場に届いていない」状態では機能しません。
- チームのKPIが「なぜこれなのか?」を共有できているか?
- メンバー一人ひとりの役割が「ビジョンとどうつながっているか」理解されているか?
- 毎日の業務の中に、目的と意味づけが落とし込まれているか?
これらを再確認しながら、上から与えるのではなく、チーム全体で再定義するプロセスが重要です。 一度、“チームの存在目的”をゼロベースで言語化するワークも効果的。 自分たちでつくった目的は、行動に直結します。
多様な強みを活かすチームビルディング
再建フェーズでは、「一体感を取り戻す」のではなく、“多様性を活かせる関係性”に進化させることがポイントです。
- 得意領域や思考タイプをお互いに共有する機会を設ける
- プロジェクトや施策単位で“役割交代”をしてみる
- 「弱みを補い合う」ではなく「強みをかけ算する」組み方にする
- ワークショップ型で他者視点からフィードバックし合う
特に、自分の強みをチーム内で“認識されている感覚”が、エンゲージメントに直結します。 お互いの個性を知り、それを活かす設計にすることで、チームは“掛け算型”に進化します。
研修・コーチング・外部支援の活用法
自力でやろうとすると、組織内部だけでは突破できない“前提の壁”にぶつかることもあります。
そこで有効なのが、中立的な視点を持つ外部支援の活用です。
- 外部ファシリテーターによる対話型ワークショップ
- 管理職層へのコーチング導入
- 組織課題の“構造化”と対策整理を支援するプロフェッショナルの活用
- 評価制度や会議体の設計サポート
一時的な施策ではなく、「考え方を言語化し、行動に落とし込む支援」を選ぶことがコツ。 外部だからこそ見えること、言えることが、立て直しの加速剤になります。
チームの立て直しを検討する際は、こちらの記事も参考に具体的なステップを踏んでいきましょう。
再発を防ぐマネジメント戦略|安定して機能するチームをつくる仕組みとは
チームが一度立て直せたとしても、また元に戻ってしまう組織は少なくありません。
その原因は、一時的な対処だけで「仕組み」が変わっていないからです。
ここでは、チームの機能不全を繰り返さないためのマネジメント戦略として、 制度・文化・人材育成の観点から“再発しない組織づくり”の要点を整理します。
評価制度と仕組みのアップデートが鍵
「評価」が曖昧な組織では、どれだけ頑張っても“頑張り損”になるリスクがあります。
- 行動や成果が可視化されず、属人的な判断になっている
- チームへの貢献や支援行動が評価に反映されない
- 達成指標が形骸化し、現場との乖離が広がっている
これでは、チームワークより“自分を守る”行動が優先されるのは当然です。
評価制度の見直しで重要なのは、「成果だけを見る」のではなく、 行動・連携・プロセスに対する期待値を明確にし、納得感あるフィードバックを設計すること。
具体的には:
- 個人+チームのバランスを取った目標設計
- 評価者による行動観察とフィードバック研修
- “評価されるために動く”のではなく“チームで成果を出す”ための指標設計
評価が“機能すれば”、組織は自然と正しい方向に動き始めます。
心理的安全性が育つ“文化設計”のポイント
チームが再び崩れないためには、安心して働ける“職場の文化”が土台になります。
制度や戦略では補いきれない部分を支えるのが、「人の行動をつくる文化」です。
- 失敗しても“問い直せる”空気があるか?
- 会議で“指摘”ではなく“対話”ができているか?
- 役職やキャリア年数に関係なく“フラットに話せる場”があるか?
- 相互理解や感謝を示す“文化的習慣”が育っているか?
これらは、自然発生に任せていても生まれません。
たとえば:
- 週1回の雑談会・称賛タイムの導入
- フィードバック文化のワークショップ
- “心理的安全性”という言葉そのものを共有する研修
制度 × 習慣 × 言語化された価値観を重ねることで、 文化は「意識しなくても良い行動」が生まれる“下地”になります。
管理職・リーダー層の育成プランと支援体制
チームの安定性は、リーダーの育ち方にかかっています。
再発を防ぐには、偶然のマネジメントではなく、育てていく設計が必要です。
よくある課題は:
- プレイヤーとして優秀だった人が、育成や組織づくりに悩んでいる
- 管理職に「感覚」で期待しすぎて、体系的な支援がない
- 若手や中堅にリーダーシップの練習機会がない
これに対して、次のような仕組みづくりが効果的です。
- チームマネジメント研修+定期フォロー(講義+ケース+実践)
- 自分自身のマネジメントスタイルを言語化する機会
- 経営層との定例面談や1on1での“方針共有”の場
- ピアレビュー(同レイヤー同士の意見交換)で視点を増やす
重要なのは、管理職を“選ぶ”だけでなく、“育て続ける”体制を組織として持つこと。 育成が仕組みになったとき、チーム力は再現可能な“資産”になります。
チームの機能不全を繰り返さないためには、こちらの記事を参考にマネジメントを仕組み化する方法を導入し、属人化を脱却することが効果的です。