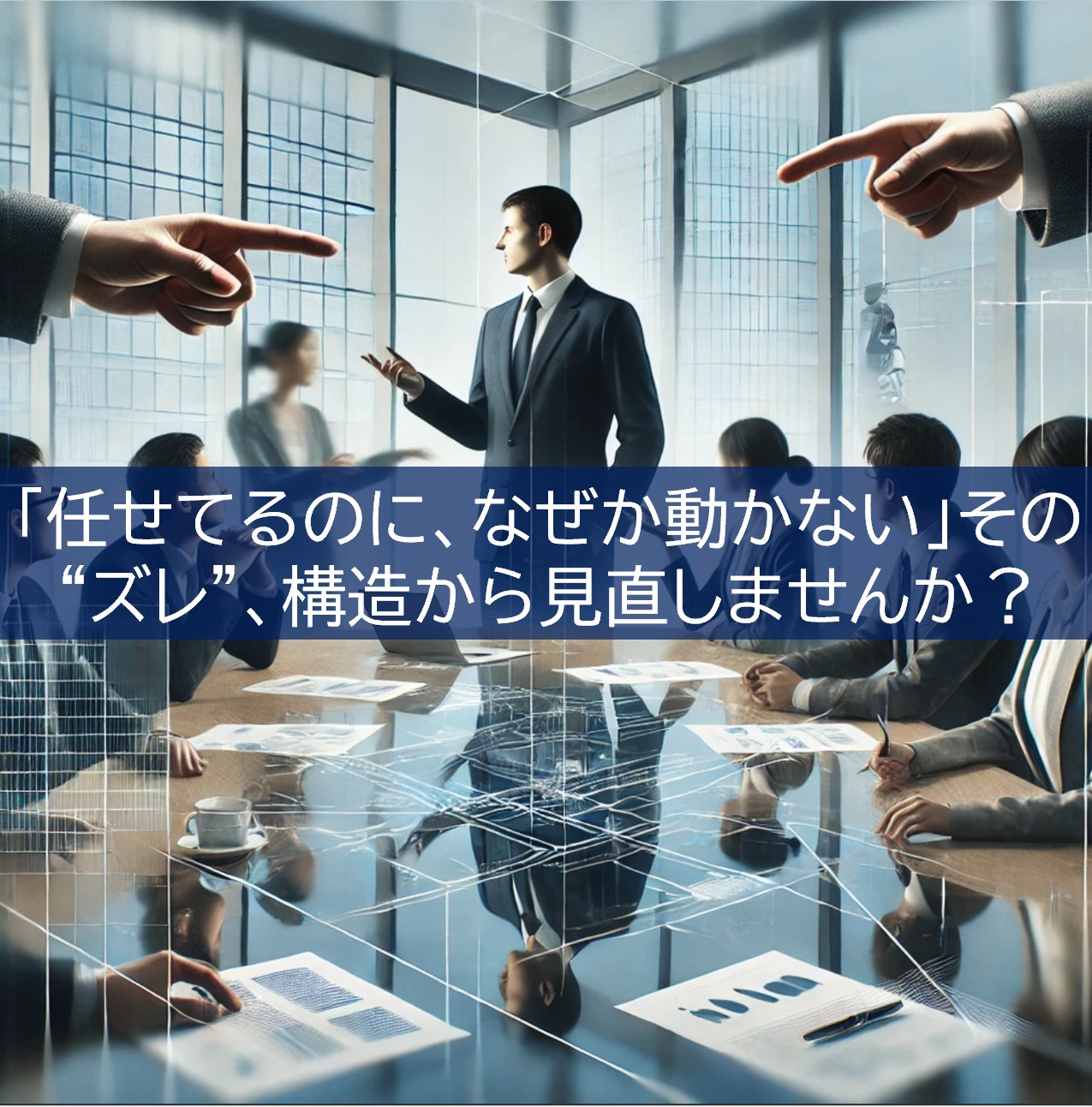──責任の所在があいまいな組織が、静かに崩れていく理由とは。
【プロローグ】
「うちは自主性を重んじるんです」
「現場の判断を尊重してます」
「指示は出さずに“任せてる”だけです」
一見、柔軟で風通しのよい組織に見えるこの言葉。
でも実は、メンバーに“放任”しているだけかもしれません。
「任せている」と「丸投げしている」は違う
一番の違いは、責任の所在です。
| 正しい“任せる” | 危険な“丸投げ” |
|---|---|
| 役割・権限が明確 | やることがあいまい |
| 進捗の確認がある | 放置で結果待ち |
| 責任を持って任せる | 結果だけ責める |
「リーダーは現場に任せるべき」と言われがちですが、
役割と責任が定義されていない状態では、“崩壊する組織”ができてしまいます。
よくある「任せすぎ」マネジメントの落とし穴
- チームメンバーの業務範囲が重複・空白だらけ
- 誰が判断者かわからず、意思決定が先送りに
- 成果が出なかったときだけ「なぜやらなかった?」と追及される
この状態が続くと、**「結局、誰も責任を取らない」**という組織文化が根づきます。
改善のための3つのポイント
①「役割」を明文化する
→ 組織図と連動して、「誰が」「何を」「どこまで」を可視化。
②「判断者=責任者」を明確にする
→ 決定プロセスの渋滞を防ぎ、自走するチームへ。
③「報告・連絡・相談」の仕組みを整える
→ チェックポイントの共有で、“丸投げ感”を減らす。
実際にあったエピソード(要約版)
ある中堅製造企業で、
「任せてるのに成果が出ない」と管理職が嘆いていたが、
実際には“誰が最終判断者か”が曖昧なまま、
複数の人が“同じ業務を並行して進めていた”ことが原因だった。
役割定義と責任者設定を行った結果、
3か月後にはプロジェクトの進行スピードが1.8倍に改善。
Bay3では、マネジメント設計の見直しを支援しています!
組織図と役割の整理
判断者の定義と意思決定フローの構築
「任せ方」研修や管理職サポート
【無料相談はこちら】
https://forms.gle/saX4FGLY6kRYfoer6
まとめ|“任せている”つもりで、実は組織を壊していないか?
- 自主性と放任は違う
- 任せるには「責任の設計」が必要
- チームがバラバラなら、“マネジメントの構造”から見直すべき
「リーダーは引くべき」ではなく、「リーダーは“仕組み”をつくるべき」なのです。
無料相談は、“責任構造の見直し”から始められます
Bay3では、次のようなステップで「任せ方のズレ」を見直しています:
- 組織図と役割の“重複・抜け”の整理
- 判断者の明確化と意思決定フローの再設計
- 管理職の“任せる力”を育てるサポート
「任せているのに動かない」「責任の所在があいまいで疲弊している」
そんな状態に、構造的なアプローチで一緒に切り込みます。
まずは30分、“どこにズレがあるか”を見える化してみませんか?
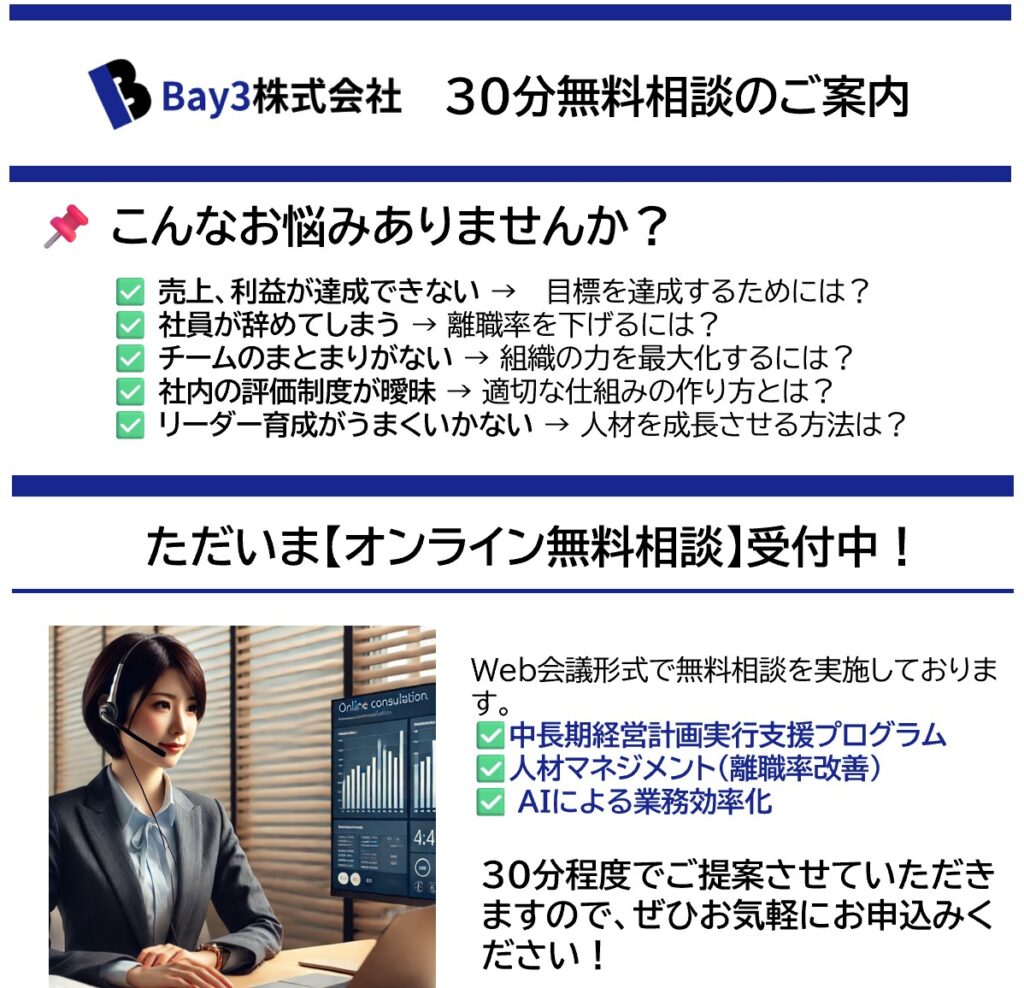
最後に問いかけです:
「任せているつもり」になっていませんか?
それは、本当に“責任を渡した状態”でしょうか?
もしメンバーが動かないと感じているなら──
変えるべきは「人」ではなく、「構造」かもしれません。