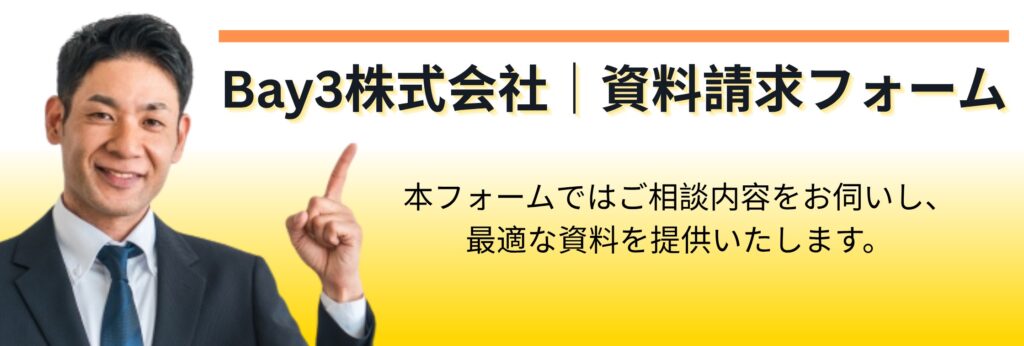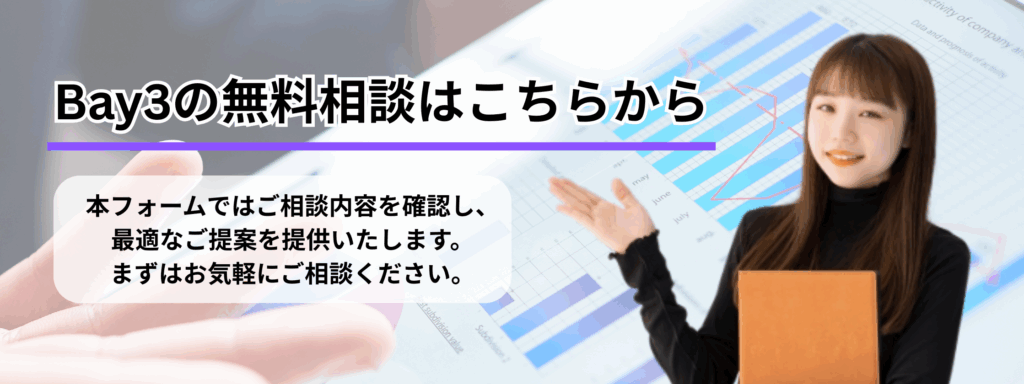スタッフの評価、どうしてますか?
「がんばってる子には上げてあげたいし、でも他の子とのバランスもあるし…」
そんなふうに感覚と経験でなんとなく決めている、という院長も多いのが現実。
でも実は、その“なんとなく”がスタッフの不満や離職を生んでいること、ご存じですか?
とくに今の歯科業界は、
- 歯科衛生士の確保が超・難関(求人倍率は20倍超)
- スタッフの入れ替わりが患者満足度に直結
- 優秀な人材ほど「納得感のある評価」を求める
つまり、「ウチは評価制度なんてまだ早いかな」と思っている医院ほど、早めに手を打つことで差がつきやすいのです。
この記事では、実際にスタッフ定着率を30%以上改善した医院の支援実績をもとに、 “導入すべきかどうか迷っている”段階の院長でも無理なく進められるよう、評価制度づくりを7ステップで解説していきます。
歯科医院で人事評価制度が必要な3つの理由

人が育つ医院には、共通して“評価の見える化”があります。
「感覚で給与を決めてた」「なんとなく褒めて終わってた」……そんな運用から抜け出したい院長に向けて、今なぜ“人事評価制度”が必要なのか、3つの視点で整理しました。
歯科衛生士不足時代の人材定着戦略
歯科衛生士の有効求人倍率は20倍超えが当たり前。採っても、すぐ辞められてしまう——この悩み、全国の院長が抱えています。
そんな中、“定着しやすい医院”には、評価制度があるんです。
- 「頑張りをちゃんと見てくれてる」という実感が生まれる
- 昇給・賞与のタイミングと根拠が明確になる
- 将来的なキャリアの道筋が見える
これらは、評価制度があって初めて実現するもの。
スタッフから「長く働きたい」と思ってもらえる医院は、評価の仕組みを整えている医院です。
給与・賞与決定の透明性確保
「この給与、なんでこの金額なんですか?」
こんな質問をスタッフから受けた経験、ありませんか?
給与や賞与を“なんとなく”で決めてしまうと、
- 優秀な人材ほど不満を持ちやすい
- 公平性が伝わらず、離職リスクが高まる
- 新規採用でも“魅力ある職場”に見えにくい
つまり、給与の根拠が曖昧だと、評価制度がないことのデメリットが露呈します。
評価制度は「給与を説明できる院長」になるためのツールです。
賞与面談の場面でも、自信を持って向き合えるようになりますよ。
組織力向上と患者満足度の相関関係
医院が成長していく中で、スタッフ数が増えると起きるのが「院長の目が行き届かない問題」。
誰が何をどのレベルでやっているのか、把握しきれなくなります。
そこで評価制度があると、
- マネージャー層やチーフスタッフが“評価の軸”を持てる
- 「この行動が評価につながる」と全員が理解できる
- 職場のチームワークや責任感が強くなる
その結果、スタッフの仕事ぶりが安定し、患者対応の質も向上。
つまり、評価制度の整備は「患者満足度」や「リピート率」にも効いてくるんです。
歯医者特有の評価制度設計のポイント
評価制度は「とりあえずExcel作ってみた」では機能しません。
特に歯科医院は、少人数かつ多職種混在という特殊な環境。
現場にフィットした制度をつくるには、「職種」「経験年数」「評価軸」を切り分けて設計するのがコツです。
職種別評価基準の設定方法
歯科医院では、歯科衛生士・助手・受付など、仕事内容もスキルも違うメンバーが混在しています。
全員に同じ評価項目をあてはめるのはNG。職種ごとの特徴をふまえて設計するだけで、「これなら納得」と言ってもらえる制度に近づきます。
歯科衛生士の評価項目(技術・接遇・継続学習)
歯科衛生士は技術職であり、患者対応のプロでもある存在。
「スケーリングがうまい」だけじゃ評価しきれません。
- 技術力(処置の正確性・スピード・ミスの少なさ)
- 接遇(患者への説明・声かけ・雰囲気づくり)
- 継続学習(外部セミナー参加、知識アップデート)
→「治療のクオリティ」と「患者満足度」の両方を支えるプロとして評価
歯科助手の評価項目(診療補助・患者対応・多業務対応)
助手さんは縁の下の力持ち。だからこそ**「目立たないけど大事な動き」が評価軸になります。**
- 診療補助(器具準備・片付け・アシストの精度)
- 患者対応(誘導・気配り・笑顔)
- 多業務対応(清掃・在庫管理・チーム連携)
→「医院の安定運営を支えている」という視点での評価が◎
受付スタッフの評価項目(接遇・事務処理・予約管理)
医院の“顔”であり、予約・会計などクリティカルな業務を担う存在。
接遇だけでなく、「管理力」も大事な評価ポイントになります。
- 接遇(第一印象・電話対応・お見送りの所作)
- 事務処理(カルテ整理・レジ・ミスの少なさ)
- 予約管理(空き枠管理・キャンセル対応・売上貢献)
→「ミスなく回す力」+「印象づくり力」の2軸で評価するのがカギ
経験年数別の段階的評価基準
同じ職種でも、1年目と5年目では求める水準が違います。
そこでおすすめなのが、「年次×役割」に応じた段階評価。
- 1年目 → 基本動作やスピード感
- 2〜3年目 → 応用力・後輩指導
- 4〜5年目 → リーダーシップ・チーム巻き込み
このように段階をつけることで、成長が見える・上を目指しやすい制度になります。
「次は何をできるようになればいいか」が本人にも伝わりやすくなります。
定量評価と定性評価のバランス
「人を数字で評価したくない」という院長の声、よく聞きます。
でも逆に「全部感覚で決めてる」と不満も生まれがち。
ここで大事なのが、定量×定性のハイブリッド評価。
- 定量評価:遅刻回数・目標達成率・業務処理数など
- 定性評価:姿勢・協調性・学ぶ姿勢・患者への態度など
定量があると納得性が上がり、
定性があると人間性や努力を評価できる。
このバランスが整うと、スタッフに「ちゃんと見てくれてる」感覚が伝わり、定着にもつながるんです。
人事評価制度導入の7ステップ実践手順

評価制度って、「作って終わり」じゃ意味がないんです。
制度そのものはシンプルでも、「現場に根づくまで」が本番。
ここでは、院長ひとりでも無理なく進められるよう、導入ステップを7段階に分けてご紹介します。
「評価制度って難しそう…」という方も、この流れを押さえれば大丈夫です!
Step1: 現状課題の整理と目標設定
まずは“そもそも何が困っているのか?”を明確にしましょう。
- 評価が主観的でスタッフに不満がある
- 給与の根拠がなく、説明に困る
- 頑張っている人が報われない空気がある
こうした声を洗い出したうえで、
「評価制度を通じてどうなりたいか?」を言語化します。
例:
→ スタッフのモチベーションが上がる医院にしたい
→ 給与の決定を公平にして院長の負担を減らしたい
最初の方向性が曖昧だと、制度がブレてしまうので要注意。
Step2: 評価項目・基準の設計
目指す方向が決まったら、次は“何を評価するか”の設計。
- 技術や業務の正確性
- 接遇やチームワーク
- 遅刻や目標達成などの定量指標
このとき「職種別」「年次別」に項目を分けるのがポイント。
さらに「この行動ができたら何点」など、点数化できる指標があると、評価の納得感がアップします。
Step3: 評価シート・ツールの作成
評価の設計ができたら、見える形に落とし込みましょう。
「点数だけでなく、コメント欄もあると伝わりやすい」「本人振り返り欄をつけると対話が深まる」など、コミュニケーションを促進する設計も効果的です。
Step4: スタッフへの説明・合意形成
制度が完成しても、「いきなり導入します」は危険。
現場を巻き込むには、導入前の説明会が超重要です。
- なぜ制度を導入するのか(背景)
- どんなルールで評価するのか(内容)
- 給与や昇給とどう関係するのか(影響)
この3点をしっかり説明し、「制度を一緒につくっていく」という空気感をつくるのがコツ。
このフェーズで信頼を失うと、制度が形骸化しやすくなります。
Step5: 試行運用と改善
いきなり本番はおすすめしません。
まずは**1〜3ヶ月の“お試し運用”**を設定しましょう。
- 評価してみたら項目が多すぎた
- 点数に差がつかなかった
- 評価面談の時間が足りない
など、実際にやってみて初めて見える課題もたくさんあります。
この時点で改善の余地を洗い出すことで、本格運用時の失敗を回避できます。
Step6: 本格運用開始
改善点を反映したら、いよいよ本格スタート!
- 評価スケジュールを決めて習慣化
- 院長・管理者で評価者を固定しブレを減らす
- 評価結果を給与や賞与に反映
評価制度が動き出すと、「頑張ったことが形になる」という空気がスタッフの中に少しずつ広がります。
小さな成功体験を積み重ねながら、制度の定着を目指しましょう。
Step7: 継続的な見直し・改善
制度は作った瞬間がゴールではなく、**“育てていくもの”**です。
- 評価項目が現場とズレていないか
- 給与との連動がうまくいっているか
- 評価する側・される側の納得感はあるか
少なくとも年1回の見直しは推奨。
スタッフからのフィードバックも拾いながら、より良い形にアップデートしていくことが、「辞めない組織」につながります。
中小企業での人事評価制度の導入手順については、こちらの記事でより詳しく解説しています。
評価制度を設計する際は、こちらの記事もあわせて読んでおくと、組織全体をスムーズに動かすヒントが得られます。
効果的な運用方法と定着のコツ
評価制度って、作ったら終わりじゃありません。
本当に大事なのは、“どう回すか”と“どう根づかせるか”。
ここでは、現場でスムーズに制度が浸透するコツを紹介します。
評価面談の進め方とコミュニケーション術
評価は、点数より「対話」が9割。
面談の場でのコミュニケーションが、その制度の信頼度を左右します。
- 最初に「よかったこと」を伝える
- 次に「伸びしろ」を具体的に伝える
- 最後に「期待してること」で締める
これだけでも、スタッフの受け取り方がぜんぜん違います。
評価面談は“ジャッジ”じゃなく“応援”の時間。
「上司と話せてよかった」と感じてもらえたら、制度はもう半分成功です。
給与・賞与への反映ルール
制度と給与がつながっていないと、スタッフの中で「意味あるの?」感が出てしまいがち。
かといって、がっつり連動させるのもハードルが高い…という医院は、まず“目安の仕組み”をつくるのが◎。
- 評価点数 × 基本昇給幅 → 昇給額を算出
- 評価ランク別に賞与倍率を設定(例:S=1.5倍、B=1.0倍)
「この点数なら、だいたいこれくらい昇給」というイメージがあるだけで、スタッフの納得感も院長の判断のしやすさも格段にUPします。
スタッフのモチベーション維持策
評価制度があるからこそ、“日常の声かけ”も制度とセットにして活きてきます。
- 月1回のフィードバックタイムを設ける
- スタッフ同士の「称賛コメント」を集めて紹介する
- 評価結果と連動した「表彰」「ごほうび」制度をつくる
数字だけじゃなく、「あなたを見てるよ」の実感があると、制度が“冷たい仕組み”じゃなく、“あたたかい文化”になります。
院長・管理職の評価スキル向上
制度はあっても、“評価する側”がぶれていたら定着しません。
そこでポイントになるのが、評価スキルのベースアップ。
- 面談時の伝え方研修(サンドイッチフィードバックなど)
- 評価の基準合わせMTG(月1回でもOK)
- 点数が分かれたときの“すり合わせルール”を決める
特に、複数の管理者が評価に関わる医院では、「誰がつけても同じ結果になる」が信頼の土台。
“評価者を育てること”が、制度の安定につながります。
評価者同士の基準のバラつきをなくすには、評価基準を仕組み化することも有効です。
\具体例や成功例など、もっと実例を見てみたい方はこちら↓/
よくある失敗パターンと対策
「制度を入れてみたけど、なんかうまくいかない…」
そんな声、実は少なくありません。
評価制度は設計より“運用”が勝負。
ここでは、ありがちな失敗とその乗り越え方をご紹介します。
制度が形骸化してしまう原因
作ったはいいけど、「最近評価してないな…」となってしまうパターン。
その原因、だいたいこのあたりです。
- 忙しくて評価面談を後回しにしてしまう
- 評価しても給与や賞与に結びついていない
- 院長・管理職が制度を使いこなせていない
つまり、「使われない制度」は徐々にスタッフの関心も薄れていき、
やがて“存在だけしてる制度”になります。
🔧対策:
- スケジュールを評価とセットで組み込む(月末・半期など)
- 評価に連動したフィードバック・表彰を実施
- 院長自身が率先して制度を活用し、習慣化の空気をつくる
スタッフの不満が高まるケース
「評価制度を入れたら、逆に不満が増えた…」というケースも。
実はこれ、“伝え方”と“納得感”に課題があることが多いです。
- 項目の意味が曖昧で、何をすれば評価されるのかわからない
- 評価者によって点数のつけ方に差がある
- 点数だけ伝えて、理由が共有されない
このあたりが原因で、「不公平」「不透明」という声が出やすくなります。
🔧対策:
- 評価基準を具体的に明文化&説明会で共有
- 複数評価者によるダブルチェック(すり合わせ)
- 点数だけでなく“言葉でのフィードバック”を徹底
継続運用できない理由と解決策
「制度が1回で終わった…」
これもるあるです。よくある要因はこの3つ。
- 評価シートやツールが煩雑で手間がかかる
- 運用の責任者が不明瞭で、誰も動かない
- 現場からの改善フィードバックを拾えていない
要するに、“仕組みの重さ”と“主体の不在”が継続の壁になります。
🔧対策:
- 評価フォーマットはシンプル&スプレッドシートで共有型に
- 評価運用の“係”や“チーム”を明確にする
- 年1回の制度見直しタイミングを事前に決めておく
評価制度が形骸化する原因は、そもそも業務が属人化しているケースも多いので、業務の仕組み化を学ぶことから始めるのも効果的です。
歯科医院の人事評価制度導入事例
「本当にうまくいくの?」と不安な方へ。
ここでは、実際に評価制度を導入してスタッフ定着率や患者満足度が改善した医院の事例をご紹介します。
成功事例1: スタッフ定着率80%改善したA歯科医院
📍医院プロフィール
- スタッフ10名規模の地域密着型クリニック
- 歯科衛生士の離職率が高く、毎年採用コストがかさんでいた
🔍 課題
- 評価や昇給が院長の感覚頼り
- 仕事へのやりがいが見えず、モチベーションが低下
- 院長自身も「誰がどれだけ貢献してるのか」把握しきれていなかった
🚀 実施内容
- 評価制度の設計(職種別・年次別の評価表を導入)
- 半年に一度の評価面談+スタッフ自己評価をセット化
- 評価点に応じた昇給ルールを設定(年1回)
🌱 成果
- 1年でスタッフの定着率が53% → 90%超に
- 「頑張りが見えるようになった」と自己評価の声多数
- 院長が“育てるモード”に切り替わり、チームとしての一体感が向上
成功事例2: 患者満足度向上に繋がったB歯科クリニック
📍医院プロフィール
- 都市部で開業5年目の保険+自費診療クリニック
- スタッフ数15名。患者対応の質にばらつきが出ていた
🔍 課題
- 接遇レベルがスタッフ間で差があり、クレームもちらほら
- 新人スタッフが育たず、離職が続いていた
- 患者満足度アンケートで「対応が冷たい」との声
🚀 実施内容
- 接遇・コミュニケーション・技術スキルを分けた評価項目を設計
- 定量(予約管理、処置件数)+定性(患者対応)をハイブリッドで評価
- 評価内容に基づく表彰制度とインセンティブを導入
🌱 成果
- 評価項目が“日常業務のガイド”として機能し、接遇品質が安定
- 新人教育が仕組み化され、OJT負担が減少
- 患者満足度調査のスコアが前年比+15ポイント改善
導入効果の測定方法と改善指標
制度が「効いてるかどうか」は、ちゃんと数値で見える化しましょう。
おすすめのチェックポイントはこちら👇
- スタッフ定着率(導入前→半年・1年後)
- 面談満足度(アンケートで「納得できた」「話しやすかった」)
- 昇給・賞与と評価の相関(A評価=◯円UPなど)
- 患者満足度アンケート(接遇・対応に関する設問)
- 業務ミス件数・処理スピードの変化
- 自己評価と上司評価のギャップ幅(すり合わせ指標)
効果が見えるようになると、スタッフも制度に前向きになり、「評価が成長につながる」文化が生まれてきます。
人事評価制度導入支援サービスのご案内

ここまで読んで「ウチでも導入してみたいかも…」と感じた方へ。
Bay3では、歯科医院に特化した人事評価制度の設計から運用まで、トータルでサポートしています。
Bay3の歯科医院特化組織コンサルティング
Bay3は「制度を作って渡すだけ」じゃありません。
現場の声に耳を傾け、スタッフの動きまで見ながら、実際に使われる制度を一緒につくっていくのが私たちのスタイルです。
- 歯科衛生士・助手・受付など職種別の評価設計
- 給与テーブルや等級制度の整備(昇給ルール含む)
- 評価シート・面談フォーマットの提供
- 説明会・面談練習など、導入支援もまるごと対応
- 評価運用後の改善・見直しまで伴走
実際のクライアントは、10〜50名規模の歯科医院や中小医療法人が中心。
「制度がうまく回らない」「院長ひとりで考えるのが限界」そんな声から始まるご相談がほとんどです。
無料診断・相談の申し込み方法
「制度って何から手をつければいいの?」
「そもそもウチに合ってるのか分からない…」
そんな段階でもOKです。
今なら、評価制度の“無料診断会”を実施中!
- 評価制度の現状チェック
- スタッフの声とのギャップ分析
- 院長の頭の中を“制度のカタチ”にする壁打ちMTG
まずはお気軽に、「話だけでも聞いてみたい」という感覚でご相談ください。
Zoom or 訪問のご希望にあわせて調整可能です。
📩 ご希望の方は以下から資料ダウンロード・日程調整をお願いします