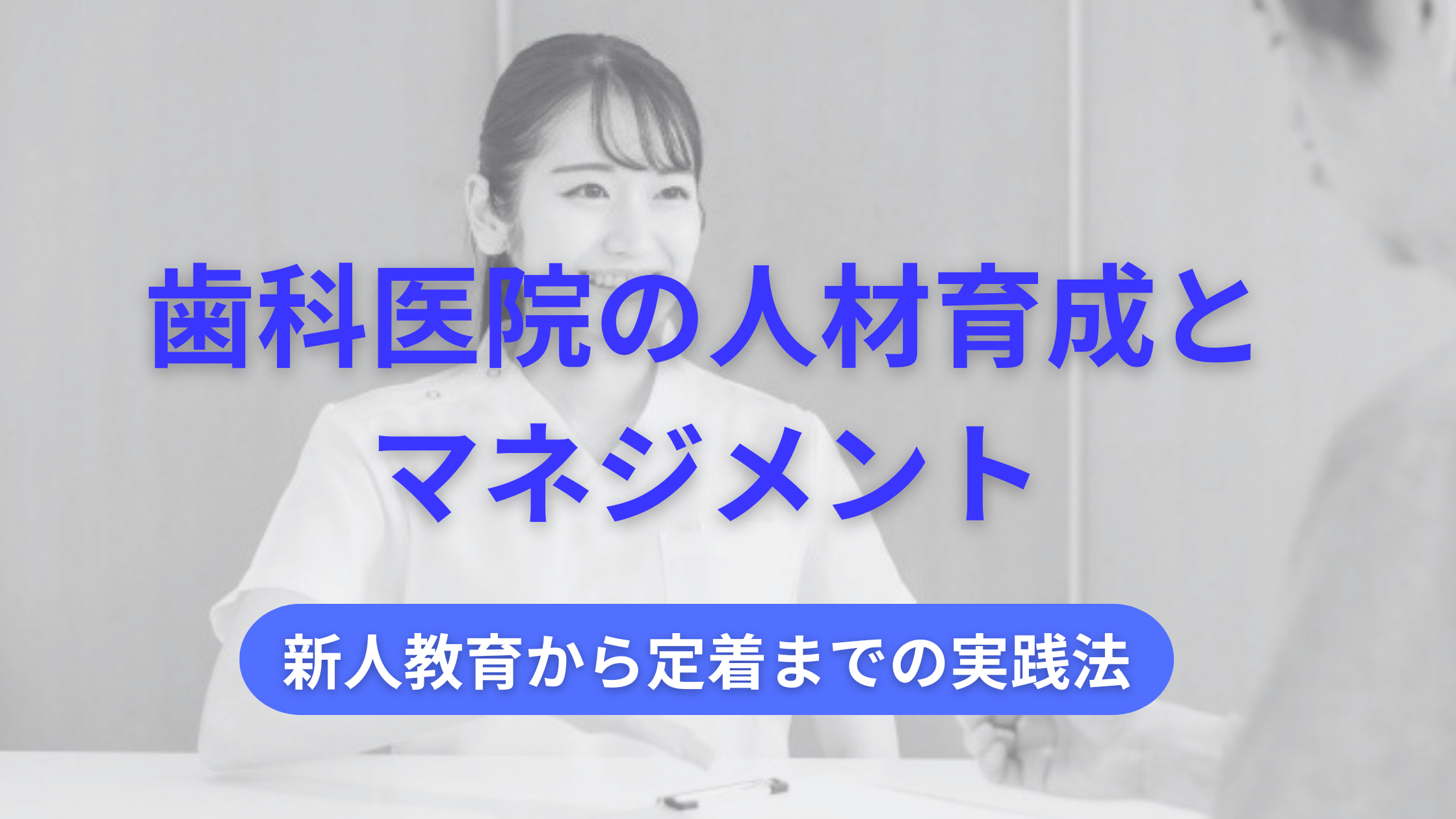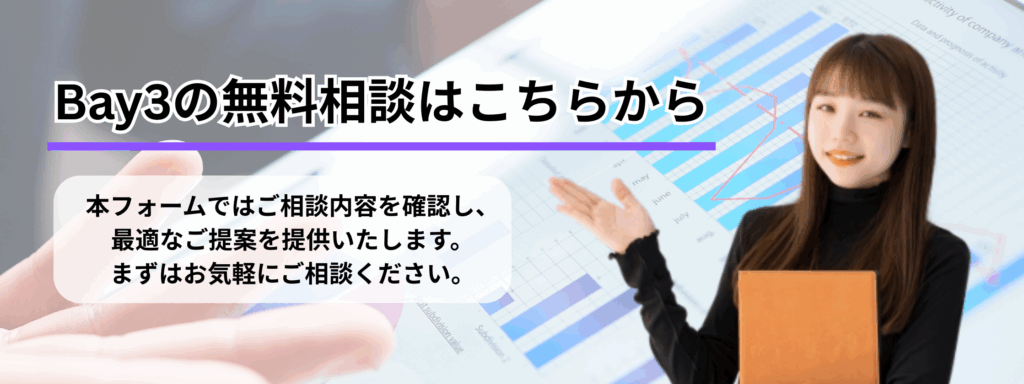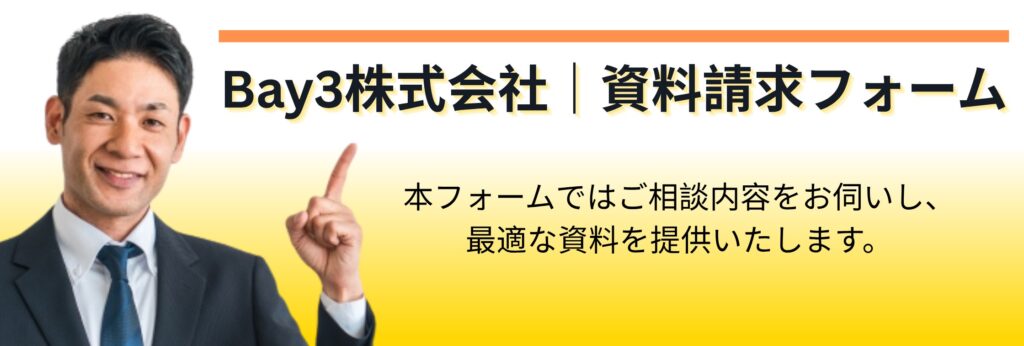歯科医院の経営を安定させるカギは「人」にあります。最新の設備を整えても、スタッフが定着しなければ、患者さんの信頼も経営の持続性も危うくなります。この記事では、新人教育から日々のマネジメントまで、歯科医院が抱えがちな課題を解決し、スタッフと患者の両方にとってプラスになる「育成と定着の仕組み化」を解説していきます。
本記事の狙いと全体像
人材育成を成功させるには「誰が」「どんな基準で」「どのくらいの期間で」育てるのかを明確にすることが欠かせません。そこで本記事は、院長・事務長・チーフがそれぞれの役割を理解し、組織全体で人を育てる流れをつくるためのガイドとしてまとめています。
「新人が入るたびに右往左往する」状態から脱却し、採用から定着までを一貫して回せる医院になること。その全体像をこの記事でイメージしていただけるはずです。
誰のためのガイドか(院長・事務長・チーフDH)
まず、このガイドは次のような立場の人に役立つ内容です。
- 院長:日々の判断を感覚ではなく「仕組み」に変えたい方
- 事務長:評価制度や会議設計を整備し、現場で再現性をもたせたい方
- チーフDH/DA:OJTやフィードバックをスムーズに回すためのチェックリストや声かけ例を知りたい方
つまり、歯科医院の中核を担うメンバーが「教育に迷わず取り組める状態」を目指すのが、このガイドの目的です。
目標KGI/KPI:定着率・患者満足・生産性の両立
次に、人材育成のゴールを明確にしましょう。ポイントは「スタッフが辞めない」「患者に喜ばれる」「生産性が上がる」の三拍子です。そのために、KGI(最終成果)とKPI(途中経過の指標)を設定し、組織全体で同じゴールを見据える必要があります。
指標例:離職率/再初診率/ユニット稼働/単価/紹介率
- 離職率:90日・半年・1年のタイミングで確認し、育成効果を測定。
- 再初診率(リコール率):教育が接遇に反映され、患者が継続的に来院しているかをチェック。
- ユニット稼働率:空き時間が多い=教育不足で現場が回っていないサイン。
- 単価:新人教育の成果が自費治療や物販の提案力に直結する。
- 紹介率:接遇品質が「紹介したい」と思わせるかを可視化。
期間目安:90日・半年・1年のマイルストーン
- 0〜30日:安全管理・接遇など最低限の型を習得。
- 31〜90日:OJTで「見学→共同→単独」の3ステップをクリア。
- 91〜180日:一人前として業務を自走し、チームに貢献。
- 181〜365日:評価制度と給与を連動させ、本人と医院の双方が納得できるキャリアを描く。
スタッフ定着は医院経営の重要課題です。こちらの記事で定着率を高める具体的な施策も確認しましょう。
歯科の人材育成を成功させるマネジメント原則
歯科医院で人材育成が長続きするかどうかは、マネジメントの仕組みにかかっています。感覚頼みでは属人化し、特定の先輩が辞めた瞬間に教育が崩れる…。そんな状態から抜け出すには「役割分担・評価軸・会議設計」という3つの柱が不可欠です。
役割分担の明確化(院長/事務長/チーフDH/DA)
人材育成は院長ひとりが背負うものではありません。
- 院長:ビジョンと最終判断を示す。
- 事務長:制度設計や会議運営など、仕組みの整備。
- チーフDH/DA:新人教育の現場リーダー。
この三者が連動することで「採用した人を確実に一人前に育てる」流れが生まれます。
RACIで可視化(決定・実行・支援・報告)
役割を曖昧にしないためにおすすめなのが RACIチャート。
- R(Responsible)実行責任:新人指導を担当するチーフ
- A(Accountable)最終責任:院長
- C(Consulted)相談役:事務長や外部コンサル
- I(Informed)情報共有:全スタッフ
「誰が決め、誰が動き、誰に相談し、誰に伝えるか」を一覧にするだけで、教育の抜け漏れは一気に減ります。
定量×定性の評価軸を“見える化”
「がんばっている気がする」では評価は成り立ちません。数値で見える定量と、行動基準を可視化する定性の両方が揃って初めて、スタッフの納得感が高まります。
行動基準(コンピテンシー)とスキルマトリクス
- コンピテンシー例:「患者への説明が3分以内でわかりやすい」「器具準備の正確率が95%以上」
- スキルマトリクス:各スタッフの「できる/指導できる」を表にし、誰がどの分野で強いか一目で把握。
面談と1on1の基本(頻度・フォーマット・記録)
- 頻度:新人は月2回、既存スタッフは四半期ごと。
- フォーマット:シート化(目標・成果・課題・次アクション)。
- 記録:紙ではなくExcel/クラウドで蓄積し、全員で共有。
会議設計が育成を加速する
教育を「日常業務に埋め込む仕組み」に変えるのが会議です。
週次運営会議/症例振り返り/朝礼・終礼の型
- 週次運営会議:進捗・課題・改善策を共有。
- 症例振り返り:臨床スキルの共有と学習。
- 朝礼・終礼:予定と所感を短く言語化する場。
5つの議題テンプレ:目標→進捗→課題→対策→決定
この型を守るだけで「会議が教育の場」となり、情報が流れず残るようになります。
採用〜オンボーディング〜定着:一貫フローの作り方

人材育成の失敗は「採用でズレが生まれる→オンボーディングが曖昧→定着せず離職」の流れが定番です。逆に言えば、採用から定着までを一貫したフローで設計すれば、多くの問題は未然に防げます。
採用基準と配属設計(欲しい行動特性を先に定義)
「即戦力かどうか」よりも「どんな行動特性を持つ人か」を先に定義するのがコツ。
例:チームワークを重視する医院なら「報連相の早さ」を必須条件に設定。
面接評価表とリファレンスの観点
- 評価表:基礎スキル/協調性/学習意欲の3軸。
- リファレンス:過去の勤務態度・退職理由を確認し、医院との相性を見極める。
30-60-90日オンボーディング計画
「最初の90日で定着が決まる」といわれます。医院全体で新人を育てる計画を持つことが必須です。
初日〜1週:安全・接遇・基本動線
まずは「安全と接遇」が最優先。医院の動線を理解し、最低限の安心感を持って働ける環境を整えます。
H5: 初日チェックリスト(鍵・更衣・衛生・帳票)
「更衣ロッカーの場所」「衛生管理ルール」「日報の書き方」など、初日から迷わせない仕組みを用意。
1か月:OJT(見学→共同→単独)と記録
「見る→一緒にやる→一人でやる」のステップをチェックシートに落とし込み、記録を残すことが重要。
3か月:評価面談・仮配属確定・次期目標
3か月で「どの業務を独り立ちできたか」を評価し、次のキャリアの道筋を本人に示す。
OJT設計(SOP×ロープレ×同伴)
- SOP(標準手順書)で基本を統一。
- ロープレで患者対応を練習。
- 同伴シフトで安心感を与える。
SBI/STARでのフィードバック言語化
「行動の具体例(Situation/Task)→何をしたか(Action)→結果(Result)」で伝えると、指導がブレません。
教材化:動画・手順書・チェックシートの運用
属人化を防ぐため、教材を資産化。新人が自習できる環境を作ることで、教育コストを減らせます。
定着施策(関係・成長・報酬のバランス)
人は「人間関係」「成長実感」「適正な報酬」の3つが揃わなければ定着しません。
メンター制度/ピアレビュー/称賛文化
- メンター制度:新人に先輩を1人つける。
- ピアレビュー:お互いの良い点を伝える習慣。
- 称賛文化:小さな成功を全員で喜ぶ。
こうした文化が根付くと、スタッフは「ここで働き続けたい」と自然に思うようになります。
👉 「新人教育を仕組み化したいけど、具体的にどう始めればいいの?」
そんなときは、まずは私たちに相談してください。
採用基準〜オンボーディング〜定着までの“失敗しない設計” を、貴院の状況に合わせてアドバイスします。
🔽 今すぐ無料相談を予約する
新人教育の実践:職種別カリキュラム
新人教育は「誰に」「どのスキルを」「どの順番で」教えるかがポイント。ここでは、歯科衛生士・歯科助手/受付・幹部候補の3つに分けて、カリキュラムの実例を紹介します。
歯科衛生士(DH)
クリニカル:SC/RP、TBI、メインテナンス
- SC(スケーリング)/RP(ルートプレーニング):基本操作をOJTで段階的に習得。
- TBI(ブラッシング指導):患者背景に応じた伝え方をロープレ。
- メインテナンス:リコール時に臨床と接遇を両立させる練習を。
接遇:説明・同意・再来促進のトーク
患者は「説明の仕方」でリピート率が変わります。
- 診療内容を専門用語ではなく“中学生でもわかる言葉”で伝える。
- 治療方針は同意を得るまで確認。
- 再来を促すトーク(「次は○日後が理想です」)を習慣化。
H4: KPI:リコール率/キャンセル率/物販率
- リコール率:新人DHが担当した患者の再来率を数値化。
- キャンセル率:接遇トークが習熟しているかをチェック。
- 物販率:歯ブラシやフロスなど提案力を評価。
歯科助手・受付/TC(カウンセラー)
受付動線・レセ連携・会計精度
- 受付では「待たせない動線設計」と「レセプトとの情報連携」が必須。
- 会計は誤差ゼロを目指すルールを設定。
TC面談の型:情報収集→提案→同意形成
TC(トリートメントコーディネーター)は患者の理解度と医院の収益を左右します。
- 情報収集:患者の不安や希望をヒアリング。
- 提案:治療計画を選択肢で提示。
- 同意形成:「納得して治療を受けてもらう」まで伴走。
幹部育成(チーフ/サブチーフ)
シフト設計・在庫・クレーム一次対応
幹部候補には「現場を止めない力」が必須。
- シフト調整は“誰が欠けても回る設計”を意識。
- 在庫管理はリスト化で標準化。
- クレーム一次対応はテンプレートでブレを防止。
コーチング基礎と1on1運用
- コーチング基礎:質問型で部下の思考を引き出す。
- 1on1:月1回、シートを用いて「振り返り→目標設定→次アクション」を明確化。
具体的な評価項目については、こちらの記事も役立ちます。
マネジメントを強化する“仕組み化”ツール
人材育成は「仕組み化」して初めて医院に根づきます。評価・会議・教材を整備することで、誰がやっても一定の成果が出る状態を目指しましょう。
評価制度:定量+定性のハイブリッド
評価表サンプル(等級×職種×行動項目)
例:
- 等級1(新人DH):基本施術の正確率、笑顔での接遇。
- 等級3(中堅DH):後輩指導力、患者教育の成果。
昇給・手当と連動する給与テーブルの考え方
評価は給与とつながって初めて「本気」になります。昇給条件を数値化して公開すると、不満も減りモチベーションが上がります。
タスクポイント制(バックオフィスの定量評価)
ポイント設計例:請求・発注・書類・電話対応
- 請求処理1件=○pt
- 発注作業=○pt
- 電話応対=○pt
感覚で評価されがちな事務を「ポイント」で見える化すると、公平性が一気に高まります。
会議テンプレとダッシュボード
週次進捗ボード/人材台帳/教育進捗ガント
- 進捗ボード:タスク完了率を一目で確認。
- 人材台帳:スタッフごとのスキル・評価履歴を一覧化。
- 教育進捗ガント:誰がどこまで習得したかを“進捗バー”で可視化。
院内LMS化(学習資産を蓄積)
動画・マニュアル・チェックリストの一元管理
- マニュアルを動画化 → 新人が隙間時間に学習可能。
- チェックリストで習得度を可視化 → 教育コストを削減。
LMS(学習管理システム)的に仕組みを作ると、「教え方がバラバラ問題」が解消されます。
👉 「評価制度や会議の仕組みを自院に合う形で整えたい…」
型はあっても、医院によって正解は違います。
評価表・給与テーブル・会議テンプレ を実際に見ながら、どうカスタマイズすれば成果につながるか一緒に考えましょう。
🔽 無料相談で自院に合った仕組みを一緒に設計
ありがちな失敗と回避策

歯科医院の人材育成は「制度は作ったけど回らない」「新人が定着しない」といった失敗談がつきものです。多くの院で共通するのは、仕組みがなく人に依存している状態。ここでは4つの典型的な失敗パターンと、実践的な回避策を紹介します。
属人化:特定の先輩しか教えられない
新人教育が「優しい先輩がいる間だけ機能する」ケースはよくあります。退職や産休でその先輩が不在になれば、一気に教育がストップ。結果として、新人が放置されて辞めてしまう…。
SOP化・交差OJT・ペア替えルール
- SOP化(標準手順書):業務ごとに「誰でも同じ説明ができるマニュアル」を作る。
- 交差OJT:新人を複数の先輩がローテーションで指導。先輩ごとの得意分野を分担できる。
- ペア替えルール:毎月指導者を入れ替える。関係性の偏りや知識の抜け漏れを防ぐ。
こうした仕組みがあると「人に依存する教育」から「組織で育てる教育」へ移行できます。
形骸化:評価が給与や会議に繋がらない
評価シートは作ったものの、給与や会議に反映されなければ「書くだけの作業」になってしまいます。スタッフも「どうせ昇給に関係ないんでしょ?」とモチベーションを失います。
評価→昇給→会議アジェンダへの“連結”
- 評価と給与:たとえば「評価80点以上で月◯円昇給」と明文化。
- 会議との連動:評価表の「改善項目」を週次会議の議題に組み込む。
- 昇給発表の場:院長から直接フィードバック+評価理由を説明。
評価が「給与にも会議にもつながる」とわかれば、スタッフは本気で取り組みます。
時間不足:教育が後回し
「診療が忙しくて教育は後で…」を繰り返すと、いつまで経っても新人は育ちません。結局、周囲のスタッフが疲弊して離職につながります。
週30分の“育成スロット”を固定化
- 毎週同じ時間に教育時間をブロックする(例:木曜の昼休み30分)。
- 議題は「今週できるようになったこと」「来週挑戦すること」を共有。
- 院長やチーフが同席して「短時間でも学びの場」を保証。
教育は“空き時間にやる”ものではなく、“予定表に入れる”ものだと考えましょう。
指標不一致:現場が追う数字がバラバラ
院長は売上、DHはリコール率、受付はキャンセル率…と、それぞれ違う数字を見ていると、チームがバラバラに動いてしまいます。
KPIの統一表と可視化
- 医院全体で「これだけは共通で追う」数字を定める。
例:離職率/再初診率/ユニット稼働率/紹介率。 - ダッシュボード化してスタッフ全員が見えるようにする。
- 会議の冒頭で毎回チェックし、全員が同じ方向を向ける状態に。
「数字が共有されるだけ」で、現場のまとまりは大きく変わります。
これらの失敗を回避し、組織全体の力を高めるには、組織マネジメントの観点が欠かせません。こちらの記事もぜひ参考にしてください。
成功事例と成果インパクト
失敗例と対策を理解したら、次は「成功している医院」をモデルにすると早いです。ここでは医院規模ごとの事例を紹介します。
小規模院(10〜15名):新人定着と院長の負荷軽減
- 導入施策:オンボーディングシート+月2回の1on1
- 成果:新人の定着率が半年で95%まで改善。
- インパクト:院長が「自分が全部教えなくてもいい」体制になり、診療や経営に集中できるようになった。
単院中規模(20〜40名):チーフ育成で属人化解消
- 導入施策:スキルマトリクスを作成し、OJTをチーフ中心に再設計。
- 成果:新人が1年以内に中堅業務を担えるように。
- インパクト:属人化が解消され、誰が辞めても教育体制が回るようになった。
複数院:評価×教育の標準化で横展開
- 導入施策:全院で共通の評価表・チェックリスト・会議テンプレを導入。
- 成果:法人全体でスタッフ定着率が20%改善。
- インパクト:教育や評価の仕組みを横展開でき、院ごとのバラつきが解消。
主要KPI推移の例(定着率/生産性/紹介率)
- 定着率:70% → 90%
- ユニット稼働率:65% → 82%
- 紹介率:10% → 18%
「仕組み化」に投資した分、生産性と売上がしっかり跳ね返ってくるのが特徴です。
7日間スプリント:すぐ始める実行プラン
仕組みづくりは「やらなきゃ」と思っても、全体設計から始めようとすると腰が重くなります。そこでおすすめなのが 7日間スプリント。
短期集中で最低限の仕組みを形にし、まずは回しながら改善していくやり方です。完璧を目指すより、小さく始めることが成功の近道になります。
👉 「他院の成功事例は分かったけど、うちに落とし込めるか不安…」
事例は参考になりますが、本当に知りたいのは “自分の医院ならどうなるか” ですよね。
実際の数値や運用ステップをもとに、無料相談でシミュレーションいたします。
🔽 成功事例を自院に当てはめる相談をする
Day1-2:役割RACIと90日オンボ作成
最初の2日間でやるべきことは「誰が何を担うか」を明確にすること。
- RACIで役割を可視化
- 院長=決定(Responsible)
- 事務長=管理・運営(Accountable)
- チーフDH=現場教育の実行(Consulted)
- 他スタッフ=報告・協力(Informed)
→ 曖昧さをなくすだけで「私がやるべき?誰の担当?」という混乱が減ります。
- 院長=決定(Responsible)
- 90日オンボーディング計画の作成
- 1日目に覚えること
- 30日でできるようになること
- 90日後に独り立ちできる姿
→ これを表に落とすだけで「新人をどうゴールまで導くか」が一目でわかります。
- 1日目に覚えること
Day3-4:OJTチェックリストと面談票
次のステップは、教育を仕組みとして“見える化”すること。
- OJTチェックリスト
- 各業務を「見学 → 一緒に → 単独」の3段階に分解
- 指導者がチェックして進捗を残す
→ 誰が見ても「どこまでできるか」がわかる状態に。
- 各業務を「見学 → 一緒に → 単独」の3段階に分解
- 面談票(1on1シート)
- 毎月の1on1で使う共通フォーマット
- 「できること/困っていること/次の目標」を記録
→ 属人的にならず、継続的に新人を支えられます。
- 毎月の1on1で使う共通フォーマット
Day5:会議テンプレ導入とKPIダッシュボード
「教育を現場の日常に組み込む」ために欠かせないのが会議と数字の見える化です。
- 会議テンプレの導入
- 進め方はシンプルに「目標 → 進捗 → 課題 → 対策 → 決定」
- 週1回、15分でも十分。課題が宙に浮かず必ず決定に落ちます。
- 進め方はシンプルに「目標 → 進捗 → 課題 → 対策 → 決定」
- KPIダッシュボード
- 離職率、再初診率、ユニット稼働率などをホワイトボードやクラウドで共有
- 毎週の会議で数字を振り返る
→ 「教育が医院の数字にどう効いているか」が明確になります。
- 離職率、再初診率、ユニット稼働率などをホワイトボードやクラウドで共有
Day6-7:試運用→振り返り→改善計画
最後の2日間は実際に“走らせてみる”段階です。
- 試運用:オンボ表・OJTリスト・会議テンプレを実際に使う
- 振り返り:良かった点/困った点を10分で洗い出す
- 改善計画:翌週からどう直すかを決める
小さな改善を毎週積み重ねれば、1か月後には「自院流の教育マネジメント」が形になります。
まとめ/次のステップ
ここまでで紹介した内容を整理すると、医院が安定して成長するには「採用→育成→評価→定着」の一連の流れを仕組み化して一本化することが重要だと分かります。
本記事の要点整理(採用→育成→評価→定着の一本化)

- 採用:面接評価表とリファレンスチェックでブレを防ぐ
- 育成:90日オンボ+OJT+1on1で新人を独り立ちさせる
- 評価:定量(数字)×定性(行動)を組み合わせる
- 定着:メンター制度や称賛文化で「辞めない仕組み」をつくる
これらが循環すれば、院長は経営と診療に集中でき、スタッフは安心して働けるようになります。
無料相談・資料(評価表サンプル/OJTチェック表/会議テンプレ)
「すぐに試してみたい!」という医院向けに、実際の現場で使えるテンプレートを用意しました。
ダウンロード案内
- 評価表サンプル:等級×職種ごとの行動基準つき
- OJTチェック表:新人が何をどこまで習得したか一目でわかる
- 会議テンプレ:15分で回せる議題進行シート
導入フローと費用目安
- 導入ステップ:①無料相談 → ②自院に合わせてカスタマイズ → ③現場トレーニング
- 費用感:小規模院なら月数万円、中規模以上は年単位の契約で導入事例多数
まずは資料をダウンロードし、「自院だったらどう使えるか?」を具体的にイメージしてみてください。その一歩が、教育と経営の未来を変えていきます。