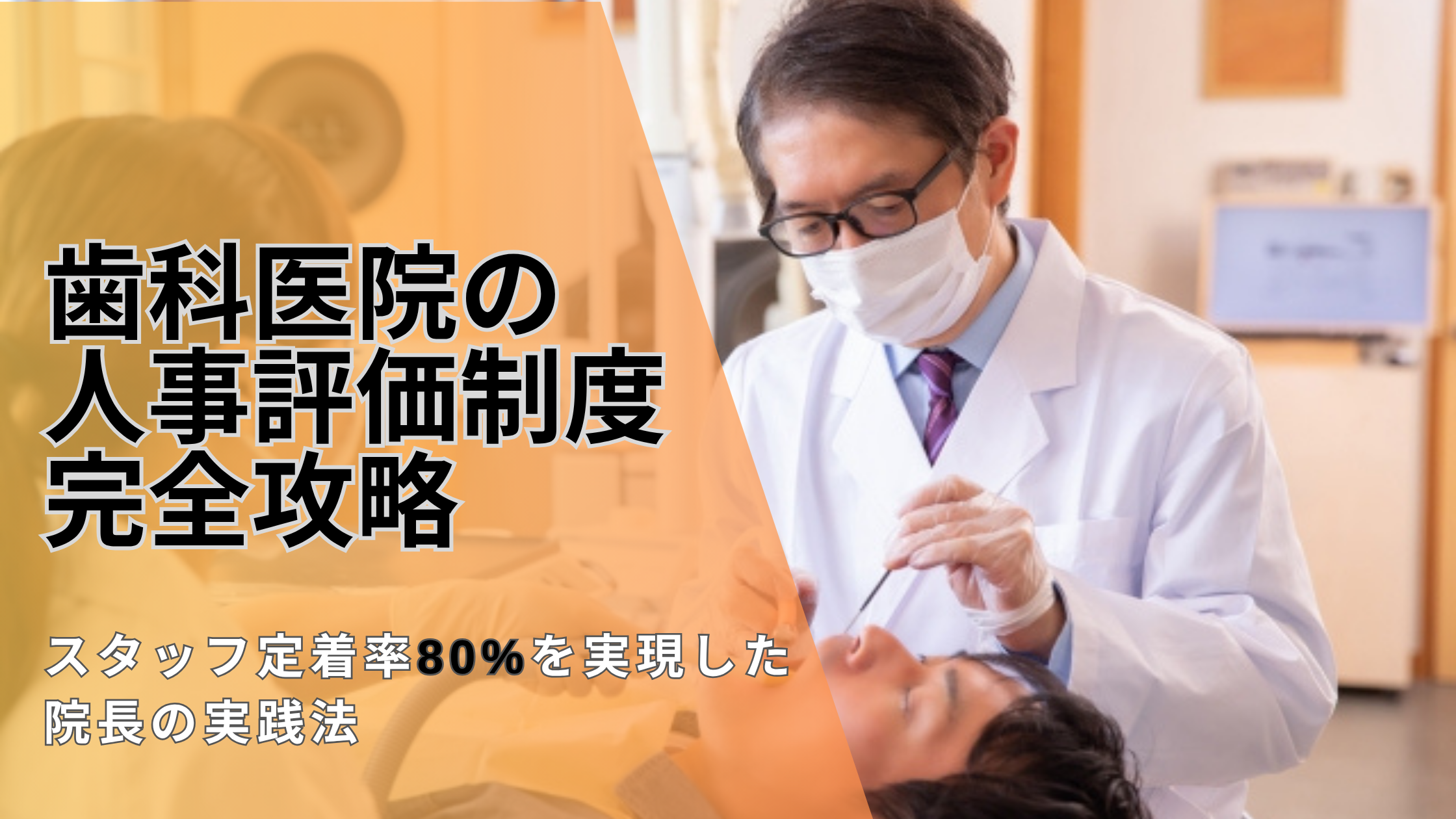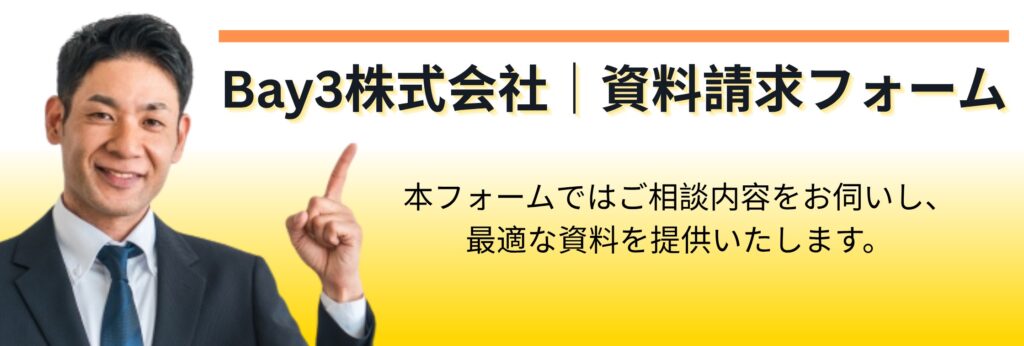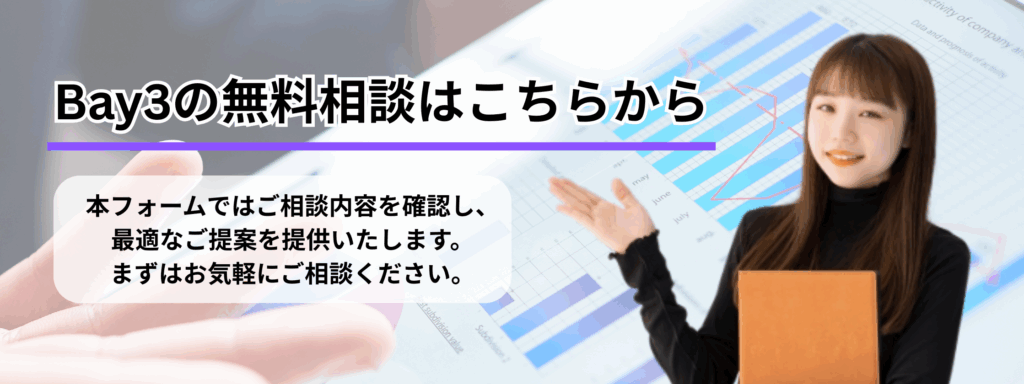「頑張ってる人をちゃんと評価したいけど、何を基準にすれば…?」
そんな院長の悩みに応える、歯科医院向け人事評価制度の完全攻略ガイド!
歯科衛生士の離職防止から給与決定の根拠づくりまで、“明日から使える”仕組みと、実際に定着率80%を実現した成功事例を徹底解説します。
歯科医院に人事評価制度が不可欠な理由
「ウチみたいな小規模でも、人事評価って必要なの?」
そう思っている院長ほど、制度を導入した後に「もっと早くやればよかった」と言います。
実は今、歯科業界は人材の争奪戦時代。
感覚で評価していた時代から、「見える化」して納得を生む時代に変わってきています。
ここでは、なぜいま評価制度が不可欠なのかを3つの視点で解説します。
人事評価制度の具体的な作り方や運用方法については、人事評価制度の作り方を完全解説した記事も参考にしてください。
歯科業界特有の人材課題と離職問題
歯科衛生士の有効求人倍率23.3倍の現実
歯科衛生士の求人倍率、23.3倍。これは、1人の求職者に対して20以上の医院が手を挙げている状態です。
つまり、「辞められたら即戦力の補充はほぼ不可能」。
求人を出しても応募ゼロ、なんて話もざらにあります。
この現実を踏まえると、 “採用”より“定着”が何よりも重要な経営戦略になります。
人材獲得競争激化による待遇改善圧力
求人競争が激化すると、自然と「給与」「待遇」「働きやすさ」のアップデートが求められます。
でも、やみくもに給与を上げるだけでは限界があります。
だからこそ必要なのが、頑張りと報酬がちゃんと連動する“評価の仕組み”。
納得感ある制度があるだけで、「ここで長く働きたい」と思ってもらえるんです。
従来の感覚的評価システムの限界
院長の主観による不公平感の発生
「この子は頑張ってる気がする」「最近ミスが多いな」
…その判断、もしかすると“主観”かもしれません。
院長の目線だけで評価が決まると、スタッフ同士でこんな声が出てきます👇
- 「え、あの人が昇給?何で?」
- 「私はずっとやってるのに評価されてない…」
これは、制度がないことによる“評価の不信感”です。
組織の空気を濁さないためにも、仕組みの見える化は必須です。
給与・賞与決定根拠の不透明性
「この昇給、なんでこの金額なんですか?」と聞かれてドキッとしたこと、ありませんか?
感覚で決めた給与や賞与は、説明がつかない=納得されないもの。
優秀なスタッフほど、評価の根拠が見えないとモチベーションを落とします。
制度を導入すると、
- 昇給や賞与の“物差し”が明確になる
- 「どうすれば上がるか」が伝えられる
- 説明責任が果たせる=信頼につながる
というメリットが生まれます。
人事評価制度導入による3つの効果
スタッフ定着率の向上
評価制度は、ただの仕組みではありません。
「見てくれてる」「認められてる」という感覚が、スタッフの定着率を大きく左右します。
導入前:離職が続いていた医院が
導入後:定着率80%以上に回復した例も。
「評価制度でここまで変わるんだ」と感じた瞬間でした。
組織パフォーマンスの改善
評価制度があると、チーム全体の動きが変わります。
- 何を求められているかが明確になる
- 自分の役割が見えやすくなる
- 適切なフィードバックが得られる
結果的に、ムダな業務や属人化が減って、組織力が底上げされるんです。
組織の成果を最大化する仕組みづくりのヒントは、こちらの記事でも詳しく解説しています。
経営の安定化と成長基盤の構築
評価制度は、経営判断の武器にもなります。
- 昇給額のシミュレーションができる
- 人件費の見通しが立てやすくなる
- 採用・育成・登用の判断軸が明確になる
つまり、“制度がある医院”は、経営がブレにくくなるんです。
制度=育成と組織づくりの“設計図”。これがあるかないかで、今後の成長スピードが変わります。
歯科医院に最適な人事評価制度の設計方法

「制度の必要性はわかったけど、どう設計すればいいの?」
ここからは、歯科医院に合った評価制度のつくり方をわかりやすく解説します。
ポイントは以下の3つ。
- 職種ごとに見るべき基準を変える
- 経験年数に応じて期待する役割を変える
- 評価と目標をリンクさせる
職種別評価基準の詳細設計
評価制度でよくある失敗が「全職種共通の基準を作ってしまう」こと。
業務内容が違えば、求められるスキルも違います。
ここでは、職種別にどこをどう評価すべきかを整理してみましょう。
歯科衛生士の評価項目(技術・患者対応・継続学習)
- 技術力:スケーリングやTBIの精度・処置時間・ミス率
- 患者対応:説明力・笑顔・安心感のある応対
- 継続学習:セミナー参加・学会報告・後輩指導など
→「手技だけでなく、人として患者から信頼されるか」がカギ。
歯科助手の評価項目(診療補助・効率性・協調性)
- 診療補助:器具準備・片付け・ドクターとの連携
- 効率性:段取り・タイムマネジメント・作業スピード
- 協調性:スタッフ間の連携・報連相・気遣い
→「目立たないけど欠かせない役割」だからこそ、見える化が大事。
受付スタッフの評価項目(接遇・事務処理・情報管理)
- 接遇:初対面の印象・言葉づかい・電話対応
- 事務処理:会計・カルテ管理・予約入力の正確さ
- 情報管理:個人情報の取扱い・業務メモの共有力
→「医院の顔」であり「信頼の窓口」。第一印象を左右する存在です。
経験年数・スキルレベル別の段階設定
「評価が偏る」「ベテランが評価されにくい」などの悩みは、年次別に基準を設けるだけで解決できます。
新人期(1-2年目)の評価ポイント
- 基本的な業務の理解と正確な実行
- 指示を素直に受け、報連相ができるか
- 先輩に頼りながらも、自立を目指しているか
→「できることを着実に積み上げる」が評価軸。
中堅期(3-5年目)の評価ポイント
- 業務の自走力、周囲への配慮
- 新人指導やチーム貢献の姿勢
- 自主的に学ぶ意欲・改善提案
→「周囲を見て動ける中堅」をどう育てるかが鍵。
ベテラン期(6年目以降)の評価ポイント
- チーム全体の流れを意識した働き方
- 院長・管理職のサポート役としての信頼感
- 組織改善・人材育成への積極的な関与
→「医院の土台を支える存在」としての振る舞いを評価。
目標設定と成果測定の仕組み
評価制度に“成長”を組み込むなら、目標設定は必須です。
でも、ただ「目標立ててね」だけでは形骸化します。
ここでは、成果を出しやすい目標の作り方と評価の仕組みを整理します。
SMART目標の設定方法
目標はSMARTで作ると実行しやすくなります👇
- S:具体的(Specific)
- M:測定可能(Measurable)
- A:達成可能(Achievable)
- R:現実的(Relevant)
- T:期限付き(Time-bound)
例)「3ヶ月以内に◯◯セミナーを受講し、学んだ内容をチームに共有する」
→「がんばります」より、「行動+期限+目的」がある目標が◎
定量評価と定性評価の使い分け
- 定量評価:件数・処理時間・達成率などの“数字”で測れるもの
- 定性評価:姿勢・協調性・患者との関係性など“感じる”部分
→両方を組み合わせると、「数字で納得」「人間性も評価」のバランスがとれます。
患者満足度との連動方法
患者満足度は、医院全体の成果を測る重要な指標です。
でも、数値だけで評価すると“アンケート対策”になるので要注意。
- アンケート項目を評価項目と連動
- フリーコメント欄の声を参考に面談
- 個人名が出た好意的コメントを“プラス材料”に活用
→「患者から見た評価」を制度に反映することで、チーム全体の意識が高まります。
人事評価制度の導入ステップとコツ

評価制度をつくるとき、最初に陥りがちなのが「急に始めて、急に頓挫する」パターン。
制度は“設計”と“浸透”のバランスが大事。
ここでは、準備・設計・運用の3フェーズに分けて、成功しやすい導入ステップを解説します。
導入前の準備フェーズ
現状分析と課題の整理
まずは“今、なにが困っているのか”を言語化しましょう。
- 評価が感覚的で、基準がない
- スタッフが昇給理由に納得していない
- 院長とスタッフで「頑張り」の定義が違う
こうした課題を洗い出したうえで、
「この制度でどう変えたいのか?」というゴールを明確にするのがスタートです。
スタッフへの事前説明と合意形成
制度を作ってから「こうなりました」では遅いです。
評価制度は“スタッフと一緒につくる”意識で進めるのがポイント。
- 制度導入の背景と目的を共有
- 評価がスタッフの成長や働きやすさにつながると伝える
- 「意見も取り入れて進めます」という姿勢を見せる
→これだけで、現場の反発や疑問がグッと減ります。
評価者(院長・管理職)のスキル向上
制度を支えるのは“評価する人の目”です。
主観・感情・ムラをなくすためにも、最低限の評価スキルを身につけておきましょう。
- 評価項目の理解(なぜこの項目があるのか)
- 面談スキル(フィードバック・傾聴・共感)
- 評価者同士の基準合わせ(すり合わせMTG)
→「評価の質=制度の信用度」です!
制度設計フェーズ
評価項目・基準の具体化
評価制度の心臓部とも言えるのが、評価項目と基準です。
ここで曖昧にすると、後の運用がぐらつきます。
- 職種別・年次別に分けて設計
- 定量+定性のハイブリッド評価
- 行動・スキル・成果の3軸でバランスを取る
「何をやれば評価されるのか」がスタッフに伝わる内容にするのがコツです。
評価シート・ツールの作成
設計した内容を、運用しやすいカタチに落とし込みましょう。
- Excelやスプレッドシートで管理しやすく
- 自己評価・上司評価の記入欄を分ける
- コメント欄・面談記録欄もあるとベター
「難しすぎない・使いやすい・書きやすい」が評価シートの3原則です。
給与・賞与との連動ルール設定
制度の「本気度」を示すのがここ。
- 評価ランクごとの昇給額・賞与倍率を明文化
- 数字だけでなく“プロセス評価”も加点対象に
- 即反映でなくても「昇給判断の材料になります」と伝えるだけでOK
→評価=お金、というイメージをスタッフに持たせることで、制度が“本物”になります。
具体的な「資料」や「相談」が必要な方は、こちらから無料でご提供します↓
運用開始フェーズ
試行運用での検証・改善
いきなり本格導入ではなく、まずは2~3ヶ月の試行期間をおすすめします。
- 実際にやってみて「面談に時間がかかる」など課題が見える
- スタッフや評価者から意見をもらえる
- フィードバックを元に改良しやすい
「完璧を目指すより、走りながら整える」ほうが制度は根づきます。
本格運用での定着化
改善後はいよいよ本番。
ここでは“制度を習慣にする仕組み”を整えていきます。
- 年2回 or 四半期ごとの定期評価
- スケジュールに組み込んで“やるのが当たり前”にする
- 評価後には必ず面談をセットで実施
→“続けること”が最大の信頼につながります。
継続的な見直し・改善サイクル
制度はつくったら終わりではありません。
スタッフの構成や業務が変われば、制度も見直す必要があります。
- 年1回の制度レビュー(スタッフアンケート活用も◎)
- 評価結果のバラつきチェック(評価者間の差)
- 「改善点あったら教えて」と現場に声をかける
→“アップデートされる制度”は、スタッフに信頼されます。
効果的な運用のための実践テクニック
評価制度を形だけで終わらせないコツは、“日常で使えるもの”にすること。
ここでは、制度をスタッフに届けるための実践テクニックを紹介します。
面談・給与反映・制度定着…ちょっとした工夫が、制度の命運を分けます。
評価面談の進め方とコミュニケーション術
面談前の準備と資料作成
「じゃあこの点数で。理由は…まあ、頑張ってたから」
これではせっかくの面談も、信頼を失います。
準備次第で、面談の“質”はぐっと変わります。
- 評価シートを事前に確認・コメント欄も埋めておく
- 良かった点・改善点・次の期待を整理しておく
- 必要なら面談チェックリストや台本も活用
→“ちゃんと準備してる”という姿勢が伝わるだけで、スタッフの受け止め方が変わります。
建設的フィードバックの伝え方
フィードバックの基本は「伝えたいことが伝わること」。
頭ごなし・ふんわり感想では、育ちません。
おすすめはサンドイッチ法(褒め → 指摘 →期待)
例:
「まず〇〇の部分、本当に助かってます!(褒め)
ただ、△△に関してはちょっとミスが目立ってるよね(指摘)
次は□□を意識してみて。期待してるよ(期待)」
→伝え方ひとつで、“指摘”が“応援”に変わります。
スタッフのモチベーション向上手法
評価制度があるからこそ、“ちょっとした声かけ”の価値が上がります。
- 面談後に「変化」を気づいてフィードバック
- 月1で「今月のグッジョブ賞」など軽い表彰
- 目標達成時にランチ招待 or ご褒美タイム
→制度に“あたたかみ”を加えることで、スタッフの心に火がつきます。
給与・賞与への適切な反映方法
昇給基準の明確化
「どうすれば昇給できるのか?」が分かれば、モチベーションは上がります。
- 評価点に応じて昇給テーブルを設計
- ランク別昇給幅の提示(例:Bランク→月2000円、Aランク→月5000円)
- 年1回の昇給タイミングを固定して運用
→不公平感ゼロの“頑張りの見える化”ができます。
賞与算定の透明性確保
賞与って、意外と“ブラックボックス”になりがち。
ここも評価とリンクさせることで透明感を出せます。
- 評価ランク別の支給倍率(例:A=1.5倍、C=0.8倍)
- 売上・組織全体の成績と連動するルールも可
- 面談時に「今回はこれくらい」と事前共有
→「納得できるか」が、制度の信頼を左右します。
処遇改善のタイミングと方法
制度を入れたタイミングや、スタッフの頑張りが“カタチになる瞬間”をつくりましょう。
- 制度導入と同時に、最低賃金や基本給の底上げ
- 昇給・手当付与などのサプライズ実施
- 「制度があるからこそ評価できた」とメッセージを添える
→小さな改善でも、“制度の成果”として伝えることで信頼度がUPします。
公平で納得感のある給与体系を構築するには、給与テーブルの作り方を解説した記事もぜひ参考にしてください。
制度定着のための継続施策
定期的な制度見直しの実施
制度は“使って終わり”じゃなく“育てていくもの”。
年1回の見直しタイミングを設けましょう。
- 評価基準のずれ・運用のムリを洗い出す
- 評価者・スタッフからアンケートでフィードバックを集める
- 見直し結果もスタッフに共有し「変えてるよ」と伝える
→“制度が変化に対応している”という安心感が定着につながります。
スタッフ満足度調査の活用
制度だけじゃ測れない、“心の声”も拾いましょう。
- 匿名アンケートで制度・面談・給与への意見を集める
- 定期的に「満足度○点」など数値化する
- ネガティブな声も「改善ネタ」として活かす
→評価制度は「仕組み」でもあり「対話の入り口」でもあるのです。
成功事例の共有と改善文化の醸成
良い取り組みは“個人の中”にとどめず、みんなでシェア。
- 「このスタッフの成長事例、ぜひ紹介したい」
- 「前回より面談がスムーズだったポイント」など共有
- 院内ミーティングで「制度にまつわるグッドニュース」を1個報告
→制度を“育てる文化”があると、評価制度が“医院の財産”になります。
よくある失敗パターンと対策法
評価制度って、作っただけではうまくいきません。
むしろ「制度を入れたことで混乱した」という声もよく聞きます。
この章では、導入時・運用時によくあるつまずきとその解決策をまとめました。
導入時に起こりがちな問題
スタッフの反発・不満への対処
「なんか評価制度とか、管理される気がする…」
こんな声が出るのは珍しくありません。
原因の多くは、“目的が伝わってないこと”。
🛠対策
- 初回説明で「制度=管理」ではなく「成長支援のツール」と強調
- 院長の思い(スタッフへの信頼・期待)を自分の言葉で伝える
- 「一緒に作っていきたい」というスタンスを見せる
→制度は“押しつけ”ではなく“共創”という空気づくりがカギ。
評価基準の不明確さによる混乱
スタッフにとって一番ストレスなのが「結局どうすれば評価されるの?」が分からない状態。
🛠対策
- 職種別・年次別に“見える基準”を明文化
- 行動例・NG例をセットで伝えると伝わりやすい
- 評価面談では、点数だけでなく“理由”を言葉にして共有
→“曖昧な制度”は不信を生み、“具体性”が納得感を生みます。
運用負荷の過大による挫折
最初に張り切りすぎて、管理が大変になり制度が止まる…というケースもよくあります。
🛠対策
- Excel・スプレッドシートで管理可能なシンプル設計にする
- 評価項目は「まずは10項目前後」など絞ってスタート
- 面談回数・タイミングも“できる範囲から”始める
→“続けられる制度”が、一番良い制度です。
運用中の典型的課題
制度の形骸化防止策
最初は使っていたけど、気づけば誰も触っていない…。
これは「制度が“目的化”してしまった」状態です。
🛠対策
- 評価制度の目的(育成・定着)を定期的にリマインド
- 評価シートだけでなく“面談文化”を根付かせる
- 年1回はスタッフと制度の振り返りを行う
→制度は“使い続ける理由”があって初めて残ります。
評価者間のバラつき解消
「A先生は甘いのに、B先生は厳しい…」
評価者によって差が出ると、制度の信頼はガタ落ちです。
🛠対策
- 評価者同士で“すり合わせMTG”を定期開催(点数の理由を共有)
- ダブルチェック方式(院長+管理者の2人評価)を導入
- 評価者トレーニングを実施(フィードバック研修など)
→“誰が見ても同じ評価”が制度の前提です。
継続的改善の仕組み化
制度を更新せず、3年放置…なんてことも珍しくありません。
時代も業務も変化する中、アップデートされない制度はすぐにズレていきます。
🛠対策
- 制度見直し月を“毎年◯月”と決めて固定する
- 「評価制度満足度アンケート」を年1回実施
- スタッフ代表も参加する制度改善プロジェクトを立ち上げるのも◎
→「制度が育つ仕組み」がある医院は、スタッフも育ちます。
成功事例で学ぶ人事評価制度の効果

評価制度って本当に効果あるの?
そう思ったら、まずは成功事例を見てみるのが一番早いです。
ここでは、実際に制度を導入して大きな成果をあげた2つの歯科医院のストーリーをご紹介します。
事例1:定着率30%改善のA歯科医院
導入背景と課題
・スタッフ数10名ほどの地域密着型クリニック
・毎年1〜2人の退職があり、採用コストと育成負担が悩みのタネ
院長は「ウチは人間関係も悪くないし、働きやすいはず」と思っていたが、
面談で「何を基準に評価されているのか分からない」という声が多く、
“評価の不透明さ”が離職理由になっていたことが判明。
具体的な制度内容
- 歯科衛生士・助手・受付で評価項目を分けて設計
- 定量(遅刻ゼロ・処置数)+定性(患者対応・学習姿勢)をMIX評価
- 面談は3ヶ月に1回、事前の自己評価とセットで実施
- 昇給ルールも評価スコアと連動(ランク制)
導入効果と成果指標
- スタッフ定着率:導入前55% → 翌年85%に改善
- 昇給基準が明確になり、「頑張れば評価される」という声が増加
- 院長が面談で“気づけるようになった”という自覚も
- 離職が減ったことで、教育の再投資が進み、医院の安定感がアップ
事例2:患者満足度向上のB歯科クリニック
制度設計のポイント
・スタッフ15名規模の自費比率が高い都内クリニック
・「接遇レベルにバラつきがある」「クレームが目立つようになった」という院長の気づきがきっかけ
制度設計のポイント👇
- 接遇・ホスピタリティの項目を評価に追加
- スタッフ全員が「患者視点」を意識できるよう、アンケート結果も反映
- 面談時には「患者さんの声フィードバックシート」も共有
運用での工夫点
- 評価結果を“チーム内で称え合う”カルチャーを意識
- 毎月1回の「〇〇賞」を導入し、小さな成功を可視化
- 患者からのポジティブコメントは、スタッフミーティングで紹介
→評価制度を“査定”から“育成と称賛の仕組み”へ転換
組織全体への波及効果
- 患者満足度アンケートスコア:前年比+18ポイント改善
- 「受付・衛生士がとても感じがいい」という声が増加
- スタッフの表情・言葉づかい・対応に明確な変化
- 結果的に自費率・リピート率にもプラスの波及
→制度ひとつで「医院の空気感」まで変わる。それを体現した事例です。
人事評価制度構築支援ツール・テンプレート
「自院でもやってみたいけど、ゼロから作るのは不安…」
そんな院長・事務長のために、Bay3では無料で使える評価制度ツール&テンプレートを用意しています。
すべて、実際の現場支援をもとに改善を重ねた“実務仕様”のコンテンツです。
無料ダウンロード資料
職種別評価シートテンプレート
歯科衛生士・歯科助手・受付など、それぞれの職種に合わせて
評価項目・基準をわかりやすく整理したフォーマットです。
- 定量・定性のバランスがとれた設計
- 年次別の到達イメージも記載済み
- 点数入力・自動集計も可能なスプレッドシート形式
→“とりあえず試してみたい”医院にも最適。
面談記録フォーマット
評価面談の質を上げるには、記録の一貫性が大事。
「面談で何を話したか」「次回に向けての目標」はすべてこのシートで一括管理できます。
- 評価者・スタッフのコメント欄付き
- SMART目標の記入ガイドあり
- 印刷用・共有用の両パターン対応
→面談が“ただの報告会”にならず、“信頼構築の場”になります。
導入チェックリスト
制度導入で抜け漏れを防ぐための、**“見落とし防止チェック表”**です。
- 導入前〜運用後までの各フェーズでやることを網羅
- スタッフ説明会・評価者育成・ツール準備まで細かく記載
- 院長・事務長・チーフの役割分担も整理可能
→「何から始めればいいか分からない」を完全サポート。
無料ダウンロード資料はこちら↓
制度設計・運用サポートサービス
Bay3の歯科医院特化コンサルティング
Bay3では、評価制度の設計から運用までを**“伴走型”で支援**しています。
- 職種別・年次別の制度設計(カスタマイズ対応)
- 評価シート・給与テーブルの設計代行
- 院長・管理者向け面談トレーニング
- 初期面談の同席・運用サポートまで含めたフル支援も可能
→“作って終わりじゃない”制度を現場で根づかせたい医院におすすめです。
個別相談・無料診断の申し込み
「うちの規模や状況でも評価制度って必要?」「制度はあるけど運用が上手くいってない…」
そんな方には、無料の個別相談・制度診断をご案内しています。
- 現行制度のチェック
- 評価項目・給与連動の改善アドバイス
- 導入有無に関わらず相談OKの安心設計
📩 ご希望の方は、以下のフォームから日程をご指定ください。
オンライン・訪問どちらでも対応可能です!