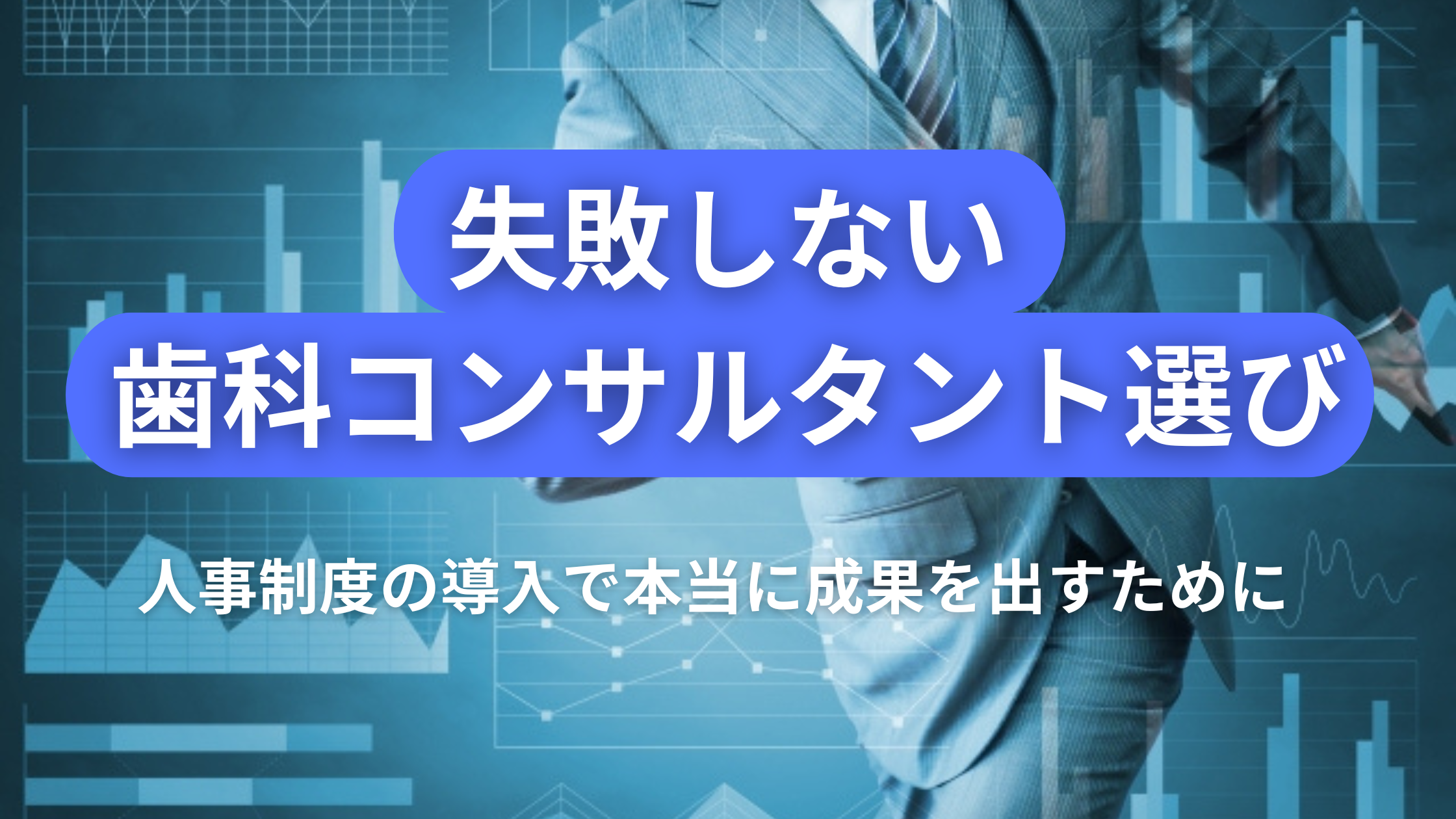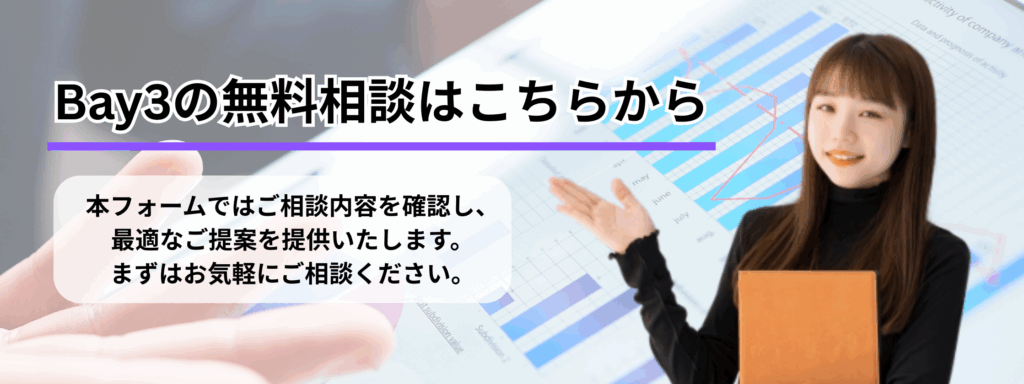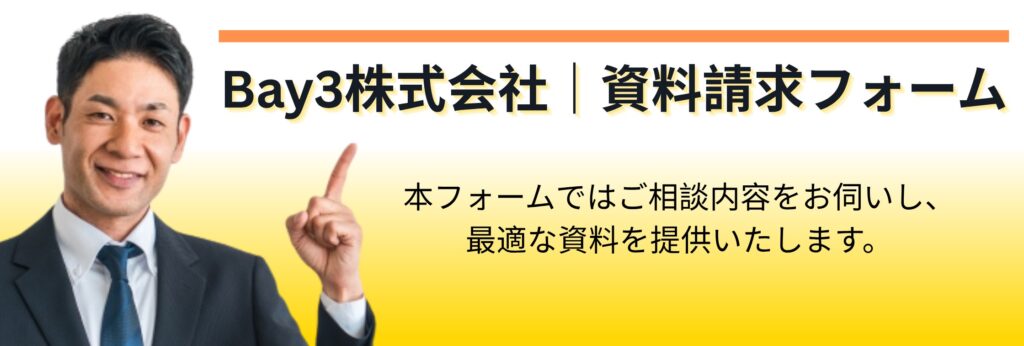「人事制度を入れてみたいけど、コンサルを入れるべきか…? それとも自分たちでやれるのか?」──歯科医院の経営者が必ずぶつかる悩みです。この記事では、人事制度の導入を検討している院長・事務長が、コンサルを使うべきかどうかを冷静に判断できるフローを解説します。
まず結論──コンサルを使う・使わないの判断フロー
結論から言うと、「全ての医院がコンサル必須」というわけではありません。
✅ 院内に制度を考えられる人がいる
✅ 運用の仕組みをきちんと回す時間がある
✅ 評価制度の雛形やチェックシートを自分で整備できる
こうした状況なら、まずは内製で十分です。
一方で、定着率が低い・離職が止まらない・評価制度を作ったけど機能していないといった課題が出ている医院は、外部コンサルを入れることで最短ルートを取れます。
離職やモチベーション低下を防ぐ評価制度の設計については、こちらの記事も参考にしてみてください。
使うべきケース(定着率悪化・稼働率低下・複数院化・時間不足)
「正直、もう手に負えない…」というサインが出ているなら、外部コンサルの出番です。例えば:
- 定着率が悪い:新人が半年以内で辞める。教育コストが垂れ流し。
- 稼働率が低下:ユニットは空いているのに売上が伸びない。原因が不明確。
- 複数院展開を予定:院ごとにルールがバラバラで、横展開が難しい。
- 時間不足:院長・事務長が教育や評価に割ける時間がない。
こうしたケースでは、ノウハウを持ったコンサルが「型」を提供してくれるので、制度がすぐに回り始めます。
内製で先に試すべきケース(運用徹底で改善余地が大きい)
逆に、まだ「仕組みを整える余地」が大きい場合は、まず内製で挑戦してみるのがおすすめです。例えば:
- 評価シートはあるが、会議で活用できていない
- 1on1や面談の仕組みは作ったけど、運用が形骸化している
- チェックリストやOJT表を用意したが、記録が残っていない
このような状態なら、制度自体よりも「運用徹底」がボトルネック。外部に頼る前に、自分たちで仕組みを回す工夫をするだけで改善できるケースが多いです。
3分自己診断チェックリスト(Yesが多ければ外部活用)
最後に、院長・事務長が3分でできる自己診断を用意しました。以下の質問に「Yes」が多いほど、外部活用を検討すべきです。
- 新人が1年以内に辞めることが続いている
- 評価制度を作ったが、昇給や会議に繋がっていない
- スタッフごとの業務レベルがバラバラで把握できない
- 1on1や面談をやっているが成果が見えない
- 院長や事務長が忙しくて制度運用に手が回らない
- 複数院で共通の評価や教育ルールが作れていない
Yesが3つ以上 → 外部コンサル導入を検討
Yesが1〜2つ → 内製で改善余地あり
Yesが0 → 今は不要、運用強化で十分
👉 この診断を読んで「やっぱり外部が必要かも」と感じたら、まずは気軽に相談してみてください。実際の評価シートや導入事例を見ながら、自院に合うかどうかを一緒に考えるのが一番早いです。
コンサルタントを活用してみたい場合は、
こちらから無料相談や資料の提供を行っています。
人事制度で何が解決できるか
「人事制度」と聞くと堅苦しい印象ですが、実際には日々の現場の悩みをスッキリ整理するための仕組みです。歯科医院が抱える 離職・採用難・属人化・モチベ低下 の悪循環を断ち切るには、人事制度がカギになります。
離職・採用難・属人化・モチベ低下の因果
- 離職が多い → 新人が育たず常に採用に追われる
- 採用難 → 応募が減り、選べず採らざるを得ない
- 属人化 → 「あの先輩しかできない業務」が増え、辞めたら崩壊
- モチベ低下 → 評価されない、給与に反映されない、未来が見えない
この4つはつながっていて、どれか1つが崩れると一気に悪循環になります。
評価・給与・キャリア・会議・1on1が変える日常
人事制度は「評価表や給与の仕組み」だけではありません。歯科医院の日常業務をスムーズに回す仕掛けでもあります。
- 評価:頑張りが見える化 → 「なぜ上がった/下がった」が明確に
- 給与:等級制度やテーブル化で納得度UP
- キャリア:3年後・5年後にどう成長できるかを提示
- 会議:週次で進捗と課題を共有 → 教育が“仕組み”になる
- 1on1:月1回の対話で不満を早期発見 → 離職防止
「なんとなく」で回っていた人のマネジメントが、数字と会話で整理され、医院全体が落ち着いてきます。
こうした人事制度の全体像や、スタッフ定着に繋がる仕組みづくりについては、こちらの記事で7つのステップに沿って解説しています。
成果指標(定着率/ユニット稼働/再初診率/紹介率)
制度導入の効果は数字に出ます。
- 定着率:新人が1年続くかどうか。教育コストの削減に直結。
- ユニット稼働:新人が育つと、稼働率が自然に上がる。
- 再初診率(リコール率):接遇や説明力が仕組み化されれば来院継続に。
- 紹介率:スタッフの接遇や満足度が患者の紹介につながる。
「感覚的に良くなった」ではなく、数字で変化が見えるのが人事制度の強みです。
歯科の人事制度コンサルタントとは?
では実際に「歯科の人事制度コンサルタント」とは何をしてくれるのか。社労士や研修会社とは違う役割があります。
役割とスコープ(評価設計/給与テーブル/運用伴走)
コンサルタントの役割は大きく3つ。
- 評価設計:職種別に「何をどう評価するか」を作る
- 給与テーブル:昇給・手当のルールを作り、見える化
- 運用伴走:作って終わりではなく、会議や1on1で回るまでサポート
要は、制度を「紙の上」から「現場で動く仕組み」に落とし込むのが仕事です。
社労士・税理士・研修会社との違いと連携ポイント
- 社労士:就業規則や労務の法律面が専門。評価制度の設計まではやらない。
- 税理士:給与計算や財務の視点が中心。制度そのものの設計には踏み込まない。
- 研修会社:研修やセミナーでスキルアップ支援はするが、制度設計や給与まで一貫はしない。
人事制度コンサルタントは「制度設計〜運用」まで一気通貫。そして、必要に応じて社労士・税理士・研修会社と連携して、トータルで仕組みを整えます。
自院との相性(カルチャー・規模・課題の適合)
良いコンサルを選ぶには「相性」が何より大事です。
- カルチャー:トップダウン型か、チーム型か
- 規模:10名規模か、40名以上か、法人全体か
- 課題:離職率か、評価運用か、給与テーブルか
例えば「新人がすぐ辞める医院」と「複数院を展開する法人」では、必要な制度もコンサルの関わり方もまったく違います。
👉 だからこそ、「相性を見極める」ことが、失敗しないコンサル選びの第一歩です。
内製とコンサルのメリット・デメリット

「人事制度は自分で作れるのか? それともコンサルを入れたほうがいいのか?」──多くの院長が迷うポイントです。どちらにも一長一短があるので、まずは整理してみましょう。
内製のメリット・デメリット(コスト・速度・再現性)
メリット
- 費用がほとんどかからない(外注費ゼロ)
- 自院の文化や状況を100%理解した上で作れる
- 試行錯誤しながらアジャストできる
デメリット
- 担当者の知識不足で制度が形骸化しやすい
- 本業が忙しい中で進めるのでスピードが遅い
- 属人的になり、再現性がない(作った人が辞めると運用が止まる)
👉 「時間はかかるけどお金は抑えられる」イメージです。
コンサル活用のメリット・デメリット(専門性・伴走・費用)
メリット
- 専門知識があるので「失敗パターン」を避けられる
- 他院の成功事例をもとに設計できる
- 仕組み化を一緒に伴走してくれるので定着しやすい
デメリット
- 費用がかかる(数十万〜数百万)
- 相性が悪いと制度が形だけになる
- 自院の状況を100%理解してくれるわけではない
👉 「費用はかかるけど成功確率は高い」イメージです。
デメリットを潰す方法(段階導入・トライアル・適合診断)
「コンサルは高い」「内製は不安」…そのデメリットを潰す方法もあります。
- 段階導入:まず評価表だけ作って、次に給与制度、と少しずつ進める
- トライアル契約:3か月だけ契約して“相性”を確認
- 適合診断:無料相談や診断チェックで、課題と解決策を見える化してから依頼
こうすれば「外してしまった…」というリスクを減らせます。
院長一人で抱え込みがちなマネジメントの課題を解決し、スタッフが自律的に育つ組織づくりについては、こちらの記事も役立ちます。
比較のしかた──要件定義→RFP→比較マトリクス
コンサルを選ぶときにありがちなのが「とりあえず話を聞いてみて、なんとなく決める」パターン。でもこれだと後から後悔しやすい。正しい流れは 要件定義 → RFP → 比較マトリクス の3ステップです。
要件定義テンプレ(範囲・KPI・期日・体制・会議頻度)
まずは自院の要件を整理しましょう。
| 項目 | 書き方例 |
| 範囲 | 評価表+給与テーブル/教育体制まで含める |
| KPI | 定着率80%/ユニット稼働90%/紹介率10% |
| 期日 | 6か月以内に制度稼働 |
| 体制 | 院長+事務長+チーフDHで運営 |
| 会議頻度 | 月2回+四半期レビュー |
👉 これを決めておくだけで、「結局何をお願いしたいんだっけ?」がなくなります。
RFP(依頼条件)の作り方と配布のコツ
RFP(Request For Proposal)は「提案依頼書」です。これを作らずに話すと、各社の提案がバラバラになり比較できません。
- 作り方:要件定義+希望予算+納期+成果イメージをセット
- 配布のコツ:2〜3社に同じ条件で渡し、横並びで比べられるようにする
ベンダー比較マトリクス(重み付け評価:実績・設計力・伴走力・費用・相性)
比較するときは「なんとなく」ではなく点数化しましょう。
| 項目 | 重み | A社 | B社 | C社 |
| 実績 | 30% | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 設計力 | 25% | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 伴走力 | 20% | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 費用 | 15% | 高い | 中 | 安い |
| 相性 | 10% | ◎ | △ | ○ |
👉 重み付けをすることで「結局どこが一番合ってるの?」が数字で見えます。
提案書の見方(テンプレ型かオーダーメイドか/再現性の根拠)
提案書を読むときは以下をチェック。
- テンプレ型:他院に配っているのと同じ資料ではないか?
- オーダーメイド型:自院の課題に沿った内容になっているか?
- 再現性の根拠:そのやり方で成果が出た事例があるか?
面談で聞く10の質問(連結設計・失敗時の打ち手・著作権・Exit条件)
面談では「聞きにくいけど後から絶対必要になる質問」をぶつけましょう。
- 制度と給与をどう連結させますか?
- 運用が形骸化したときの打ち手は?
- 過去に失敗した事例は?
- どの規模の医院が得意か?
- 伴走サポートの範囲は?
- 教材やテンプレの著作権は誰に帰属しますか?
- 社労士や税理士と連携できますか?
- 院内の会議に同席してもらえますか?
- 途中解約は可能ですか? Exit条件は?
- 実際に関わる担当者は誰ですか?
👉 この質問だけで「信頼できるパートナー」かどうかが一発で見抜けます。
料金とROI──費用対効果を数字で判断する
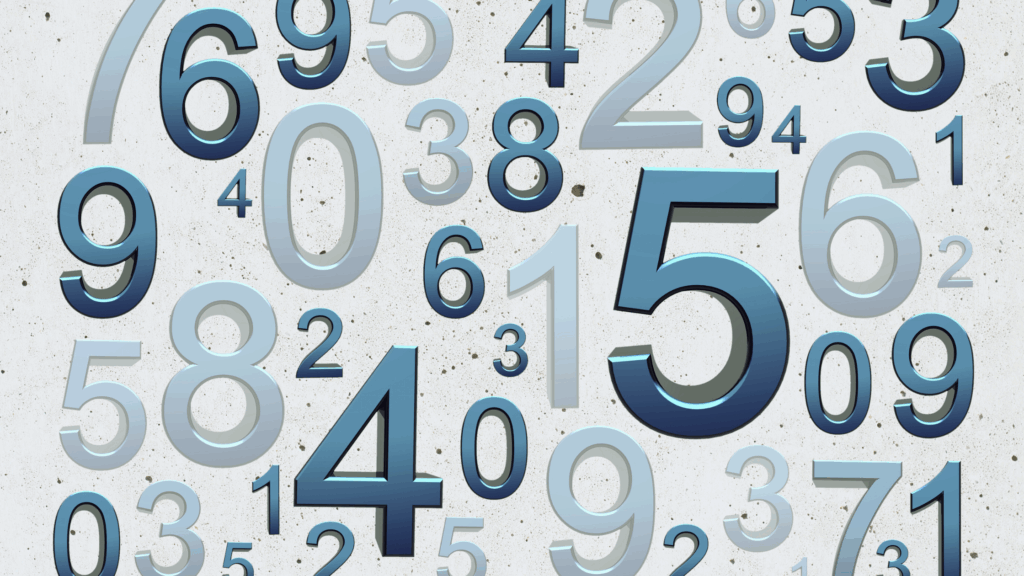
「高いけど効果があるのか?」「元が取れるのか?」──歯科コンサル活用の一番の不安はここです。費用レンジとROIを整理すれば、冷静に判断できます。
ざっくり費用レンジと内訳(診断・設計・運用伴走・研修)
コンサル費用は医院規模と依頼範囲で変わります。ざっくり分けるとこんな感じ。
| 項目 | 費用レンジ | 内容例 |
| 診断フェーズ | 10〜30万円 | 現状分析、ヒアリング、レポート |
| 設計フェーズ | 30〜100万円 | 評価制度・給与テーブル・キャリアパス設計 |
| 運用伴走 | 月10〜30万円 | 会議同席、評価シートレビュー、定着支援 |
| 研修・セミナー | 1回10〜30万円 | 院内研修、リーダー育成、スタッフ教育 |
👉 トータルでは半年〜1年で100〜300万円程度が一般的。
簡易ROIモデル(離職低減・稼働率改善・紹介LTV)
投資回収をイメージしやすいように、簡易モデルを紹介します。
- 離職低減
年間2人辞めていた→制度導入で1人に減少。
採用・教育コスト150万円が浮く。 - 稼働率改善
ユニット稼働80%→90%に改善。
月100万円の売上増=年間1200万円。 - 紹介LTV
紹介率が2%→5%に。
患者1人あたりLTV(生涯価値)15万円 × 年間30人増=450万円。
👉 この3つだけで年間数百万円〜1000万円超の効果が見込めるケースも。
回収期間の目安と意思決定ライン(6〜12か月で可否判断)
「投資に見合うか?」の判断は6〜12か月でROIを確認するのが現実的です。
- 6か月時点:スタッフの定着率や稼働率のトレンドを見る
- 12か月時点:採用・教育コスト削減や売上効果を数値化
- 意思決定ライン:「費用の2倍以上のリターンが出そうか」で継続判断
👉 漠然と「良さそう」ではなく、数字でYES/NOを判断しましょう。
契約前のSOW/SLAチェックリスト

契約前に内容を詰めずに走り出すと「聞いてない」「そんなはずじゃ…」となりがち。SOWとSLAをしっかり決めるのがトラブル回避のカギです。
対象範囲・成果物・改訂回数・スケジュール
- 対象範囲:評価制度だけか、給与・キャリア設計まで含むか
- 成果物:評価シート/給与テーブル/運用マニュアル など
- 改訂回数:1回までか、納得いくまで対応か
- スケジュール:いつまでに設計完了? 伴走は何か月?
👉 曖昧にすると「思ったより成果物が少ない」と後悔します。
週次/隔週レビュー・KPI・レポートの合意(SLA)
SLA(サービス水準合意)で運用のルールを先に握っておきましょう。
- レビュー頻度:週次 or 隔週ミーティング
- KPI報告:定着率/稼働率/会議実施率 など
- レポート様式:ダッシュボード形式 or テキスト報告
追加費用の条件・変更管理・著作権とデータ扱い
- 追加費用:範囲外の依頼が発生したらいくら?
- 変更管理:制度改訂を依頼したら再度見積り?
- 著作権:評価シートや資料は自院に帰属するか?
- データ扱い:スタッフ情報の管理方法や守秘義務は?
👉 このあたりが曖昧だと後でトラブル化しやすいです。
Exit条項(未達時の見直し・途中終了・引継ぎ)
最後に大事なのがExit。
- 未達時の見直し:KPI未達なら契約内容を再協議
- 途中終了:3か月前通知で解約可能などの条件確認
- 引継ぎ:コンサル終了後も運用できるマニュアルを残す
👉 「出口設計」があるかどうかで、安心感は段違いです。
リスクと回避策(“あるある”を先に潰す)

人事制度を導入するときに、歯科医院でよくあるつまずきポイントがあります。ここを事前に潰しておけば「せっかく作ったのに回らない…」を防げます。
形骸化リスク→評価→給与→会議の連結ルール化
制度が「紙に書いただけ」で終わる一番の原因がこれ。
- 評価をしても → 給与に反映しない → 「意味ない」
- 評価結果を会議で共有しない → 改善策が回らない
👉 ルールはシンプルでOK。
- 評価結果は給与テーブルに直結
- 評価シートの改善項目は会議アジェンダに載せる
- 昇給は院長からフィードバック付きで発表
現場反発→段階導入・現場代表の参画・称賛文化
「また新しいルールか…」と現場が反発するのは当然。
回避ポイントはこの3つ。
- 段階導入:まずは1職種(DH)から試す
- 現場代表の参画:設計段階からチーフを巻き込む
- 称賛文化:できたことを全員で共有・称賛する
👉 「現場を置き去りにしない」だけで導入の空気が変わります。
時間不足→週30分の育成スロット固定・代行タスク明確化
診療に追われて教育が後回しになるのも“あるある”。
- 週30分の育成スロットを固定(例:木曜昼)
- 代行タスクを明確化(育成時間中の電話対応は受付が代行)
👉 「教育は空き時間にやる」から「予定表に入れる」に変えるのがカギ。
依存/ブラックボックス化→成果物の院内利用権・運用手順書
コンサル任せにすると「コンサルがいなくなったら何も残らない」問題が起こりがち。
- 成果物(評価表・給与テーブル)は院内に著作権が残る契約にする
- 運用手順書やチェックリストを院内資産化する
👉 「自院で回せる状態」をゴールにするのが鉄則。
導入ロードマップ(30-60-90/180日)
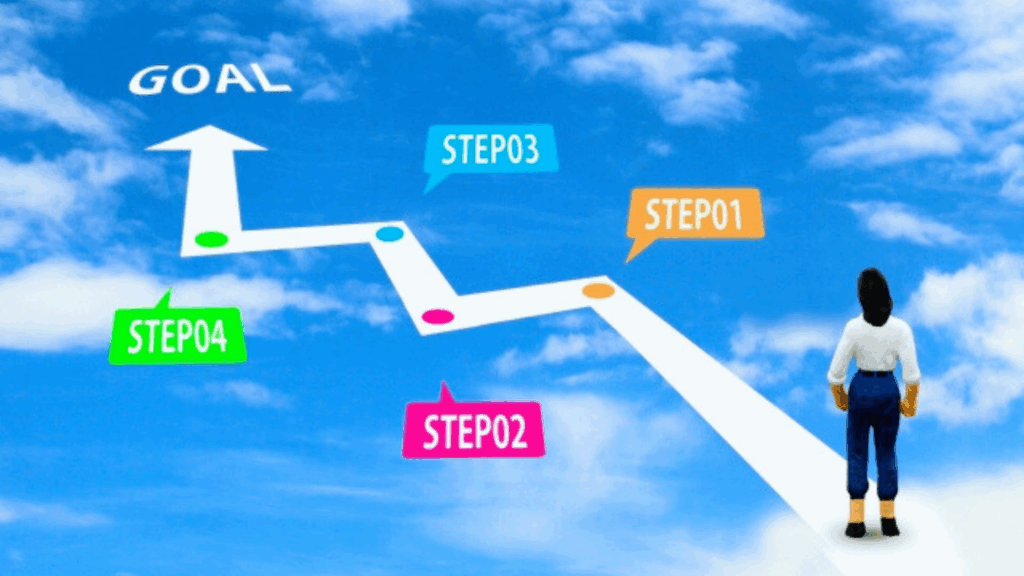
人事制度は「一気に完璧」ではなく「小さく導入→回して改善」が現実的。ロードマップで見える化しておくと安心です。
0–30日:診断・KPI合意・評価要素草案・会議テンプレ初版
- 診断:現状ヒアリング(離職率・稼働率など)
- KPI合意:医院として追う数字を決定
- 評価要素草案:職種ごとに仮の評価軸を作成
- 会議テンプレ初版:進捗共有フォーマットを導入
31–60日:パイロット運用(DH→受付→TC)・改訂①
- 歯科衛生士チームで試運用
- フィードバックを受けて受付・TCに拡大
- 制度設計の改訂①を実施
👉 小規模スタートで「うちに合う形」に寄せる。
61–90日:全体展開・給与テーブル仮連動・教育資産化
- 全スタッフに展開
- 給与テーブルを仮連動して「評価=昇給」の実感を出す
- OJTチェックリストや動画教材を蓄積
91–180日:本運用・定着レビュー・横展開(複数院)
- 本運用に切り替え、評価と給与を完全連動
- 半年レビューでKPI改善を確認
- 複数院への横展開準備
👉 180日(半年)で「制度が根づく」状態に持っていくのが目安。
よくある質問(費用・期間・院内負担・秘密保持)
制度導入で院長が一番気になるのは「現場にどれだけ負担がかかるか」「本当に守秘されるのか」。ここを先に潰しておきましょう。
どれくらいの内製工数が必要?
基本設計はコンサルがリード。院内で必要なのは以下の最小限の時間です。
- 院長:月1回 30分のレビュー
- チーフ:週1回 15分のOJT進捗共有
- スタッフ:評価面談に30分参加
👉 「仕組みづくりに追われて診療が止まる」という心配は不要です。
現行制度は活かせる?全部作り直し?
ほとんどの医院は「評価シートはあるが形骸化」「給与ルールはあるが連結していない」状態。
✅ 活かせる部分は残し、足りない所だけ追加が鉄則です。
ゼロから作り直すのはコスト高。既存制度を“土台”にアップデートするのが効率的です。
機微情報の取り扱い・守秘は?
- 個人評価や給与データは、NDA(秘密保持契約)を必ず締結
- データは院内クラウド管理、外部持ち出し禁止
- コンサルの成果物はすべて院内に著作権帰属
👉 「評価が外に漏れる」「給与データが使われる」といった不安を解消できます。
院長が不在でも進む運用の作り方
制度は「院長が指示しないと動かない」状態だと崩壊します。
- チーフや事務長に**“決定権”を委譲**
- ダッシュボードと会議テンプレで自走型運用に
- 院長は「最終レビューだけ」でOK
👉 仕組みさえ整えば、院長が出張や不在でも教育・評価は止まりません。
「本当にウチに合うの?」を悩むより、まずは30分で試すのが一番早い!
是非一度無料相談を行ってみてください。
持ち物(現行評価表・給与ルール・KPI)と当日の進め方
- 持参するのは「評価表」「給与ルール」「直近の数字(定着・稼働など)」だけ
- 相談当日は、ヒアリング→課題抽出→改善余地の診断まで実施
👉 事前準備はほぼゼロ。気軽に参加できます。
その場で作る「比較マトリクス採点」と「90日ロードマップ雛形」
相談時にお渡しできるのは、単なる感想ではありません。
- 比較マトリクス採点:複数コンサルの強み・弱みを点数化
- 90日ロードマップ雛形:自院がどんなステップで導入できるかの叩き台
👉 相談後すぐに「この会社に頼むか」「内製でいけるか」の判断ができます。
まとめ──“成果から逆算”で選べば迷わない
結局、選び方の基準はシンプル。「成果が出る仕組みにつながるかどうか」だけです。
最終チェックリスト(実績・設計連結力・伴走力・KPI・相性)
- 実績:同規模の歯科医院での導入事例があるか
- 設計連結力:評価→給与→会議の一貫設計ができるか
- 伴走力:導入後3〜6か月、現場に並走できるか
- KPI:定着率・稼働率・紹介率など数字を追えるか
- 相性:医院のカルチャーに合うか
👉 この5つでチェックすれば「選んで失敗」はまず避けられます。
「制度を整えたいけど、どこから手をつけるか分からない」
「コンサルを比較しているけど決め手がない」
そんな方は、まず無料相談で“自院に合う道筋”を一緒に描きましょう。
🔽 今すぐ無料相談を予約する